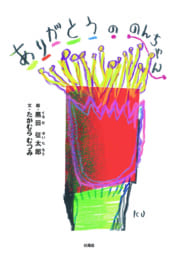余韻の残る人だった。表情も言葉も動きも柔らかで、濁り・淀みがなかった。彼女、美紀子さんがやって来たのは、桜がようやく開花し、春が本格的に動き始めようかという時だった。彼女はのっけから季節の流れに、雑草園の営みに溶け込んでいた。小さな新芽が枝々の至る所から吹き出ている楢(なら)・橡(くぬぎ)・栗などの下で、ハコベ・ギシギシ・ヨモギ等々、泉のように茂る若草を刈り、鶏小屋に運んだ。
静かな人だったが、言う時ははっきりと言った。九州に住みたいそうで、ではどこかに就職するのかと聞くと、
「私、お嫁さんになりたいんです。コンクリートのマチではなく、土の上でずっと暮らしたいんです。」
もちろん、気の合った縁のある人と、が大前提だが、それにしても彼女の発想は私には新鮮だった。
愛は個対個とは限らない。個と個を愛が包むということもある。場、空間、宇宙が愛を生み出すということもある。大地という場で、個と個が愛を創っていくということもある。個の中に愛が詰まっているというよりも、その個と個が見つめ合うよりも、個は空(くう)の方が空(くう)と空(くう)がいいかげんに、おおらかに、宇宙という愛に抱かれて生きていく方がいいのかもしれない。
例えば一人が山羊の乳しぼり、一人がちょっと離れた畑で草取り。顔を合わせるわけでも、話をするわけでもないが、互いに存在を感じ合っている。存在と存在とが静かに深い所で、感応しあっている。この場に一緒に居るというだけでなにかしら落ち着く。対人間だけではない。犬・猫・鶏・山羊・カラス・蜘蛛・アリ・・・・・草々、木々、風、雲、日の光・・・、いつも自然の声が聞こえてくるような、自然の心を感じているような。そういう関係。
山桜が五分咲きの頃、彼女と犬二匹と雑木林を歩いた。山桜は清らかな薄い雲のようだった。緑の粒が山じゅうに流れていた。静寂の中、ポツンとウグイスの幼い声が響いた。彼女は一心に山の気に浸っていた。七、八分後、林の奥に異様な金属製らしき建造物が見えた。産業廃棄物処分の焼却炉だ。私の説明を聞いて、彼女は無言でじっと林の奥を見つめた。
幸いこの二、三年、この焼却炉はほとんど休止しているが、十五年ほど前、稼動を始めた。グオーンと地の底から漏れ出るような音が山じゅうに響き、灰色の煙と重苦しい異臭が漂った。嫌というほど思い知らされた。余りにも当たり前すぎて気付かなかったことを。ただの空気の、ただの静寂の有難(´´)さ。どこまでも透き通ったこの山の気のかけがえのなさ。
もっとかなしいことは、この山の気が汚染されていることに、市長、議員を初めてして地元住民のほとんどが無関心なことだった。まして廃棄物を出す大都会の人々にとってはこの山のことなどそれこそどこ吹く風だろう。
保健所にかけあうしかなかった。徐々にだが改善されてはいった。
私達は有毒の廃棄物を燃やすということを、あまりにも安易に考えすぎてはいないだろうか。空気は水以上に必要不可欠な私達の生命なのだ。そして空気に混入した毒物は直接肺から血液に侵入する。食物よりもはるかに危険なのだ。まして放射能をわざわざ広範囲の大気中にばらまくなど、人間のみならずすべての命、この地球への許しがたい冒瀆だ。
美紀子さんを筑前大分駅まで送った日、桜は満開だった。穏やかに白みがかった青空を、ぶ厚くそれでいて肉感の無い妖艶な桜の白が覆っていた。かすかな風に一つ二つ花片が枝を離れ宙にゆれた。
桜が散って、春は走り始めた。落葉樹の緑の粒は面へと成長し、ウグイス色の雲となり山じゅうに漂った。いつのまにか新緑に変わり天に向けてモクモクと湧く樟(くす)は入道雲だ。
なんという伸びやかさ、柔らかさだろう。全身を包み込むような、生命の芯にしみこむような、この深い安らぎを、今までどうして感じることができなかったのだろう。春の生命のすさまじいばかりのエネルギーに圧倒されて、自身の生きる力を萎えさせてしまっていた。
ただ、ちょっと安らぎすぎてどっと気が緩み、また風邪をひいてしまった。腰の調子も悪い。こうなると雑草達の勢いについていけない。見る見るうちに緑の海だ。
どっかと座り込み、四つん這いになって、鶏の餌の青草を手で取る。ウーファーさんたちが鶏小屋の肥料をたっぷりまいてくれたお陰で、みずみずしく豊かに茂っている。特にハコベは透き通った柔らかさでいかにもおいしそう。雑草達に元気をもらい、少し汗も出て、ようやく身体が軽くなった。
見上げると、山藤の花が青空に連なっていた。しゃきっとした紫だった。その陰に、山椿の生き残りの真紅がひっそりと咲いていた。古い葉と葉の間から、蕾のような幼い葉がいくつも湧き出ていた。
2012年4月30日