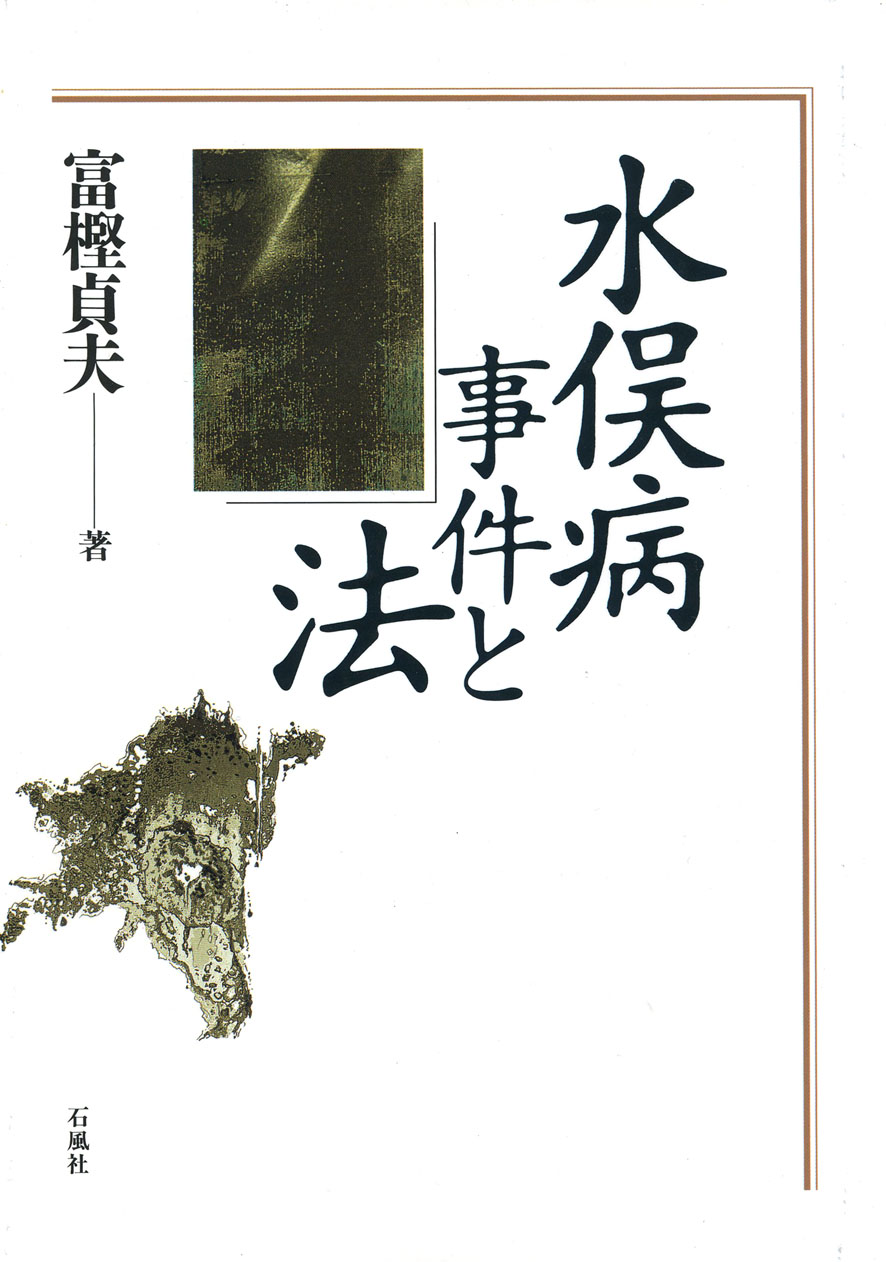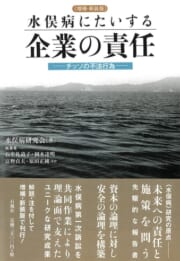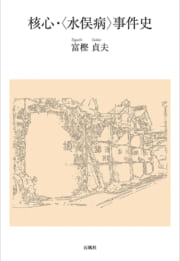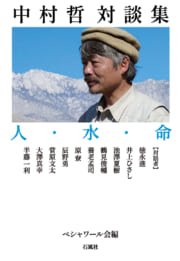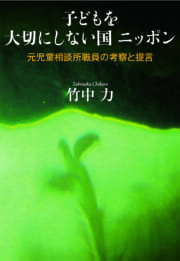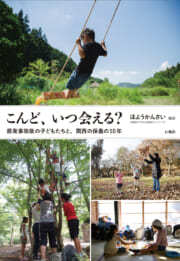ネット書店で注文
水俣病事件と法
水俣病事件における企業・行政の犯罪に対して、安全性の考えに基づく新たな過失論で裁判理論を構築。工業化社会の帰結である未曾有の公害事件の法的責任を糾す。──水俣病事件と共に生きてきた一法律学者の二十五年におよぶ渾身の証言集。
目次
1 水俣病裁判論序説
2 水俣病事件と法
水俣病患者の補償問題 公害法の視点
3 水俣病訴訟の法的諸問題
4 水俣病認定と法
「認定」と行政 医学診断と「認定」
5 水俣病裁判とともに
水俣病裁判の意味 水俣病と刑事訴追 未認定患者と訴訟 行政の水俣病対策
6 水俣病の過去・現在・未来
第三水俣病問題と医学 補償協定の空洞化と和解 幻のもうひとつの日本
7 水俣病事件関係資料
資料 水俣病事件裁判一覧
著者略歴
一九三四年生まれ。 山形県高畠町出身
東北大学法学部卒業後、同大学助手
熊本大学法文学部講師、同大学法学部教授などを経て、現在、熊本大学名誉教授。水俣病研究会代表、一般財団法人水俣病センター 相思社理事長を歴任
著書『水俣病事件と法』(一九九五 石風社)
『〈水俣病〉事件の61年 未解明の事件を見すえて』(二〇一七 弦書房)
編著『水俣病にたいする企業の責任 ─チッソの不法行為』(一九七〇 水俣病を告発する会)
『水俣病事件資料集上・下巻』(一九九六 葦書房)
『〈増補・新装版〉水俣病にたいする企業の責任 ─チッソの不法行為』(二〇二五 石風社)
関連情報
石風社より発行の関連書籍