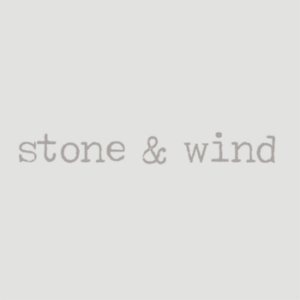昨年11月、高雄の美濃で行われたイベント『踩著一樣的月光,我們去尋找三毛的〈美濃狗碗〉』(『同じ月の光を踏みながら、三毛の[美濃狗碗]を探しにいこう』)で三毛との縁に関して話したが、そのとき話した三毛との縁をもたらしてくれた台湾の友人について少し付け加えたい。
1964年10月、日本の大学を卒業した後、私は台北にある台湾省立師範大学(現・国立師範大学)国文科へ一年間留学した。三毛との縁はそこの同級生・吉美がもたらしてくれたものだ。
私は華僑の学生たちと大学内の女子寮に住んでいたが、台湾現地の学生は新入一年間、寮の収容人数に限度があったため校外に部屋を借りて住んでいた。そのため私はクラスの同級生たちと教室以外ではほとんど交流の機会がなかった。
ただクラスの女性の級長(男女一人ずつ級長がいた)吉美はいつも何くれとなくこの一人の留学生に気を配ってくれていた。学校が休みになって帰省するとき、彼女は何度か新竹の家へ連れていってくれた。一家で歓迎してくれ、私は温かい気持ちに包まれ、台湾の人々の生活にも触れることができた。とても懐かしい。
吉美をはじめ当時の台湾の学生は非常に勤勉で、いつも勉学に励んでいた。今でも目に浮かぶのは、カーキ色の軍服のような制服に身を包み机に向かい本を読む姿、字を書く姿だ。いつも勉強していた。
一年後私は家の都合で帰国しなければならなかった。
台湾を離れてからも中国語の勉強を続けた。手紙を書くためだ。台湾で知り合った友人を失いたくなかった。彼女らは日本語ができない。私が中国語の手紙を書くしかなかった。私は少しでもまともな中国語が書きたかった。
自分でできることは一つだけ、ひたすら辞書を引いて本を読むことだ。中国語の本は当時私が住んでいた小さな町ではほぼ手に入らなかった。私は手元にあるわずかな本や、新しく出版された文法書などを繰り返し読んだ。
このように、帰国以後も寮で同室だった華僑の友人たちとはなんとか連絡を取り合っていた。
地元の学生である吉美は校外に住んでいたので普段はめったにおしゃべりする機会がなかった。だが彼女のことは私の心の中に確かな位置を占めており忘れることはなかった。
彼女に手紙を書こうと時々思ったが、もう少し上手に書けるようになってからだと思って先延ばしにしているうち、最初の手紙を送ったときには13年が過ぎていた。
吉美はすぐ返信をくれた。彼女はお嬢さん先生から母親先生になったと書いていた。そして私の手紙を「文情並茂的書信」(文の形式、内容ともに優れている手紙)とほめてくれた。うれしかった。彼女は師範大学国文系出身の優秀な国語教師だ。生徒を褒めることを知っている。励ましてくれたのだ。
そのころ私も二人の男の子の母親となっていた。吉美との文通が始まった。手紙のやり取りのほか、彼女は、私が中国語の勉強を続けられるようにと自分が読んだ本の中で面白いと思った本を一冊一冊送ってくれた。三毛の本はその中の一冊だった。
80年代に入ると台湾との行き来も楽になり、家族で台湾へ行き吉美一家と会ったこともある。その後吉美が教職を退いた90年代後半からは、彼女が日本に来たり私が台湾に行ったりして会う機会が増え、彼女といっしょに高知県の田舎の私の実家へも行った。その時は妹さんも一緒で、母や従兄たちが遠来の客を歓迎してくれた。
その後奈良へ行き、早春の法隆寺を散策し、人影もまばらな早朝の法隆寺を満喫した。彼女も日本の古い文化に興味があった。
吉美のお母さんは日本人だ。台湾の旧家に生まれたお父さんが日本で仕事をしていたとき二人は知り合い結婚した。1945年の初め、前年日本で生まれた男の子を連れて三人で中国大陸に渡った。
1946年1月、吉美は戦後間もない吉林省で生まれた。父親は母親に口がきけないふりをさせていた。その年の9月、二歳に満たない長男と生後8か月の吉美を伴って一家は大連から船で台湾の基隆に引き揚げた。
吉美のお母さんは私に、台湾留学中から「いつでも台湾の実家へ帰っておいで」と言ってくれていた。
お母さんは晩年には何度か日本へ帰国して親類を訪ねていたが、1997年9月、九州の旅が最後の帰国となった。車椅子の旅だった。私もお供をした。
太宰府で力士の博多人形を見て、「ああ、おすもうさん」とじっと動かず、買って帰りたいと言った。物をほしがるようなことのない方だった。郷愁に浸っていることを感じ、ああ、こういうものが懐かしいのだと、長い異国での苦労がしのばれじーんとした。お母さんは翌年の1月に台北で亡くなった。
吉美に感謝しているのはそれだけではない。彼女は一年在籍しただけの私と、同級生を繋いでくれたのだ。1968年卒業の国文系50余名のこのクラスは、共通テスト合格の台湾学生25名、現職教員の推薦入学者数名、華僑学生20余名(蒋介石政権は世界各地の華僑青年に優遇した教育の機会を与えていた)。クラスのほぼ全員が中、高、大学で教職に就き、定年退職後しばらく経った2008年、大学卒業後40年目に同窓会が立ち上げられた。第一回の同窓会に、わずか一年の在籍にすぎない私も招待された。それから毎年一回、四月に開催される同窓会(コロナの時期を除く)にずっと参加している。今年で17年目になる。
最初は昼食の集いだったが、一泊の旅になり、二泊の旅になり、皆が年をとってまた一泊となり、まだ続いている。今でも毎回二十人以上が参加している。
最初私はほとんどの方を覚えていない状態だったが、一年に一度とはいえ、二日、三日と同じ空間で過ごすうち互いに理解が深まった。様々なことを見聞きし、話し合い、台湾に対する新たな認識も少なからず得た。何よりも「よき友たち」を与えてもらったことは感謝にたえない。
吉美は私が興味を持っていることを理解してくれ、いろんなイベントを知らせてくれた。白先勇原作の舞台劇『遊園驚夢』、林懷民率いる「雲門舞集」のダンス、三毛の逝去20周年の記念行事など、ことあるごとに知らせてくれてそのたびに私は勇んで出かけていった。
この美濃のイベントの準備をしているうち、突然あることを思い出した。
あるとき吉美と台北の淡水河の岸辺の木陰に腰を下ろし、ペーロン(龍舟)競争の練習を見ていた。そのうちどちらからともなく言い出した。
二人で台湾と日本の間の文化交流のためになにかできるといいね。小さな橋をかける、粗末な丸木橋でもいいからと。そう言いながら二人とも大笑いした。夢が大きすぎることが分かっていた。
私は二人が夢見たこの二、三十年昔のことを思い出したのだ。それでスマホのラインで吉美に聞いた。私たち、台湾と日本の間に橋をかけたんじゃないかしら? 小さな粗末な丸木橋かもしれないけどね。これって私がほらを吹いていると思う? こんなふうに言っていい?
吉美からの返信にはこう書いてあった。「いいよ!」
それで美濃では二人がかけた橋のことを話した。それは小さな粗末な丸木橋かもしれないが、吉美と私をつなぐ確かな橋で、三毛はその橋を渡って日本にやってきてくれたのだ。