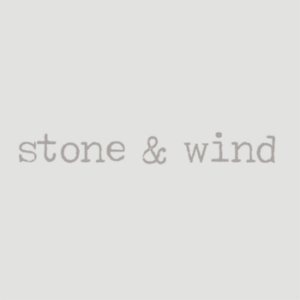知音とは深く心の通じる友を言う。
半世紀ぶりに友のギターと歌を聞いた。
少し声が低くなっていて、息の吸い方に特徴のあるいい声に深みが出て、ギターも膨らみのある時を刻んだ音がした。
四十年以上前と、十年前に、会って以来連絡はつくという状態のまま、時が流れた。けれど、例えば、読み直すことはなくとも長い間、文箱の底にずっと大切に寝かせている手紙のような存在であったと思う。
あの頃、福岡にはまだ市電が走っていて私たちが出会ったのもその中だった。降りる駅が同じで会釈を交わすようになっていったのだが、彼の私の第一印象は「まだこんな人がいるのか」だったらしい。長い髪に下駄ばきで、画材屋で買った絵の具入れの袋を肩に本を読んでいた。確かその頃は吉川英治の『三国志』あの厚い本を亡父の本棚から抜いて読んでいたように思う。私はその頃、甘えでしかないのだが、何もかも諦めた気持ちになっていて不愛想に暮らしていた。もし、人生に消しゴムがあってやりなおせるのなら、あの数年を消したいと思う。
そんな中で、彼がいた場所だけが明るかったような気がする。
はじめは、ろくに顔も見ずに会釈をしていたのだが、少し言葉を交わすようになってまじまじと見て驚いた。爽やかな美少年であった。随分年下にみえた。笑うと口角が上がり、コカ・コーラのコマーシャルに出てきそうだとおもった。
彼に会わねばボブ・ディランもウディ・ガスリーも、ライ・クーダーもあのどっしりと染み込む初期のブルースも労働歌も、山之口獏の詩も知らなかっただろう。
その頃の私は北欧のジャズと浅川マキばかり聞いていた。
面白いのは、話していると、ふとこちらの思考を止めるようなことが度々あったことだ。それは、遮るというのではなく、私が全く違う文法の言葉を聞いているような気になったからである。具体的なことは忘れてしまったが、同じことでも私と発想や切り口が全く違っていた。私が主語から、順次考え述語に至るのに対して、いきなりポンと述語を持ってくるような、一本の竹を眺める私に対してさっと斜めに切ってみせるような。
それでいて、重々しさを嫌い難しい言い回しを忌み、早春の風のようにふうわりとしていた。
そして、少し皮肉屋でもあった。
何十年もの時が過ぎ、毎年頂くある組織の年賀状に彼の名が代表者のひとりとして連なっていた。驚くと共にあの発想が組織の助けになることも多々あったのではないかと、おもった。
その彼とライブ会場でばったりあった。持ってきてくれたビールで乾杯し、少し話した。いい風が吹いていくような、短い中にも時が静かに満ちてくるような会話だった。
そのあと、このライブは彼が所属していた組織の集まりも兼ねていたので、彼はステージ近くに移動して、多くの人と握手を交わしていた。近づく人々が自然に湧き出るような笑顔で彼も其れに応え柔らかな笑顔であった。「いい人生だな」と私は思った。仕事もプライベートもそう一筋縄ではいかぬこともあったろう、多くの苦しみもあったかもしれない。しかしこの笑顔の広がりを見る限り彼がどんなに信用されていたかわかるような気がした。
気が付くと頬が濡れていた。ずっと繋がっていたわけではない、何か特別なことが起こったわけでもない、しかし、苦しくもあり、中途半端な何者でもないある時期に何か大切なものを共有していたという思いが、私にはある。そっと心の底にあり続けたその友が信頼された、いい笑顔に囲まれている、と、いうことが、こんなにも嬉しいことなのだと、友の幸せそうな笑顔がこんなにも嬉しいものなのだと、私は初めて知ったのである。
それから、又時が経ち彼が参加している会に出るという知らせを受け取って半世紀ぶりの歌を聴いたのだった。
曲は先輩が作ったという、聞き覚えのある、哀しみの中に、若い尖りもあり心に沁みるブルースらしい曲だった。
作者は、随分とクラブ活動で鍛え上げられた鬼先輩で、一方、音楽への道に誘った人でもあり、ある時不意に姿を消して長いこと行方も分からないのだという。
「今日ここで話して唄ったら、ふっと、会える気がして」そう言って歌いはじめたのだった。
私は、先輩が「その人」であることがすぐにわかった。
その人は友と私が話を深めるきっかけになった人でもあったのだ。
親不孝通り、今では親富孝と書くのか、という名前がつく前で私たちは万町(よろずまち)と呼んでいたが、まだちらほらと店があるくらいの静かな通りに男前の髭の主人と津軽出身の女将が店を開いた。色々な職業の人や職業の無い人や芸術家や芸術家崩れなどなどが集まって、その頃は主人たちの誠実さが伝わるような店だった。私も隅で焼酎を飲んでいた。
その時は店に数人残っていて、もう閉める頃だった。外にいた主人が一人の男を連れて入ってきた。
「この人、旅をしていて帰る金に困ったらしい。みんなカンパしてやってくれんね」
男は深く頭を下げ、ケースからバイオリンを取り出し弾き始めた。
思いがけぬ澄んだ音色で、聞き覚えのある曲を数曲奏でた後、静かな沁みいるような「音」だけが流れるような曲を弾き始めた。すると客の一人が、やはりケースからフラットマンドリンを取り出して、低く音を調節し共に弾きだした。
二つの音は重なり、時に語るように、秋の初めの微かな冷気の中に流れ出した。
私たちはしばらくその音の中に居た。
ひと月ほどして、店の丸太のカウンターに座ると、主人がすり鉢に梨を盛って出した。
顔をみると、ちょっと微笑んで「あの、バイオリンの人から」と言った。
鳥取の人だった。
何故そうなったかは記憶にないのだが、この話を、友にすると「その話、知っています」と言った。「そのマンドリンの人、僕の先輩です」それから、しばらく私たちは黙っていた。私の耳にはあの音がよみがえっていた。友が何を思っていたかはわからない。しかし、この時から、私たちは様々なことを話すようになった気がする。
あの初秋の冷気に流れた音のように、時は流れ半世紀たったのだ。
友とは又出会うこともあるだろう。その時私たちはおそらく目を合わせ、「やあ」と言って盃を上げすれ違うだろう。そこには、おそらく、一瞬、あの早春の風が吹くに違いない。