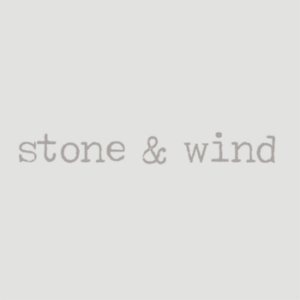東京に住み始めたのは昭和54年だった。
最初に驚いたのは人の顔の種類の多さで、新宿や渋谷の山手線の列車から掃き出されるように降りてくる人たちを見ながら「日本人ってこんなに色々な顔があったのか」と思った。
それでいて、私はどこに行っても「九州でしょ?」と言われるのだった。
眉の濃い眼の大きいエラの張った顔は、どうやら西郷隆盛を連想させるらしかった。
今、山手の駅に立っても顔の違いは感じない。日本人の顔が変わったのか、私が慣れたのかはわからない。
初めてのアパートは中目黒だった。
今のようにレストランやカフェなどが並ぶしゃれた町ではなく、その中でも私たちが住んだのは、ちょうどすり鉢の底のような一帯で、目黒川が細くなったすぐ横の豆腐屋や酒屋や小さな工場に囲まれた木造の二階建てのアパートで、新築だった。
小さなベランダの横は手の届きそうに近い木造で、斜めに大きな棒で支えられていた。外階段から見えるとなりの家は、二階の窓が変に大きく、足をまたぐとすぐに屋根というぐあいで、朝夕家族が座っては、団扇太鼓を叩いて、お題目を唱えていた。
「ナンミョウホウレンゲエキョウ、ドンドン、ナンミョウホウレンゲエキョウ、ドンドン」団扇太鼓というのは、芝居や落語で知ってはいたが、実際に見たのは初めてだった。
ここの親父からはずいぶん怒鳴られた。
その頃、プルトップが付いた丸い小瓶のビールを飲んでいて、夜、外のごみ箱に入れるときに用心してもカシャンと音がする。音がするや否や団扇太鼓が「この野郎!何時だとおもってやがんだ。毎日じゃねえか!バカヤロー」と言ってガシャンと窓を閉めるのである。
私も朝に出せばよいものを、すべてのゴミを出してからでないと落ち着かない癇症なところがあって止めない。ついには、階段の足音ひとつにもガラッ、バカヤローがつくようになった。
ところが、ある日突然に、この親父と仲良くなったのである。
その頃、どこからか白黒のはちわれ猫がやってきてアパートの付近で日向ぼっこをしていた。良く慣れた大人になる少し前の、黒いところは真黒く光り白いところは混じりけなく真っ白な、アイラインが入ったような眼をした美しい雄猫で、近所の子供たちが触るとコロンコロンと身を転がして遊んでいた。
私たちはこの猫に夢中になった。痩せてはいないので飼い猫かとも思ったが、首輪もしておらず、時々餌を与えたり、ミルクを飲ませたり、あそんだりしているうちに、家の前で帰りを待つようになった。それが嬉しくて紐やらボールやらで遊んだ。夜初めて家に入れた時は夜中になって急に部屋を走り、不安なのかと思ったらトイレをさがしていたのだった。植木鉢に乗って用を足した。
トイレも用意せずに家に入れてしまい申し訳ない事をした。
朝出かけるときに外に出すと、ぴょんと手すりから何妙法蓮華経の屋根に飛び移った。
「おお、くろ、どこに行ってやがった。心配したぞぉ」と親父が言った。
まずい、と私は思った。これは正直に謝るしかない。
私は、あまりに可愛くどうしても一緒に居たくて泊めたこと、トイレも用意していなかったのに、粗相せずちゃんと植木鉢にしたこと。食べさせたものなどを話した。
何故か、愛おしくて涙が出てきた。
「世話になったな」と返事があった。
驚いて顔を上げると、「よく人になついてんだろう? 飼い猫だったと思うよ。迷ったか、置いて行かれたか。この頃、マンションってのに住み替えるやつが置いてくのが増えてさ。そんなのが、三匹俺んちにいるよ。こいつで四匹目だ。」
「良かったら、飼ってやってくれよ。」但し、と声を強めて「二度と悲しい思いさせるなよ」
こうして、バカヤローは、ヨオーに変わった。
親父の家の前の細い路地を抜けると角に、ドアに嵌め込んだ小さな波ガラスに美容室と金字で書かれた民家があった。白衣のウエストをキュッと締めた粋なお婆さんが一人でやっていて、髪を結うのが滅法手早くうまかった。
「若い頃は芸者衆の髪を結っていたんだ。引退して娘と暮らしてたんだけど、折り合いが悪くてね。」と話してくれて、ふっと笑った。
そこを左に曲がると、豆腐屋があって、朝早くから湯気がでていた。
朝、小さいボールを持って買いに行くと、大豆の香りが残った湯気のなかにある。
「何にすんの」豆腐屋が聞く。朝のお味噌汁です、と答えると絹ごしの三分の一をトントンッと賽の目に切ってボールに入れ、残りを包んでくれた。「夏の味噌汁は絹の方が旨いし、入れすぎると野暮だからさ。あとは、よく冷やして夜に奴にでもな」
豆腐屋からの帰り道、太田屋という酒屋があって、細面の面高な顔の店主がこれも朝早くから箒を使い水を打っていた。
頼むと、ビールなどをケースでかしゃん、かしゃんと届けてくれた。
家で飲むワインといえば、その頃はまだドイツワインのマドンナやポルトガルのマテウスくらいで、今とは全く違っていた。我が家では、質より量というわけではないけれど、一升瓶に入った甲州ワインをよく呑んだ。
店に入ると知らない日本酒が並んでいてラベルを見るだけでも楽しかった。ずらりと並ぶ酒は私たちには手の出ないものが多かった。楽しそうに見ていたからか、店主が「ちょっと味見してみるかい」と言って小さなグラスについでくれた。
冷(ひや)酒で、「少し甘味が残るのに後味が良くって米の酒らしくておいしいです」というと、そうかい、と言ってもう一杯くれた。冷酒で、きりっと心地よい鼻通りの良い酒だった。そうかい、と又言って「鶴亀」と「禅」だと教えてくれた。それから時々「良いのが入ったよ。味見してくかい」と言って一口飲ませてくれた。
二十歳半ばに届くかどうかの小娘である。立ち飲みのカウンターで何の疑問もなく、キュッと一口飲ませてもらってどんな酒かも教えてもらう。今思うと恥ずかしいような、けれど幸せな気持ちがする。
東京は、秋のなり方が違った。
急にすうっと風が立ち、すとんと秋になる。
これも、今は気候が変わってしまい年寄り噺になってしまった。
そんなふうに秋がくると煮物が似合う。落とし蓋を開けて煮物の香りが立ち、柚子を散らして香が重なると時々入る微かな冷気にふれて何とも落ち着くのだった。
そんなある日、ベランダの窓の向こうにバチバチという音がした。
「火事だったりして」と冗談軽口をたたきながら包丁を置いて窓を開けると、ほんの少し離れた屋根に、本当に赤い炎が揺れていた。
裏のつっかえ棒の家のあたり火事になったら一発だねと、話していたが、その一発であった。
バチバチという音が大きくなっていく。風は家とは逆だったが、炎の先は時折こちらを向く。「消防車!」と急いで受話器を取る。もう消防車は向かっているらしい。
ドアが開いて、太田屋の店主が入って来た。
「着物、着てたろう。他にも大事なもんあれば預かるから、持ってきな。通帳とか、自分で持ったらすぐに外に出な!」
指さすとタンスの引き出しを重ねて運び出してくれた。
外に出たとたん「しろくろ!」と口に出て初めてうろたえた。時々あの屋根で日向ぼっこをしていた。しろくろ、しろくろ、とあたりを見回すと、団扇太鼓の家の方から丸いものが飛んでくるように見え私の胸に飛びついた。無事だった。
「だいじょうぶだぞ!」と親父が叫んだ。
しろくろを抱きかかえて、ほっとして、何か変な気がして左手を見るときゅうりを持っていた。わりと落ち着いているつもりだったが、ずっときゅうりを持ったままだったのだ。
結局、私たちの部屋からホースを入れて火は消し止められた。
大家の、小山のお婆ちゃんが近火見舞いを持ってきてくれた。
まさか、大家さんからお見舞いを頂くとは思わず随分と恐縮した。
その大家さんは、背の低い、背中が少し曲がった小さなお婆さんで白髪をちょこんとまとめて、紺色の丈の長い、よく酒屋で見るような前掛けをいつもしていた。
なんでもこの辺り一帯は小山さんの土地だったらしいが戦後少しずつ手放して今は広い家とご主人が亡くなった後に建てたこのアパートだけになった。
ある日、アルバイトで着物を着て出かけるところを、ばったりと出くわした。
「よく着れてるよ」と言ってもらい、私は襟つけがうまくいかなくてと、応えた。
「教えたげるから、いらっしゃい」という言葉に甘えて、数日後、襦袢と襟を持って伺った。
小山さんは、襦袢の襟のところを膝に乗せ片方を正座した脚の下にはさんできりっと引いた。それから、時代劇に出てくるような背の高い針山から針をつまみ、チョンと針を入れてスウーと引いて少し離してチョン、スウーを繰り返した。その間襦袢の襟もとはピンと張ったままだった。
「襟は替えるもんだから、大きく縫っていいんだよ。つまむとこだけ気をつけて」と言いながらリズムは変わることなく、その幅も変わらず縫っていった。
見惚れていているうちに、一瞬、小山さんの指を凝視した。
右手の小指が無かった。
縫い終わって、私が襦袢を畳む間にお茶を入れてきてくれて、よいしょと言って座卓のまえに座った。
「これ、かい」と無い指をみせて「犬に喰わせてしまったんだよ」と言った。
私は何かの例えか、とも思ったが返事の仕様が分からなかった。
「そりゃ、冗談だけど、昔ドーベルマンを飼っていてね。おとなしい子だったが在る時セールスの人に吠えかかって、その人が振り払う仕草をした途端に飛び掛かろうとしてね。
私はとっさに横から犬の口に手を出したんだよ。あの子は勢いで私の小指を噛み切ってしまった。後から指を探したけど見つからない。
結局、呑み込んでしまったんだろうということにね。」
小山さんは、痛みや治療の話は何もしなかった。
ドーベルマンは、ちゃんといい子で長生きをしたそうである。
アパートの名前は「セブンツウ 小山」だった。
夫を亡くした小山のお婆ちゃんが72歳で一念発起して建てたアパートだった。
薄い黄色の壁色で、屋根に少しだけ青い丸い瓦が葺いてあった。
あのすり鉢の底の愉快な日々から、50年近くも経ったのだ。
「セブンツウ コヤマ」
未だにチョンスウー、キリリと襟を替えられない私は呟いてみる。
今年でわたしも、72歳に、なった。
関連ジャンルの書籍