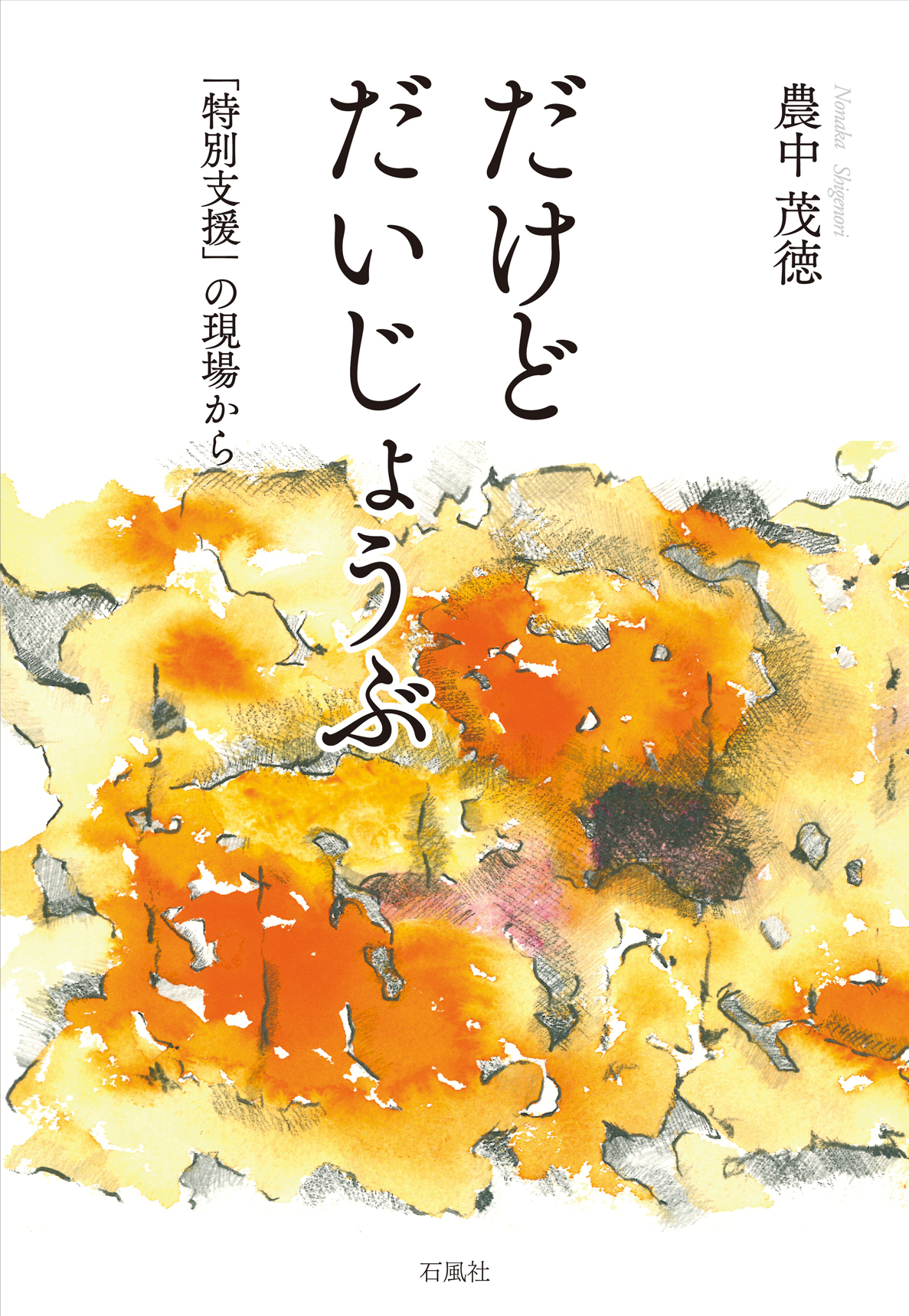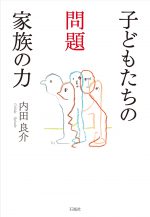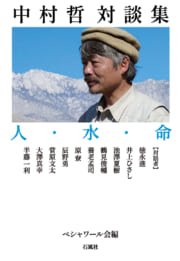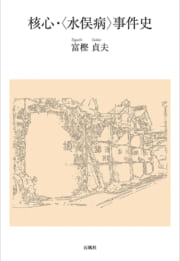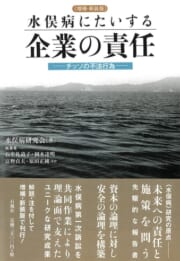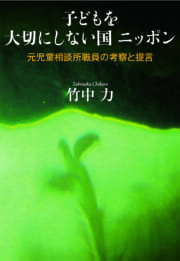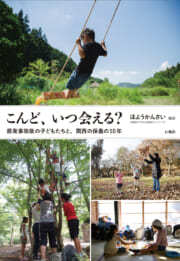ネット書店で注文
だけど だいじょうぶ
「特別支援」の現場から
- 著者:
- 農中茂徳
| 判型・頁 | 四六判上製240頁 |
|---|---|
| ISBN | 978-4-88344-281-2 |
| 定価 | 1980円(本体1800円) |
| 発行日 | 2018/06/21 |
三池の炭鉱社宅で育った少年が
「特別支援」学校の教員になった
「障害」のある子どもたちと
くんずほぐれつ心を通わせていった
一教員の実践と思考の軌跡――
「我在り ゆえに我思う」
学校には、家族の愛情をいっぱい受けながら通っている子もいるが、やって来る子どもたちの多くは、さまざまに苦しい事情をかかえている。
「できない、できない」と言われ続けた子がいる。「みんなのじゃまだ」と言われた子がいる。汚い言葉をくり返しあびせられてきた子がいる。親から見放され、おとなへの信頼をなくした子がいる。それまでの自分ではなくなり、自分の存在価値を見失った子がいる。
そばにいた私は、「だけど」という言葉を浮上させ、心のなかで声をかけていた。
「だけど、だいじょうぶ。人生は今だけじゃないから。ぼくが生きてきたように、十年後、二〇年後を生きてみようよ」と。(「まえがき」より)
Ⅰ 手話は禁止されていた
学校間交流/スピーチ/駆け落ち/視線/道をつくるように
Ⅱ 人間ですからね
すてきなプレゼント/百々(もも)のリハビリ/えりごのみ/趣味は仕事と魚釣り/バリアフリー
Ⅲ ふたたびの聾学校
タクシーで山登り/生きていく力/なぜ、学校に来ないのか/ウナギのかば焼き教室/こわい魚/「子わかれ」からの性教育/授業へ
Ⅳ 先生、元気ですか
旬を楽しむ/十年後はおとな/罰を受ける/ぼくの名前も変わりました/演技の練習には怖さも潜む/おかあさん!/種を粉にひくな
Ⅴ 二十年後を生きていく
チテキショウガイ/学童保育と学籍/地域懇談会/言葉の力で進む/「地域所属」/蛭子丸/もう一つの神話を
1946年生まれ。大牟田南高等学校卒業。東京学芸大学を卒業したのちに福岡県内の聾学校および養護学校に勤務。現在は福岡県立大学非常勤講師(人権教育)、福岡県人権・同和教育研究協議会会員。