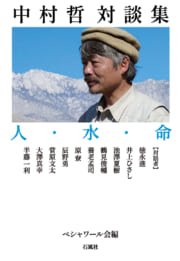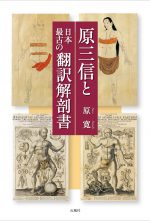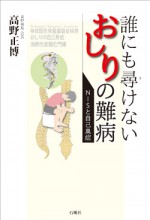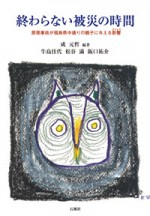進行した認知症者では、本人が自覚することなく脳内の変化がまとまりのないまま(ありのまま)、表情、態度、言葉と行動として表出される。しかし、外界に対する知覚は鈍っており、反応性は弱く不規則なため、精神的には不安定になりがちでもある。このように人の脳内変化は気象にも似ており、季節、地域における特徴や変動があり、人の個性や反応特性など比較的変わりにくい季節のような面と刻々と変化する日々の天候(天気)にも例えることが出来る。私の診療は日和見診療(私の世代では、日和見主義にはネガティブな記憶もあるが)であり、天気を観るように認知者の気持ち(脳内の事象が、知覚、反応、知識、思考により外界とつながり、相互作用によって生成される)を眺めている。それは(削除)入院中の認知症者に対しては、朝、昼、夕の面会により、その様子や反応を天気のように観察して、その気持ちを測る。朝の面接では、窓のカーテンを開け、挨拶と呼名により靄の中の個人を呼びさまし、その時だけでも本人の本人としての自覚(アイデンティティー)と人とのつながりを意識してもらうためである。人のアイデンティティーや言語は“そこに生まれたから”に始まり、また、人の実存の芯にもなっており、私はコミュニケーションやなじみの関係を形成する便法として、医師・患者関係の緊張を緩めるため、認知症者の属性である方言、地域、歴史、文化などを活かしたローカルなご当地診療も許してもらっている。
この姿勢は水俣病被害者やペシャワール民衆のために生涯を捧げた原田正純医師や中村哲医師二人が語っていた“そこに居合わせたから”という言葉も拠りどころにしている。最近、「local for local」という言葉も聞くが、「global」という価値観に対するアンチテーゼとなるか分らない。
私の病棟での仕事は、毎朝の回診から始まる。病室を訪れるか病棟のホール(集いの場)で認知症者と対面して、起床の有無、覚醒度、室内での様子と過ごし方を観察しながら、挨拶や呼名「名前を呼ぶ」によって、その日の始まりと共に、本人の自覚、人とのつながり、その日のモチベーションを喚起するようにしている。また、外来診療の合間、昼食や夕食の時間帯にも、病棟で入院者と対面して朝の回診と同じように本人と交流しながら、記憶が困難で自己表現の苦手な認知症者の状態や日内変動を知る機会にすると共に、私自身が集団の一員として受け入れられるようにしている。意識や記憶に頼れない認知症者は無意識のままに語り、行動することが多く、私も認知症者の無意識に語りかけている。認知症者の気持ちは無意識のままに記憶の断片や作話として表出され、認知症者の間で交わされる仮性対話もコミュニケーションの大事な手段になっている。
私の経験と視点
ここで、自己紹介に代えて精神科医になってからの経験と視点を語らせてもらうが、読者の中には聞きなれない言葉や内容も含まれるので私のモノローグとして読み飛ばされて構わないものである。
私は1973年熊本大学医学部を卒業して神経精神科の医局に入り精神疾患の人々に出会ったが、当時の神経精神科医局での主な研究テーマは精神分裂病(現、統合失調症)に対する生物学的研究が進められていた。認知症も器質的精神障害として治療と研究の対象であった。当時、病棟には梅毒による進行麻痺や脊髄癆(せきずいろう)、ヒロポン(メタンフェタミン)中毒後遺症、三池鉱炭じん爆発事故による脳局在症状(その後、高次脳機能障害)を呈する一酸化炭素中毒後遺症、角膜に青い銅の沈着したウイルソン(Wilson)病の青年なども入院していた。また、入局した年の11月19日、熊本市では老舗の大洋デパート火災が発生して104名が亡くなり、その時も一酸化炭素中毒や低酸素脳症の患者が多発して、その頃から高圧酸素療法が普及した。中学生時代、私の祖母は火鉢を抱え込むようにして意識を失くして亡くなったので、後になって一酸化炭素中毒であったろうと思い起した。
当時の医局は、立津政順教授時代であり、立津教授の徹底的な観察と詳細な記述を追求する態度は私の診療における座右の銘にもなっている。後年、モンテフィオーレ病院の平野朝雄教授から立津先生の「黒核障害の精神症状と病理」についての署名入りの論文をもらった。その論文は発表当時認められなかったが、1964年には黒質(黒核と同義)で産生されるドーパミンの前頭葉への投射路が判明したので、立津先生の指摘は的外れではなかったと思った。リモート診療が一般化してきた現在でも、速やかに記憶を失くすような認知症者に対するメンタルケアの実践には、立津先生の姿勢は有用であると思っている。立津教授の後任である宮川太平教授は、神経病理、特に、電子顕微鏡の達人であり、神経原線維変化とアミロイド線維の電子顕微鏡写真は卓越していた。また、原田正純先生(後に熊本学園大学社会福祉学部教授)による、てんかんや睡眠の研究のため脳波検査が行われており、先生に脳波の判読を教えてもらった。当時から水俣病の研究は教室を挙げて取り組んでおり定期的に地元での検診に同行した。後に、先生のベトナムでの枯葉剤汚染調査に参加して、ツーズー病院で「ベトちゃん・ドクちゃん」にも対面する機会もあった。原田先生は胎児性水俣病の発見のみならず水俣病被害者の支援に生涯を捧げた。
京都大学老年科で神経学について学ぶ
その後、1977年から京都大学老年科(その後、老年科と神経内科に分化)の亀山正邦教授の元で神経学について学び、症候学に基づく神経診断学に触れた。客観性に乏しい精神科診断と違い、筋委縮性側索硬化症、多発性硬化症、サルコイドーシス、ベーチェット病など身体症状と検査所見からの診断は新鮮であった。教授室の壁の一面には最新の文献が分類されて置かれており、教授回診や医局カンファレンスで紹介される知識の豊富さと整理の精緻さに感心した。なお、当時CT(Computerized Tomography)が臨床に導入された頃であり、亀山先生の鑑別診断にニューマン(Neuman)の皮質下グリオーシスという疾患もあった。その脳の白質の病理については、今では前頭側頭葉変性症に分類されている三山病の経験を介して、発見者である三山吉夫先生(宮崎医科大学精神科名誉教授)に教えを受けたこと、菊池病院時代に保存されていた唯一の脳が「第17番染色体連鎖前頭側頭型痴呆・パーキンソニズム」という新しい疾患だったことなど、現在の代表的な認知症になったタウオパチーに私の経験では繋がっている。なお、当時、脳内モルヒネ(エンドルフィン)が発見された時期でもあり、京都大学医学部では井村裕夫内科学教授により精力的に研究が進められていた。その検出を可能にしたのはノーベル生理学・医学賞者のR・S・ヤロウ教授が開発したRIA(放射能免疫測定法)であったと知ったのは、女史がモンテフィオーレ病院に私と同じ時期に在籍していたからだった。後に、認知症者に対するメンタルケアの効果に対しても科学的根拠が要求される時代となり、エンドルフィンによる評価ができないかと考えたが設備や技術のなさで断念した。
モンテフィオーレ病院に留学
1982年、神経病理を学ぶためニューヨーク市ブロンクス区にあるモンテフィオーレ病院神経病理部門に留学した。動機は世界的な神経病理学者である平野朝雄教授の日本での講演を聴いた時、星状グリア(膠細胞)の突起の先端が布の様に広がって脳内を満たしている電子顕微鏡の像を見たからである。これは粘菌が木の根に絡みついて共生しているだけでなく粘菌自身が神経ネットワークのような構造と機能を持つと言われていたことも連想させた。この病院はアインシュタイン医科大学の関連病院であり、神経病理部門のH.M.ジンメルマン名誉教授はアインシュタインの脳を剖検した人でもあった。当時、ニューヨーク市の治安の悪さはThe Bronxという映画でも紹介されていたが滞在中危険を感じたことはなかった。また、同市はAIDS(後天性免疫不全症候群)の世界的な発生地となり、同性愛者の性感染症として恐れられるだけでなく偏見や差別も浮き彫りにした。脳内病理では、トキソプラズマやクリプトコッカスなどの真菌感染と共AIDS脳症が注目されており、忘れられつつあった進行麻痺を思い出した。クリプトコッカス膿瘍は中学生時代の親友が意識障害の状態で大学病院に入院して亡くなっており、私も一緒に伝書鳩を飼っていたのが気になっていた。なお、私が熊本から来ていると知った同病院のAIDS研究者から有毛細胞白血病(hairy cell leukemia)について尋ねられた。それは九州出身者に多く、熊本大学内科学の日沼頼夫教授が発見した成人T細胞白血病も念頭にしたものと思われ、直後の1984年に確認されたAIDSの原因であるHIV(Human Immunodeficiency Virus:HIV)にも繋がることが判明した。その時、米国における情報収集の正確さと素早さに感嘆したが、今日のビッグデータ分析や生成AIとの連続性にも思い当たる。日沼教授のウイルス学は疾病論だけでなく、疫学的手法から民族学まで広がったことに感心したが、最近、ヒトの遺伝子解析から日本人が縄文人の遺伝子を多く引き継いでいる特異な存在ではないかとも推理されるなど学問や科学の進歩に感嘆すると共に、文化人類学や民俗学などの観点から認知症をどのように受け止められるかということにも興味がある。
モンテフィオーレ病院では世界的な神経病理学者である平野朝雄教授の膨大な症例についての内容や年代の正確な記憶には驚かされ、電子顕微鏡の像が色彩のある光学顕微鏡の像と異なり、主観性の少ない白黒ながら分子の観察も可能であることも新鮮な認識であった。
国立肥前療養所に勤務
帰国後、代々続いてきた内科医院を閉院して、1990年、臨床研究部に神経病理部のある国立肥前療養所(2000年4月から独立行政法人国立病院機構・肥前精神医療センター、「以下、肥前療養所」)に勤務することになった。そこには将来を嘱望されていた佐藤雄二先生(初代ペシャワール会事務局長)がいて、その恩師である九州大学脳神経病理部門の立石潤教授の指導も受けることが出来た。そこでは、クロイツフェルド・ヤコブ病の先端的研究が行われており、間もなく異常なプリオン蛋白が発症の原因だということが判明した。それから35年後、プリオン病と代表的認知症であるレビー小体病の病理的進展の類似性が指摘されている。
臨床経験としては、赴任後に発見された吉野ヶ里遺跡のある佐賀県神埼郡東脊振村(当時)にあった肥前療養所は、精神医療の西の雄とも呼ばれており、私が直接経験していなかった多様な分野の精神医療が展開されていた。内村英幸所長は神経科学の研究を専門としながら森田療法にも造詣が深く、個性的な医師たちと共に新しい精神医療と社会的使命を推進していた。そこには日本の行動療法のパイオニアである山上敏子先生や社会精神医療分野の活動家である村上優先生(現国立病院機構さいがた医療センター、現ペシャワール会会長)など多士済々の顔ぶれが揃っていた。
なお、神田橋條治先生の後継者とされていた精神療法家の松尾正先生による統合失調症者と治療者の意思疎通の瞬間のフッサール的解釈は、後日、菊池病院で認知症者へのメンタルケアを始めた頃、認知症者との接触でも同様の瞬間があることを経験することになり、認知症者の間主観性について、木村敏京都大学精神科名誉教授に尋ねてみたこともある。また、当時は、国内外でも精神医療に対する反省と改革が求められており、患者自身の人権回復や当事者主導などの萌芽があり、患者を標的にしない家族療法も広く普及していた。反精神医学というものもその時期に一時的に出現した。
基礎医学分野では、後に、ノーベル生理学医学賞を受賞する山中伸也教授によるiPS細胞発見にも繋がる、動物のキメラやハイブリッド研究ついて岡田節人京都大学名誉教授の講演で聴いた「人が創造するものは神に許されているのか」という言葉が気になっていたが、iPS細胞や生成AIによる結果を人が創造したものとして倫理的に許容されるのかという最近の命題と重なるところもある。
自分史の回想
次に、私の志向を探るために精神科医になるまでの自分史の回想を語ることにするが、人の記憶自体、脳内の意識野の中で、消去されたり、加減されたり、歪められたり、断片化しながら個人的な記憶となっており、私が精神科医になった動機は意識下の深層心理にあるかもしれない。
幼児体験として想起するものには自宅の庭から広がった環境への出会いがある。その頃は、ヤギがいた自宅の庭の奥が、ラジオから流れていた童謡「緑の丘の赤い屋根」で始まる「とんがり帽子の時計台」の世界だと思っていた。保育園に通うようになると新たな環境との出会いに驚きの日々だった。通園する途中、畑の中に小径があり、自分の背丈よりも高い花に出会って感動したが、後になって、それが撫子(かわらナデシコ)だと知り、想い出の花となっている。また、ガリバー体験のように風に揺れる青い麦畑を緑の海原と思ったのか、その中を歩き回り、麦の穂で顔や服を黒く汚したことも憶えている。水がぬるむ田植えの前、水を引いた田んぼに入り込んで泳いでいるのを自宅に通報されたこともあった。また、自宅と保育園の中間ぐらいの所に水路にかかる細い木の橋があり、川の流れをのぞき込み、水面に映る自分が動き出すのを不思議に感じたイソップ童話の体験も記憶に残っている。子供時代誰しもそうであるように、現実と空想の世界に境界はなく、他者と自分を比べることもなく、自分が見たものがすべての世界だったのではないかと思う。進行した認知症者の「well being」もそのようなものかもしれない。
少年期は、代々の医家であったので生活と医療が共存していた、居間の二階にあった鉄格子の小窓のある暗い謎の部屋が、ずっとのちになって精神障害者や梅毒患者のための座敷牢だったのではないかと思い至った。また、倉庫には、曾祖父あたりが醜形の残った梅毒患者の鼻の形成をしていたという古い医療器材と動物の骨の入った箱があった。また、近づきがたい雰囲気のカーテンのかかった暗い病室で痙攣していたのは当時の農村では珍しくなかった破傷風患者だったと医学生になって知った。1958年(昭和28年)6月26日に熊本を襲った大水害では、2016年(平成28年)5月16日未明の熊本大震災の10倍もの犠牲者が出て、父は、泥土に埋まった遺体の検視に出向き、裏の山では木の枝に下がった自殺者も見つかった。
なお、少年期には死の恐怖(タナトフォビア)に脅かされ、自分が無に帰することの恐怖感に襲われていたが、その恐怖心は歳をとるにつれ徐々に薄れ、いつの頃からか、真偽は不明ながら良寛の死に対する言葉とされる「死にとうない」、「散る桜、残る桜も散る桜」という心境で良いと思うようになった。
高校生時代は、当時、受験戦争と呼ばれていたが、現実的には、専門用語で、離人症(depersonalization)や離現実症(derealization)という感覚のためか、ただの流行として生きていたような気がしている。これは死の恐怖体験と共に人の成長に伴う通過症候群とも見なされ、この時期には、「若きヴェルテルの悩み」を読んではハイデルベルク大学に憧れたり、文芸春秋で発表された同時代を意識した芥川賞作家である柴田翔の「されど我らが日々」や五木寛之の「青年は荒野を目指す」に共感した記憶がある。なお、振り返ると同時期の芥川賞作家である、丸谷才一の「年の残り」、大庭みな子の「三匹の蟹」が時代を先取りした内容であったことに今になって作家達の先見性には感嘆している。当時は聴くこともなかった吉田拓郎の「今日まで、そして明日から」もその類かもしれない
1966年大学に入学して当時は2年間の教養課程があったが、全国に広がった学生運動のために大学は休講となり、社会性のなかった私だが学生の集会やデモの喧騒に新しい息吹の心地よさと意気を感じていた。同時期に流行していた実存主義作家、J.P.サルトル、A.カミュ、F.カフカ、阿部公房などの本を好み、アングラ文化と呼ばれた、寺山修二の作品、唐十郎の「赤テント」や佐藤信の「黒テント」劇団、浅川マキの「夜が明けたら」や長谷川きよしの「黒の舟歌」などの唄が身近にあった。個人的には不幸を感じることなく、教科書で習ったことのある、カール・ブッセ(上田敏訳)の「山のあなた」における「幸」を「自由」にすり替えて、カオスの状況を自由と勘違いしていたふしもあるが、未だに世界では「カオスと自由」は「戦争と平和」と並び両価性の対語となっている。
大学の授業が再開すると、対立がなかったかのように大学側と学生側のわだかまりは忘れられ、大人に立ち向かった子供のような模擬的関係を感じた。論理的に学生運動に参加した友人の数名は社会の要職に就いたが、心情的に影響を受けた友人の何名かは退学したり、行方不明になったり、自害して亡くなった。私も、女学生だった妻に自分の夢を託して、いまだに自責の念が点滅する。その思いはN.ホーソンの「緋文字」へと繋がり、更には、当時、我が家の庭の片隅にあった緋桐という赤い花の咲く木と重なっている。また、当時、流行したフォークソングで、PPM(ピーター・ポール&マリー)の歌「Where have all the flowers gone」にも連なっていた。その木は、ずっと以前に我が家から消えてしまっていたが数年前に園芸店で見つけて細々と復活している。
エピローグ
人類は自然から学び戦いながらも、想像と知性を頼りに地球を開拓して巨大都市を建設し、宇宙を探索し、生命科学は、啓示的なマリアの処女受胎を連想させる、人の再生までしようとしている。認知症の医療でも科学性や客観的・統計学的なエビデンス(根拠)が要求されるようになり、伝統的な診断基準や精神病理学は後退して、操作的診断分類など科学性に叶うようにデザインされ、病態に対しては分子生物学的な解明が進められている。反面、知性の産物には、賢明さを欠けば人類の滅亡や自然界の崩壊を招きかねない負の所産も少なくない。人工知能(AI)による仮想現実(VR)研究者も認知症者の仮想現実を理解しようとせず、今なお、認知症は恐れられ、忌嫌われ、失望されている。しかし、精神医療は科学の領域のみに留まらず、文化、社会、芸術などの分野にも広がっており、人の価値観も多様であり、最近は、当事者のウェルビーング(well-being)も診療や治療の指標にされるようになっており、当事者の実感と統計的なエビデンスが一致することも大切にしなければならない。
認知症者の鏡現象から発想した「デフォルメ鏡」という視点は、人と人の間にある認知症による境界を再考する機会にもなる。人間と鏡の関係は既にエジプト時代に黒曜石や銅などを材料として作られていたことが古代遺跡からの発掘品で知られており、古代から人間が鏡に神秘性や魔性を感じていたことは現代人にも通じるところがあると思われる。また、鏡の起源は水面とも推測されており、水面のゆらぎにも関わらず自分の姿と判っただろうことは水面とデフォルメ鏡の共通性を想起させる。デフォルメ鏡に映るものは脳内の意識野であり、巨匠P.ピカソの「鏡の前の少女」の絵も心理を見つめるデフォルメ鏡ではないかと勝手に連想している。
〈なじみ〉の心理は両価性であり、同調圧力としても人の自由や自立を阻むものとしてネガティブな一面があり、兼好法師の言葉とされる「ひとりこそよかれ」、吉本隆明の言葉である「群れない、一人が一番強い」、百寿(センチュリアン)の堀文子女史による「群れない、慣れない、頼らない」など賢人の至言がある。しかし、多くの認知症者にとってなじみは自分のアイデンティティーを保つささやかな術になっており、なじみの心性は、精神分析学者土井健郎の有名な「甘えの構造」にもある日本人の精神構造にも通じるのかもしれない。認知症が進行すると、発症原因は違っても認知症者に共通してなじみの心理が生じることを知ることが人を理解する一助になると考える。私は、人のなじみという心性を活かしたメンタルケアを実践しながら認知症者の傍らで今を過ごしており、宮沢賢治の「雨にも負けず」のくだりを重ねたりしている。
人生は、あらゆることに対する片想いに似ており、それが、私の、人、科学、美術、社会に対する共通する関係とも言えるのではないかと思うようにもなった。片想いは一面から見れば不幸で道化のようなものかもしれないが、ネガティブな面だけでなく持続的な人の情熱や努力の言動力にもなっていると思われる。精神科医で小説家の箒木蓬生からも紹介された、英詩人ジョン・キーツが提唱した「ネガティブ・ケイパビリティー」にも通じるものを感じる。
40年も前、ある人から人にはそれぞれのエンジンがあり、大型のエンジンの持ち主は大きな仕事があり、小型のエンジンの持ち主は相応の仕事があると聞いたことがある。私は精神という人の謎に興味を持って精神科医になって、ボブ・ディランが唱えた「The answer is blowin’ in the wind」に任せる勇気もなく、エンジンのない帆船で迷走しながら認知症者のいる世界に漂着した。精神科医として50年以上過ごしてきたのは自分探しという片想いの夢だったかもしれないが、認知症者と共に過ごしながら人の不思議を学んできた。私の説は受け容れられなくても、語り部として認知症を往きている人々のための触媒(catalyst)になり、最期に、「c’est la vie(セラヴィ:これが人生)」と言えれば悪くないような気がしている。(ひとまず終わり)