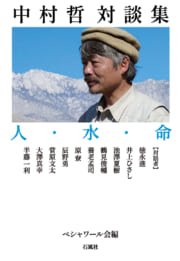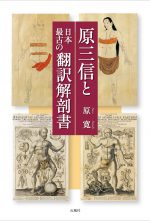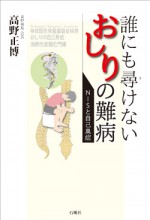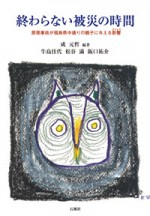熊本地震
熊本地震(震度6から7)は2016年4月14日21時と4月16日深夜1時に発生した。
私の勤務する病院では、4月16日の発災で精神科病棟の損壊のため、入院者65名(担送26名、車いす護送18名、要介助21名)を停電の中人力搬送を行い(電灯の明かりはなくエレベーター停止による)、リハビリ病棟に緊急避難して10日間を過ごした。避難当夜は、恐怖と混乱状態であったにも拘わらず、全員、事故や外傷もなく患者達の動揺も目立たなかった。翌朝には、大半の認知症者は何が起こったのか、どこにいるのかなど分からないままに大勢の中の一人として過ごしていた。リハビリ棟では、臥床状態の人にはマットを敷き詰めたエリア、座って過ごせる人はテーブルと椅子を並べたエリア、点滴や経管栄養の必要な人にはベッドやマットを使用するためにカーテンで仕切った区画などを設定して対応した。
その間、避難集団の安心、安全のためリハビリ棟での対応が困難と判断した5名は他の病院に転院してもらった。また、合併症を治療中の3名は一般病棟に転棟した。
避難10日目には60名が精神科病棟に戻ったが、急性ストレス症状や不測の事態もなく、無事に再適応することができた。混沌の中、一般的に非現実的だと否定されがちな認知症者の言動には、災害と非日常の中でもその時その場の“今”を生きる認知症者の日常である、“仮性適応という症状”も活かされているようであった。
地震のこぼれ話
その男性は、熊本地震で被災した時、避難所に避難せず軽自動車で過ごしたが、自宅に住めるようになっても自宅の庭で車の中に寝具など用意して、食事だけは自宅で摂り、車中泊を続けた。地震前は、不機嫌になりやすく妻との口論が日常だったが、車中泊をするようになってからは喧嘩することもなく平穏な生活になったと本人も家族も認めていた。面接でも車中泊の状況や昔話などを話題として受診を楽しみにしていたが、閉塞性肺疾患の悪化により、1年余りで車中泊は終了した。災害による突然で一方的な行動ではあったが、本人と家族の生活をリセットする効果になったようだ。
新型コロナウイルス流行
2019年末に感染爆発として出現して、瞬く間に世界に蔓延した新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)がわが国にも2020年1月には上陸した。コロナの流行初期には未知の事象であると共に重症者や死亡率の高さから、個人的にも社会的にも感染に対する不安や恐怖心が共通認識としてあった。そのため感染予防に対する規則や対応について感染防止が最優先された。3年後の2023年5月にはコロナが5類感染症に移行して社会的には感染対策が緩和され、コロナに対する認識が個人としても社会的にも多様化している。なお、医療機関によっては、現在も院内感染防止のため3類感染症に準じた行動制限が行われているところも少なくない。
認知症者には口頭や掲示による行動自粛が困難なため行動制限が行われているが、当事者にとっては収容状態であり、安心や安全が犠牲にされることにもなり、感染対策によって精神科に対する医療人の潜在意識もリエゾンとして浮かびあがった面もある。
私の勤務する病院では、2020年初からコロナ診療体制が開始され、熊本県コロナ重点病棟(2021年11月1日開設)のため2021年10月に精神科病棟(38床)が休棟となり、同病棟の入院者40名に転院、施設入所、自宅などへ退院してもらった。
その後、精神科病棟でも2022年6月感染クラスター(陽性者25名)が発生して、4名は精神科コロナ病床を有する精神科病院に転院したが、他の入院者は精神科病棟自体を精神科コロナ専用病棟に臨時転用して対応した。以後、病院全体で単発ならびにクラスター感染が発生しており、精神科病棟では3回のクラスター感染を経験した。その間、3週間以上の行動制限を余儀なくされ、収容化による精神状態への負の影響や安全性の問題に加え、スタッフの心身負担など解決や改善しなければならない課題が明らかとなった。
なお、コロナ感染予防のため、対人距離は1.5m、同室時間は15分と言われていたが、私の診療は、診察室であり、時間も15分以内では終わらないので、常に感染のリスクに曝されることになる。これは、私が認知症者に認知してもらう最小時間にも相当する。
認知症者に残る職業歴
海外航路の船乗りであった人が、頻回のタクシー利用や徘徊のため入院してきた。はじめは、病棟のホールで、ひとり離れて座っていたが、少し馴れてくると洗面台をトイレ代わりに使うようになった。この人は貨物船の船員だったので、東南アジアの国々やその港や街についてはよく語り、いつの間にか、私を社長と呼ぶようになった。そこで、病棟の窓から見える景色をなど、船内であることをイメージして病棟での規則や生活を説明するようにしたところ、近くに居る認知症者の言動にも目配りして、話し相手になったり、時には注意するようになった。誤認による仮性適応ではあるが、自分の立場や役割を得たように、退院という下船を急ぐことはなかった。
パイロットだったこの人は、定年後、田舎での釣りを楽しみに帰郷したが、飲酒が増えて酩酊するようになった。70代になり、高額な品物を注文したり、妻に対する暴言が激しくなった。その後、もの忘れが明らかとなり、「熊本城の石垣は自分が積んだ」と大言壮語するようになった。面接では、紳士的で落ち着いており、飲酒の問題やもの忘れの検査と治療のための入院にも同意した。
入院後数か月、夜間はせん妄(意識が混濁して言動が混乱する)と呼ばれる無意識の言動があったが、本人にはその記憶はなかった。昼間は退屈することもなく平然としていたが会話の内容はほとんどが作話であった。入院3ヶ月過ぎ、夜間、ベッドから転落して、腰椎圧迫骨折のため歩けなくなったが本人はそれを苦にすることはなかった。私との対話で、「釣りには行っている、飛行機も操縦している、晩酌もしている、生活に満足している」と答えるようになった頃から、夜間も良く休めるようになった。妻は、夫が動けなくなって、飲酒のことも昔話になって、やっと一息つけるようになったと語った。
その人はタクシードライバーであったが、70代後半から運転中に道が判らなくなることがあり仕事を辞め、家にいる時間が増えて、動けなくなるまで酩酊するようになった。ある日頭部を打撲して硬膜下血種のための手術も受けた。その後、せん妄が起こったので入院してきた。夜間も「焼酎を持って来い、帰る」と大声で叫び毒づいていたが、退院時は温和になった。但し、酒好きは変わらず、「いつも飲んでいる、飲みに行きましょう」と私に言葉をかけ、実際に飲まなくても安全運転の「エア飲酒」となっていた。
退院後、飲酒することはなかったが、面接ではいつも上機嫌で、「一緒に飲みに行きましょう」と、呑み友達のように私を誘ってくれた。大虎から猫になった大酒飲みとして私の記憶にある。認知症者によっては、入院により酒もたばこもすっかり忘れた人もいる。
自動車運転
高齢ドライバーが社会問題になって久しく、道路交通法の改正により高齢者に対する運転中の規則や免許証更新時の基準が強化され、運転出来なくなる人も増加しているようだが、診療でも、家族から運転断念や免許証返納について相談を受けることがある。
車の運転は、人によっては、車に関する知識、操作技術、走行中の注意、判断、安全確認などの認知機能を作動させる機会になっており、車にまつわる記憶、運転による気分転換、所有によるステイタス感や自身の確認になったりしている。
面接では、本人に、運転する目的や運転の頻度、走行道路、一ヶ月の走行距離、免許証更新時期、運転継続や免許証返納の意思などを尋ねて、認識や記憶の程度、自信度や安全意識を評価しながら自覚を促している。同席する家族には、本人の運転に対する心配や悩みを述べてもらい、家族の意見に対する本人の認識や反応を考慮して、免許証返納の条件に違反回数、違反内容、修理費用などの数字も挙げて、本人と家族の双方が納得できるように努めている。
7年以上通院しているその人は職人で、50年以上も仕事で運転をしており、無事故無違反が自慢であった。家族は本人の運転を危惧して、受診の場でも本人に運転しないように説得するが、当初は、聴く耳はなかった。しかし、本業の注文がほとんどなくなると運転する機会がなくなり、何もせず無気力な日々を過ごすようになった。しかし、仕事や運転はしなくなった今でも、仕事も運転に対する自信は変わりない。
他には、家族が自宅のから車を移動させたところ警察に盗難届を出したり、鍵が見当たらないと何度も合鍵を作ったり、販売店に新車の注文をする人達もいた。なかには、免許証を返納して外出することがなくなり、元気を失くして立ち直る間もなく、コロナに罹患して回復後に自宅での生活が出来なくなった人もある。
なお、受診のため家族が運転することは多く、病院まで時間と体験を共有する適度な機会になり、受診日を、一緒にドライブ、外食、買い物する日にしている家族もいる。
趣味の効用
その人は腰椎の骨折のため入院したところ、夜も寝ないで家族に対する猜疑心も起こり具体的に被害を訴え、入院継続困難となり、私の診療を受けに来た。非難の対象となっている家族は来院できず他の家族が同伴した。
初めての面接で、あらかじめ情報があった趣味や出身高校を尋ねると、長年、造花作りを教えていたことを語り、「先生もお好きですか、今度、作ってきます」と造花の話に夢中になった。また、出身女子高校の話になると、「先生も同じ高校ですか」と一方的に思い込みで安心したのか、校歌をリクエストすると歌ってくれた。入院して数日すると、全てが帳消しになったように家族への不信感は忘れて、家族の自慢話に変わった。趣味の作品が本来の自分をつなぎとめているようだった。
もう一人の女性は、認知症の診断には該当していたが、一人暮らしをして、週3日のパチンコを楽しみにしており、毎回の面接でもパチンコ話を生き生きと語っていた。パチンコ店にはバスを乗り継いで通っており、行きつけのその店では、本人のためにパチンコ台を確保して昼食も取り寄せるなど気を使ってくれていた。ところが大腿骨の骨折のため入院すると、当初は自分の現状を受け入れることが出来ず、自宅での生活とパチンコを切望していたが、徐々に気弱になり、帰宅は叶わぬことと諦めて施設に入所した。本人にとっては、パチンコは勝ち負けよりも、その店に通うことが気持ちの張りになっていたようだ。
この男性は、初めての受診時から赤い帽子を被っていた。その帽子は広島カープのもので、認知症は進んでいたが、彼の育った校区にある小学校が古場監督の母校であったことから長年カープファンだったと野球少年のように話していた。面接のはじめに、毎回、古場監督について同じ話を繰り返して、薄れゆく自分の記憶を繋ぎとめようとしているようでもあった。彼は、「母ちゃん」と呼ぶ妻の言うことを子供のように素直に聴いて、妻が働いている昼間は、聞き分け良くデイケアに通い楽しみ、その性格の良さからその場の人たちに好かれていた。
数年後、認知症が進み、受診の時、赤い帽子ではない野球帽を被って来るようになり、広島カープも古場監督も彼の記憶から消え去っていた。
家業手伝
認知症者には、長い間、携わってきた仕事が生活の一部となっている人が少なくない。
農家であれば見守りながら作業をする家族もある。農家では、草取りが習性となっているが、最近は、握力と寿命には相関があるとも指摘されており、握力を強くする草取りも有用かもしれない。
果樹園で家族と互角に作業するその人は梨の品種も収穫時期も忘れることはなく、毎年の本人の生き甲斐となっている。また、かなり進行した花卉農家である別の人はカスミソウの出荷の手伝いをしており、これまでは検品にも合格している。一方で、雑草と野菜の区別が出来なくなって、毎年ニラと水仙の芽を間違える人もいた。更には、隣の敷地の草取りをして自分の敷地と主張した人もいた。
生涯現役である美容業の人を診療する機会は少なくないが、腕や経営に自信を持っている人が多く、技術以上に長年のなじみの関係が支えとなっているように思われる。仕事をしなくなった後も作話ながら現役のつもりの人は多い。仕事をしている時は、認知症でなくなるひと時にもなる。
謝辞に寄せて
このエッセイの第1章と第2章の一部は2019年2月に石風社から『デフォルメ鏡-もう一つに生き方』として出版してもらった。そして、石風社の福元満治さんと大学時代から朋友であった陶芸家の故山本幸一さんに読んでもらった。山本さんは当時、「虚を注ぐ」というテーマで作品を発表しており、「虚」という共通点もあったので作品展の傍に飾ってもらう話をしていたが、間もなく、病状が悪化して叶うことはなかった。
本エッセイを山本さんと同じく大学時代からの知己である福元さんに一読してもらったが、このままでは一般の読者に理解されにくいということだった。語り部は、自身としては何もできない触媒に似ている。そこで石風社のコラム欄に好意で掲載させてもらうことになり、余計なものだが私の個人史まで曝すことになった。
私と、何人かの知り合いとのつながりは、それぞれの生き方は違っても細々ながらも途切れることなく、半世紀以上に及んでおり、O. Henryの短編小説「after 20years」を読んでからも同じくらいの年月が過ぎた。小説では20年後に再会を誓ったふたりは約束の場に立ったが、一人は警官、もう一人は犯罪者として指名手配されており、たばこに火を灯した相手の顔に気付き、名乗ることなく立ち去った。現実は変化していくが、人の心には変わらないものもあるという内容は、生物学者である福岡伸一の動的平衡という科学的な理論とも通じるものがある。また、老人は、昔を今に生き、若者は、未来に生きるとも謂われており、人の主観的時間では、現実の時間をたやすく超越もする。
私の認知症者に対する診療は10年を一区切りとしてきたので、2025年3月をもってこれまでのような寄り添いの診療は終了した。そして、義を見てせざるはではないが、退役の身ながら文字通りベテランとして、転換期にある熊本の精神医療の中に参加することになった。参加という懐かしい言葉は、「アンガージュマン」というJ.P.サルトルの呼びかけとして学生時代からこころに残っており、否応なしに誰もが人生に参加しているとも言える。
私は、今、七十の手習いとして、陶芸教室で、実際は見ることの難しい日本の絶滅危惧種(主に、シマフクロウ、ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、イシカワガエル、オオサンショウウオなどの小動物)を自分の絶滅危惧説に思いを馳せながら作っている。
最後に、私の片想いのエッセイを読んで戴いた方々に感謝を申し上げると共に、密かに、いつかどこかで皆様との対話(ダイアログ)など夢想しています。
(おわり)