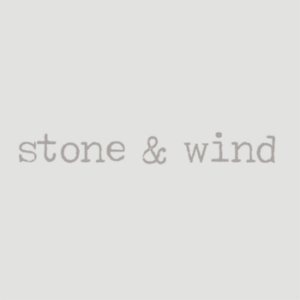3月31日は高場乱(おさむ)の命日である。
高場は天保2年(1831)博多瓦町に生まれた眼科の女医で、その家塾から後の玄洋社の頭山満をはじめ多くの弟子が育った。
高場に関する資料を時々読んでいたのは、ノートをみると2000年から2006年程で、その頃高場の墓参りに崇福寺の玄洋社墓地を訪ねると草は長く生え、あまり手入れらしいものはされていなかった。
高場のことも今ほど知られていなかったと思う。
毎年3月31日になると気になりながらこの10年近くは参ることができずにいたのだが、命日には少し早いある日、急に思い立って出かけたのである。出かけるといってもその気になればすぐの場所なのに、おかしなことに、昔の思いの籠った場所に行くというこころの余裕がなかったのだ。
驚いた。
山門を入り墓地の方を向くと、何もないはずの場所に大きな像が見えた。
「牛」はそこからは見えなかったが、それに横座りに乗り髪を茶筅に結んだ細身の、椿を手に持つ、玄洋社会館に残る軸の画のままの大きな像であることはすぐにわかる。像には彩色が施されている。
墓地は石を敷き詰めてきちんと整備されており、その像は令和5年3月31日建立とある。
墓の位置は変わらない。
中央に五輪塔を挟み左に高場乱、右に来嶋恒喜。頭山満の墓もある。
後ろに回れば五輪塔裏に「殺身成仁」来島には「明治二十二年十月十八日於東京霞関自刃行年三十一」と頭山の勢いのある書が刻まれている。高場の墓碑の裏は勝海舟書である。
墓地の周りを玄洋社社員の墓石がきちんと取り囲んでいるのは整備されたときに揃えられたのかもしれない。
敷き詰められた石の上を 歩きながら、あの頃何に惹かれて高場を調べていたのだろうと思った。
高場乱は、男子として育てられ、帯刀を許され医学と漢学を学び、儒学においては、古学派ながら自由研鑽を旨とする亀井塾で亀門四天王に数えられた。同時期に父の跡を継ぎ診療をし、人参畑、現博多駅前4丁目に移り眼科と共に興志塾を開いた。
ここで、悪ガキといわれた少年たちを育てるのである。
夢野久作の言葉を借りれば、「タカが女の学問塾と思って軽蔑すると大間違い、頭山満を初め後年、明治史の裏面に血と爆弾の異臭をコビリ付かせた玄洋社の諸豪傑は皆、この高場乱子(原文のまま)女史と名乗る変わり者の婆さんの門下であったというのだから恐ろしい」
「当時の福岡でも持て余され気味の豪傑少年は皆このシュル・モダン婆さんの時世に対する炬火(かがりび)のごとき観察眼とその達人的な威光の前にタタキふせられたものだという」
夢野久作「近世怪人伝」は時に声を上げて笑うほど面白い。しかし、表面に出すことはない、その底に流れる哀しみと強風にも顔をむけたまま逸らさぬ視線が伝わってくる。
もはや滅びようとしている、己の守るべきものに愚直に忠実な人々への敬意と哀惜の念を可笑しさの中に塗りこめている。
資料を読むにつれて、高場の人となりについて又当時の眼科治療についても興味が膨らんでいった。そのうち、全く知らなかった幕末から明治にかけての福岡の歴史にふれていくと、あの悪童といわれた子供たちのことをおもわずにはいられなくなってきた。
勤王、佐幕と、ころころと藩論が変わる。其のたびに多くの藩士が切腹を申し付けられる。
どちらの思想にしても、志を持ったものは死んでいく。藩は財政難であり、その政策は、時に一時のバブルを起こしては急落する。大風は吹く。水害はおこる。警備を担当していた長崎のみならず玄海沖にも異国船はあらわれ対応におわれる。コレラは流行る。江戸は大地震。黒田藩邸も崩壊する。
落ち着かぬ世相の中、おそらくは壊滅した筑前勤王党の子弟も、多く高場の塾に入門したことだろう。
そんな中、「近世快人伝」の武部小四郎と少年たちの話は、ずっと私の心にある。
福岡の変が鎮圧され、少年たちが捕らえられ拷問を受けていると聞いた塾長の武部小四郎は、逃げおおせていたにもかかわらず、少年たちに罪はないと証言する為に、取って返し自首する。処刑の早朝、自分たちのために武部が斬られると知った子供たちは手を握りしめて正座し耳を澄ます。少年たちの牢の場所を知らぬ武部もそれを察し大声で「いくぞおお」と叫ぶのである。少年たちはひれ伏し泣く。その声が「一生の腹の腐り止め」になったと、少年のひとり、奈良原至は後に語り、そのこころのまま一生を送る。
奈良原の人生を全て称賛するというものではない、が、腹の腐り止めは私にとっても常備薬なのだった。
何か秘めた心はある。しかしそれをどう表し、何をすればよいのかわからない。そうした暴れん坊たちを、高場は受け入れたのではなかったか。
腹を据えて受け入れる胆力と、客観性、身に着けた学問、そして、子供たちを縛らぬ融通無碍な「いいかげんさ」は彼らを生き生きと過ごさせたのではないか。
高場が女として生まれ男として育ち、人として生きたことに、私は矛盾を感じない。
高場には矛盾を感じさせない落ち着きと、りきみのない、力の抜けたところがある。
藩も周囲もそれを認めていた。弟子たちも疑問を挟まなかった。
玄洋社を起こす前の子供たちと高場について、私はノートにこう書いていた。
一言でいえば、代価可能な近代の価値観を否定する愚直なまでの無私と熱
今も変わらず、私は、そこに惹かれるのだと、思った。
しかしそれは、玄洋社を設立する前の彼らである。
当時、玄洋社社史にも目を通した。今は記憶も曖昧になっているが、まず感じたのは違和感であった。
高場を調べる前の、私の玄洋社のイメージは、今思えばロマンに過ぎるが、大陸浪人のそれであった。自らの義に忠実で、おおらかで、国にとらわれず易々とそれをこえるような。
夢野久作は、玄洋社を語る故老の話として「主義も主張もない何もない。今の世の中のように玄洋社精神なぞいうものを仰々しく宣言する必要もない。ただ何となしに気が合うて、死生をともにしようというだけでそこに命知らずのれんちゅうが、黙って集まり合うたと言うだけで、そこに燃えさかっている火のような精神は文句にも言えず、筆にも書けない」と伝えている。おそらく、そうであったと、思う。
しかし、その後、その軸足を無防備に、強く、近代国家に置いた在り方は、国を超えた義侠心からの働きはあったとしても、それからの時代を背に又その熱ゆえに、危険と幼児性を合わせ持つようにおもえた。
高場の墓に並ぶ来島恒喜が大隈重信の馬車に爆弾を投げ入れたのは墓碑にあるように明治22年。右脛骨粉砕上腿切断、大隈は右脚を失った。高場は「如何なる訳か門弟毎に正直に流れ、匹夫の雄に落ち、愧じ入り候義、諸国への聞こえ甚だ残念に候」と書いている。
諸国への云々は、私は理解しがたいが、正直にながれ、、、愧じ入、の言葉に、高場の悔いを見る。多くの弟子たちの死とこれからに対する暗然とした思いと彼らへの愛おしさ故の悲しみを感じる。
来島は罪が人に及ばぬよう周辺を整理し身一つで事を起こした。その生き方に、襲われた大隈は感じ入り、命日には香典を送り続けたと聞く。高場も来島のその在り方にだけは、そっと頭をなでたのではなかったか。
その二年後、病を得た高場は、くすりを飲まず、食を断ち静かに一生を終えた。
20年以上も前のノートである。
頁を繰りながら、その隅に小さく走り書きがあるのに気づいた。何か途中で思ったのかもしれない。
目の端に入ったまましばらく眼を動かせなかった。
そこには、薄く、タリバンの少年たち、パレスチナの少年たち、と書いてあった。