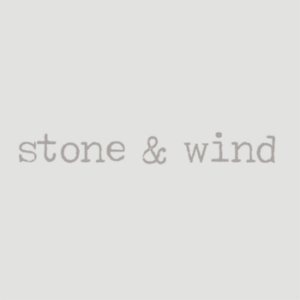朝の散歩をしていると、出会う人と「おはようございます」と挨拶を交わす。
犬を連れている人は犬同士の挨拶もあるので自然に言葉を交わすようになるのだが、ただすれ違うだけの人たちも挨拶だけは交わしていく。お互いに微笑みがあると、それだけで良い一日が始まる気がする。全く知らない者同士であるのに早朝だけは不思議である。もし、日中に見知らぬ人に挨拶などしたら不審者とみなされかねない。
日の出に手を合わせたくなるように、差し込む朝日に顔を向けてその光を浴びたくなるように、早い朝は特別なものなのかもしれない。
40年以上前にも早朝に散歩をしている時期があった。東京中目黒のすり鉢状に低くなっている場所から坂を上り木々に包まれた、くるりと曲がる石段を昇り詰めると、洒落たマンションがありそこを過ぎると猿楽町、代官山に出る。
当時はヒルサイドテラスやマダムトキ、そして幾つかの大使館がある静かな町だった。昼間になると人は増えるものの混雑することはなく独特のいい風があった。レンガ屋というレストランやカフェ、トムズサンドウィッチ、ビギのカフェ、吹き抜け地下のアントニオというイタリア料理店は上から見る事ができ舟に果物や花を飾って吊り下げてあった。レストランに行く生活の余裕はなく外から眺めるだけだったが、どの店もつい微笑みたくなるような粋な作りだった。裏庭には古墳があり、先に進むと西郷山公園から時々富士山の頭が見えた。
ヒルサイドから、少し歩くと同潤会のアパートがあり、古いレンガ造りの壁で、中庭に入り込むと夢かと思うような、静かな、時間のゆらぎがあった。薪も積まれ銭湯に見えたのだが、記憶違いかもしれない。どこも変わり始めたのは、今も有名な雑貨店ができ、交差点に沿って新しいビルが建ち始めた1983年ころだっただろうか。
賑やかになり人が増え店が増えて、お洒落な若者が行き交った。そして確実に失われたものがあった。
それは「さりげなさ」であった。店も、上質なものも、高価なものも、古いものも、廉価なものも、そこに集う人々も皆、さりげなかった。人も物も、その多くは、さりげなくあるべき位置にあった。
そんな中に、それこそさりげない小さなシェ・リュイというパン屋があった。今もあの大きさだと嬉しいのだがどうだろうか。初めて入った時には、バケットの香りや、甘いものにも本物のバニラ等を使用してあること等も、今なら珍しくもないのだけれど当時はこれが都会かと思ったものだった。道を隔てて向かいには、同じ経営のこれも小さなビストロがあった。ホワイトクロスではない小粋な店であった。
ここで、思いもよらぬ挨拶を受けたのである。
妹が上京し、ちょっと奮発してお昼をとることにして赤と白のクロスのテーブルに着いた。店の入り口にレジがあり、そのカウンターに立って後ろ向きにお茶を飲んでいる人がいた。
大きな湯飲みで「お茶」をすすっていた。
ふいに、「お嬢さんたちはよくこういう所で食事をするの」という声がした。開店したばかりで客はまだ私たちしかいない。妹と顔を合わせて、いいえ、と言った。
振り向いた湯飲みの人は、渥美清であった。
色が白く、横から見ると、随分身体が薄く見えた。物静かな話し方だった。私も福岡から妹が来たので、など答え少し話を交わした。そして、「男はつらいよ」は全て見ています、と言った。本当に全部見ていますと言いながら頭がいっぱいになったような気がした。「そう、ありがとう」と小さく答えを聞いた時、とっさに聞いてしまったことがある。若かったとはいえ、何故あんな不躾なことを聞いてしまったのだろうと、何故あんな言葉が出てしまったのだろうと、今でも申しわけなく、ぎゅっと胃が縮む。
私は「お辛くありませんか」と言ったのだ。少し間があって「つらい・・・・かなぁ」と答えがあった。
それから、少し話をして、彼はお客の入りと同時に私たちに少し手を挙げて、軽く二度肯いて店を出ていった。
近くに事務所だったか、住まいがあり湯飲みは店で預かっているとの事で自分から話しかけられるのは珍しいと、店の方が言われた。私たちは、田舎から出てきていかにも嬉しそうに仔犬のように喋っていたのが珍しかったのかもしれないと思った。
1995年の暮れに家族で「男はつらいよ 寅次郎紅の花」を観に行った。
海に居る満男達の姿を眺める寅さんの横顔が映し出された途端に、それはセリフの合間のほんの短い間の眼差しだったのだが、うろたえるほど涙が出て止まらなかった。
劇場が明るくなると恥ずかしいほど目を腫らしていた。訳がわからなかった。
「男はつらいよ」を最初に観たのは友人の誘いだった。「すごく、おもしろかったねえ」という友に、私はどこかもう一つ入り込めないと言った。ところが、二作目を一人で観てからは、あの「トつーん」というオープニングの初めの音を聴きあの歌を聞くだけでもうじんわりとしてくるのだった。渥美の語り口調も声もたまらない。御前様、さくらをはじめ、あの世界に、私はそしておそらく私たちは季節ごとに、帰るのだった。何かどこか、すがるような気持ちも少しあった。友はそれからあまり寅さんを観る事もなくなり、苦労して医者の道を進み始め、私は何もかもから逃げて酒の中にいた。
「寅次郎紅の花」を観た翌年、96年の8月、飛行機の中央スクリーンのニュースで渥美清の死を知った。
私はそれまで彼の病のことを知らなかった。思わず息を吸い「あ、あ・・」と声にならぬ息を吐いた。そして、あの映画の、あの一瞬の眼差しを思い出していた。
あれは、渥美清が、命を見ていたのだ。海にいる若い二人に、命そのものを見ていたのではないか。だから、何も言葉に変換されることもなく心にそのまま入ってきたのだった。
そして、ラストシーンを思い出した。震災後の長田区。その時の記憶では瓦礫の横に寅さんが立ち、瓶に挿した供花から被災跡の空き地へと歩く。パン屋夫婦等との会話があり、カメラが引いて跡地に立った姿からチマチョゴリを着た人々の踊りの輪へと広がる。
山田監督と渥美清、震災で失われた命と生き抜いた人々、監督にとっての盟友の命、渥美自身の死への思い。二人の思いが溶け合う画面だったのではなかったか。
飛行機の座席の背もたれから滑るように座り、映像を描きながら長い間、思い続けたのだった。
寅さんの最後のセリフは被災した人々への「本当に皆さまご苦労様でした」だった。
これが、俳優渥美清の最期のせりふになった。
ゆうべの台風 どこに居た ちょうちょ
風天
風天は渥美の俳号である