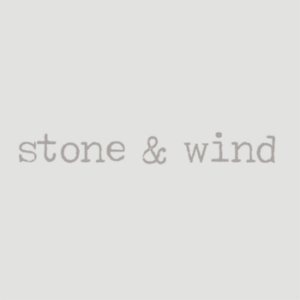上海の田子坊という通りに「老上海」という店があって、面白い絵葉書や本や画を売っていた。中でも『老上海』(昔の上海)を描いた賀友直(1922-2016)のペン画はとても好きで、お土産にコピーされたものを行くたびに買って帰った。賀友直(He Youzhi)は中国ではよく知られた挿絵画家らしく、私は、彼の引く線そのものが好きで、そこに描かれたおそらく1930年代から40年代前半の庶民の日常もとても心惹かれるものだった。
賀友直は上海のモダン都市化、租界期の混合文化開始から終焉と共に育った。風俗から見ると、1930年の頃を描いたものも多いらしい。とすればその頃を描いたものは、幼少年期の記憶によって描かれたことになる。不思議な透明感でこちらの眼に入るのは、大人になって回想する子供の眼差しではなく、子供の眼差しがそのまま描かれているような気がするからなのかもしれない。
線画には、耳かき屋、帽子を深く被った車夫が引く人力車、足マッサージを受ける太った男の、くううっと痛みを堪える様子など、当時の様々な職業や庶民の生活が活き活きと描かれている。餅(ピン)を焼く人、肉を捌く街の湯気を感じる画もあれば、魔都らしくアヘンを吸っているものもある。
煉瓦造りのアパート夫々の部屋の人々が洗濯物を長い竹で干したり子供が走ったり、女性が窓から窓へと移動したり、筆で何か書きつけていたり、老婆が孫のシャツを着せていたり、食べたり、喧嘩をしたり、麻雀をしたりする生活が、一枚の画の、一つ一つの窓越しに描かれる。一階の路地には自転車で牛乳を届ける様子やゴミ拾い、天秤棒を担いで麺を売る人々が通る。こうした街は建物で囲って門を作りそこに路地を通す独特の造りで、「弄堂石庫門房屋是上海的特産」と書かれているので当時でも珍しい上海独特の造りだったのだろうか。人々は大抵中国服を着ているが、金持ち風の人は帽子を頭に革靴皮カバンである。
そういえば、上海をぶらぶら歩いていて、ふと門に気付き入ってみると、レンガ造りの建物に囲まれた狭い通りがあった。そこには、道に竹かごや筵(むしろ)を敷き野菜を並べ、青いプラスチックのたらいに肉を入れ、立てた棒にも肉を下げ、地面に伏せた竹かごには生きた鶏がおり、たらいの魚はぴしゃぴしゃと水をはね、田ウナギはドロンと身をよせていた。市場というより露店が集まっては消える路地のようにおもわれた。中には逃げ出してきたすっぽんが歩いたりしている。人々は薄いビニール袋に沢山の品を詰め込んで歩いていた。
今思うとこれが石庫門房屋で、おそらくはあまり豊かとはいえない人々の住まいで、かつては上海にいくつもあったのかもしれない。そこに、今も、まだあの「市」はあるのだろうか。
「老上海」では、印刷されたアパートの画を分けて、便箋を作り、それを折り角を糊付けするとそのまま画が繋がり、封筒になるように配されている冊子があり、便箋ごとに画が異なり大変洒落ていて、表紙には、門と左右に広がる店々の繊細な画と共に「弄堂裏的 老上海人 二〇〇八年 九月 賀友直書」に続き説明が墨書されていて、それを見るだけで嬉しくなるのだった。
中華民国、共産党、日本軍、複雑な大変な時代、悲惨な戦争が激化する前のほんのひとときの生活。毎回日本人としても複雑な思いを抱えてこの街を訪ねたが中国という国の、描く、書く、覚く、ということを垣間見る楽しみもあった。
ところが、10数年前から田子坊も変わり始めた。奥にあった少数民族の布を扱う店は洒落たポーチなどの土産物が揃うようになり、「老上海」の品もポップなものの方が多くなった。洒落たカフェもでき始めた。扇子の店は愛らしいミニ番傘を作り美しく天井からぶら下げて若者の目を引き、次第に「老」の空気は消えていった。
アジアは旧暦の正月を祝う。日本は新暦の正月にあっさり切り替えたが、旧正月は新春、初春の香りがする。中国も旧で祝う春節ながら10数年前の外灘の新暦の大晦日は大層賑やかなものだった。
現在では、花火は縮小、観光客の爆竹は禁止、それに伴い交通規制もゆるやかになったと聞く。だとすれば、あのような大晦日の出来事はもうないかもしれない。
外灘はイギリス租界であり金融商業の中心として東洋最大の国際都市であった。 1840年のアヘン戦争、42年の南京条約で、上海にはイギリス、フランスなどの租界が設けられていた。
ヨーロッパ様式のビルが建てられ、今も残るレトロな建築群となっている。銀行、新聞社、ナイトクラブ、ジャズ、映画館などの賑わいと黒社会の台頭などは映画やドラマで良く知られるところであるが、外灘を取り巻くように中国人居住区「華界」があり、あまり類を見ない二重構造都市であった。国民党と共産党の戦い、日本軍の侵略占領、その間もこの構造は変わらなかった。
沢山の事を頭に浮かべながら、食事の後、私たちは大晦日の外灘を歩いた。
コートを着ていれば風が心地よい。光あふれる美しい旧いビルの連なり、聞こえてくるジャズやバイオリンの音色は租界時代をふと思わせる。それはモダンな華やかさに溢れた金と退廃、それを囲む貧困と生活と思想の渦、デカダンな闇と光は人を酔わせる。と、良い気になって歩いていてタクシー乗り場に一台も車がいないことに気付いた。そういえば先ほどから日本人観光客を見ない。ビルの入り口で訊ねると、今から花火が始まり今夜は夜中まで車は進入禁止だという。聞いた途端にヒュウーッと花火が上がり河上に広がる。対岸の東側は新都市で高層ビルが立ち並びあのテレビ塔が建つ。未来都市が浮かび上がる。おおきな歓声と次々と上がる花火で賑やかな事この上ない。少し間をおいて、「たまやー」などというような余裕はなくバンバン上がる。その上に爆竹である。めでたい。めでたいが、疲れる。私たちは帰ることにして歩いたが、どこにも車を見ない。引き返してドアマンにきくとかなり広い範囲で車は止められているらしく、タクシーも場所を指定して呼べないという。ホテルまでの道は分からないし、かなりの距離があった。何せどこに行くのも旅行社を通さぬ弥次喜多である。ましてや上海は博多から近い。ろくに調べてもいなかったのだった。
まだ携帯ナビで案内など出来ぬ頃だ。書いてもらった地図を頼りに歩くしかない。大変な人込みである。中国人より西洋人が多い。日本人はきっと調べていて早々に帰ったに違いない。肩が触れるような道から少し広い通りに出る。そこも人で溢れている。が、バイクで引いた力車に乗ってはしゃいでいる人がいる。空いている俥はないかと見廻すが勿論いない。ぶつかりながら歩き続ける。がしっと肩に何かがあたる。痛っと横を見ると力車で人は乗っていない。指さすと顎をしゃくる。「大丈夫かな」と合い方が言う。「たぶん」と答えてホテルの名刺を見せる。その時顔が見えた。ブルースリーの拳法の師を描いた「イップ・マン」という映画の主人公にそっくりだった。
狭いシートに座る。勿論赤ゲットなどは掛けてくれない。ちょっと、斜め後ろに俥を引く。車線などないも同じの人の波と俥である。ぶるん、ぶるんとエンジンをふかす。満を持すような、待て待てとはやる馬を抑えるような気配である。少し間をおいて、人が空いた隙にぶおおおんと出発した。私たちはのけぞった。バチッと俥の端同士がぶつかる。座席を引かぬバイクもどこからか出てきて人を拾って走る。俥はびゅんびゅん飛ばす。脚のすぐ横をすれすれにバイクが通りあわてて引っ込める。ここで脚を失ってもだれも責任をとらないだろう。人の波を見事に縫うようにして進む。そのたびに深く傾きバイクから席が抜けるのではないかと思う。ちらりと見える車夫の横顔は面(おもて)をかぶっているように静かである。前から来る俥に若い白人女性が立ち上がって、手を挙げ満面の笑みで叫んでその手を車夫の方へ向ける。と、彼はすっと手を上げて、ハイタッチをした。一瞬横を向いたその表情も微動だにしなかった。幌をつける横棒を掴み私も立ち上がってみた。冷たい風が心地よい。
人の波や俥やバイクがぎりぎりに横を過ぎる。爆竹や声の固まりが渦を巻きながら後ろへ後ろへと流れ飛んでいく。
花火の音は遠ざかった。やがて人も少なくなり車が通る道に出た。そこでも、ハイウェイのように加速しながら、やがて低い丘の見える道に入るとスピードを緩めた。車も増えてきた。見覚えのある丘だった。ここにホテルがあるのだ。丘に登らず、彼は俥を止めた。指で降りろと言う。私も指で上を指すと再び降りろと指さす。ドアマンに見られたくないのだと気付いた。支払うと首を振る。乗る時に言われた賃金ですというと、きれいな英語で、あれは一人分だという。仕方ないなと顔を見合わせタクシーの何倍分も渡す。けれど、私は満足だった。こんなに面白かったのだ。昨年までは二軒の家を整え、出来たおせちや出汁の寸胴を本家に運ぶ大晦日だった。15年間、それはそれで楽しかったが、夫が本家を継いで取り止めた。先ほど外灘で食事を終わるまでは、大晦日らしくないと思っていたのだが、一転、こんなに面白い年越しは初めてだと心弾んだ。
「A happy new year」表情は全く変えず彼は言った。「新年好」私は答えた。ぶるるんと音を立てて去って行く後ろ姿にもう一度「新年好」と呼びかけた。
彼は直角に肘を曲げたまま手を挙げて、スピードを上げた。
ホテルに入ると黒を基調に中国の意匠を潜めたネオチャイニーズと呼ばれるシンプルな静かなロビーにやはり黒の端に細く赤の縁取りのあるチャイナ風の制服を着たスタッフが出迎えた。静かに新年の挨拶をして、彼はエレベーターのボタンを押した。
何だか、長い時間の旅をしたような気がした。