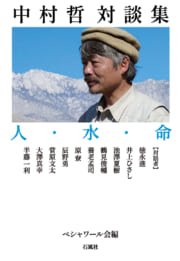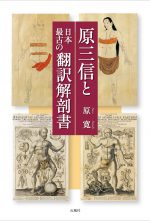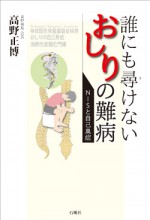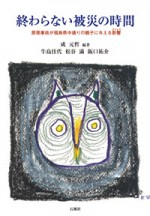疾病より人間への関心
1
認知症者と私の診療の関係は、出会いの時に気があえば長年にわたって続いている。断っておかねばならないが、私は日本精神神経学会精神科専門医、日本認知症学会専門医、日本老年精神医学会専門医の資格はあるものの、疾病よりも人への関心を持っており、今どきの精神科医から外れたマージナルな精神科医なのかもしれない。もとより、精神科自体が、医療のみならず一般から辺縁(マージナル)の存在と見なされて、それが精神科医の存在意義と思っていた過去もある。
20年以上も認知症の診療に携わっていると、色々な逸話を見聞したり経験したりする。この章では、認知症者と関係者との幾年月を通じての交流とエピソードについて、不確かな記憶と主観的な解釈に基づきながら語ることにする。
親子2代
この人は70代で認知症を発症した。早い時期から受診したのは、認知症者だった母親も10年以上診療しており家族として同伴していたからだった。同居の母親を長らく介護して最期を看取った経験があるためか認知症を本人なりに受け止めていたようだった。本人の家は代々酒屋を営んでいたが、本人の時代には昔ながらの得意先の注文だけになっていた。それでも家業の成り行きも現実として受け入れ、診療場面では、10年間悲観的な発言はなかった。2か月ごとの面接では、店番のこと、喫茶店に行くことが楽しみだということなど話していた。喫茶店は若い元気な頃の話であるが、毎回、現在のこととして繰り返していた。現実的な日付や社会の出来事について尋ねても「分からない」の一言で済ませていた。受診から10年目に癌の診断を受けてあっけなく亡くなったが、最期の面接でもいつもと変わりない会話を楽しんでいた。
喫茶店と言えば、若年性認知症の女性のことを思い出す。診察場面では屈託のない表情でよく笑う人だった。初期には「友達と喫茶店をやりたい」と語っており、診察の度に「西田佐知子のコーヒールンバ」の話に声を上げて喜んでいた。数年後、認知症が進行して、言葉も体も不自由になり、自分では動くことが出来なくなっても、面接では、喫茶店とコーヒールンバの言葉に、分かったように西田佐知子のような笑顔で応えてくれた。
別の一人は、私が親子2代にわたり診療をしてきた人である。一人暮らしの母親が施設に入所するまで10年以上母親の受診に同伴していた。数年後、自身が夫にもの忘れを指摘されて受診すると、検査では軽度認知障害(認知症の前段階で、必ずしも認知症に移行するものわけではない)に相当していた。本人ももの忘れは認めていたが「他の人にもあることで、
自分より分からない人もいる、夫も自分と同じくらいもの忘れがある」と、実母のような認知症としてのもの忘れとは認めず回避しながら現在に至っているといえる。10年間で、徐々に認知機能は低下したが軽度に留まっており、口達者で家庭生活には支障がない。本人にとって認知症の否認はそれに対するレジスタンスとして、自分を律して生きる支えになっているようにも思われる。
認知症に対する知識や受け止め方は人それぞれであるが、医学的知識があるゆえに、実際に関わった人にとっては「怖い病気、なりたくない病気」とされている。また、「認知症になる、あの人は認知症だ、あの人はアルツだ」など、認知症者自身を認知症と同一視するような表現が通るところがある。もとより、人と疾患は別物であるが、日本語には認知症者の主体性や人権をあいまいにする一面が感じられる。他方、一般の人の中には、認知症を「にんち」と呼び、「にんち」が入ったという見方をすることもある。これは「にんち」と擬人化して、人と病気を同等視することで直面する困難をかわしていく庶民のささやかな抵抗といえるかもしれない。人と動物の同格視は、古くは鳥獣戯画の世界にも描かれている。
徘徊
認知症者の徘徊や行方不明者については、代表的な認知症の行動・心理症状(BPSD)として知られており、家族にとっても、社会にとっても重大な懸案になっている。その人は、夕食後、こっそりと自宅を出て、今はない旧飛行場当たりまで6キロほど歩いて行き、その付近にたどり着いたものの飛行場を見つけられずに座り込んでいるところを保護された。それを契機として私と出会い、「どうしようもないですね」と苦笑する妻と共に10年以上の交流となった。その後も同じ経路を徘徊して、保護されては警察官に家まで送ってもらっていたが、「すんまっしぇーん」の言葉に苦笑いで許されていた。認知症が進行して言葉が限られてきても、自分が困った時には「すんまっしぇーん」で切り抜けている。謝らない、赦さない規範圧力の強い社会の中で分かって欲しいせりふでもある。
もう一人は、住みなれた古家に一人で生活しており、自由に外出していたが、家族が室内の様子や話の内容に疑問を感じて受診となった。認知機能検査では軽度認知障害であったが、初対面の私に、何故か、嘘か真か「家で幽霊を見た」と語った。現役時代の仕事や人脈についての知識や記憶はまだ保たれており、趣味で古いレコード盤の収集を自慢していたが見せてくれることはなかった。この人も認知症が進行した頃から、従来の街歩きではなく自分なりの用件を思い立つと、時間を問わず5キロ以上の目的地まで出向くようになった。徒歩で行った訳は、「タクシーが止まらなかった、バスがなかった」ということだった。幽霊話は、尋ねると「出た」と答えるも切迫した表現ではなくなったが、私には、熊本にいた八雲の顔と重なっている。5年後、住宅が区画整理されるため施設に入所することになり、反応を心配されたが、最期はもの分かりよく立ち退いた。
幽霊話
もう一つの幽霊話は、90歳を超えた人だった。介護施設に入所して、穏やかに、何事もなく暮らしていた。ところが、ある時から夜な夜な叫び声をあげるようになり、次第に叫び声は施設全体に轟きわたり、昼間も叫ぶようになったので入院してきた。
面接では、落ち着いて上品な態度であったが、夜になると絶叫が始まった。翌朝に夜間のことを尋ねても記憶はないようだったが、しばらく経ってから「幽霊の夢を見なかったか」と尋ねると、「見た」と答えた。古い童唄にある「幽霊に揉まれた天台さんの乙姫」の話は聴いたことがあるということなので、叫びは幽霊のせいだという訳のある話にして、本人の恐怖感を宥めていった。その後、本人が数を唱えるようになった頃から夜も眠れるようになって、私のことを、別名の時もあるが、「先生」と呼んで喜ぶようになった。両親も生きていると言うので、本人のルーツ(家族)を求める心性を満たすため長男夫妻に面会を多くしてもらった頃から、叫び声はほとんどなくなって、元の施設の戻ることが出来た。家族療法で言われていた、家族の力(エンパワーメント)効果を思い出した。
もう一人も90代の人で、若いころから精神的に不安定となることはあったが、落ち着けばしっかりした生活者であったという。70代後半になり、幻聴に続きもの忘れが始まって、過去の症状にも似た被害感や精神の混乱が激しくなり、興奮して「死ぬ」と包丁を持ち出して騒ぐこともあり、その後、頻回に入院することになった。認知症が進行しても、家族と私のことは認識して瞬間的には安堵していた。その後、大腿骨を骨折して歩けなくなり、認知症も重度化した。難聴と共にほとんど言葉が通じなくなると、ムンクの「叫び」の人物のような表情で「ホー、ホー」と訴えるような叫び声が残った。何か言いたそうな時も、何か怒っているような時も、同じ叫びであったが、いつの頃からか、念仏のように「80,81,82・・と」数え始め静かになったので、興奮してる時に、私が数を唱えると本人も数を唱えて温和しくなった。後日談として、その人が施設に入所することになった施設の初代施設長から、本人が10代の頃プロポーズされたというサプライズまであった。
妄想と生きる人々
この女性は、30年近く自分だけで「妄想」を抱いたまま90歳を迎えた今も一人暮らしを続けている。「連中」は、昼間はどこかに行っているが夕方になると家の床の下に入り込み、冷蔵庫から食べ物や食材を持って行き、畳の下にテープレコーダーを仕掛けて録音していると毎回の面接で述べる。「連中」の中には以前の職場での知り合いもいて、悪い人たちばかりではない。煩わしさはありそうだが不安や恐怖感の訴えはなく、夜は良く眠っており、警察に通報したことはない。一度引っ越したこともあるが、すぐに「連中」はやって来た。自転車の使用を止められて、まとまった買い出しは嫁いだ娘が手伝っている。最近は、年末年始を
娘の家で過ごすようになり、滞在中は「連中」は現われないが長居せず数日で自宅に帰る。彼女にとって、「連中」は招かねざる客ではあるが、逃れられない「妄想」から自らを律して地道に生きている人間の在りようでもある。
もう一人は、「妄想」に苛まれながらもめげることなく毅然とした態度を保っている人である。始まりは、思い過ごしのようなことから、「犯人」が絞られて行き、この数年間は受診している病院の医師が「犯人」にされている。「妄想」というのは、体を電波で攻撃されるというもので、電波で靴下が破れる、補聴器の雑音が酷いなどもある。彼女はいつも丁寧に化粧をして服装にも気を使っており、女性兵士のような凛々しさもある。
日常の受診先は、「妄想対象」が勤務している病院であるが、主治医は別なので平気だという。生活に関する昼夜の確認電話が家族のストレスになり、本人も自ら定期的に入院してくる。その間も「電波」は止まないものの忘れたように過ごしている。これも本人なりの対処法(コーピング)だろうが、前述の人とは違い、家族を巻き込んでいる。
また、別の人は、長い間、県外で過ごしていたが、定年後の生活のため帰郷して、甥の家の隣に住むようになった。甥夫妻は、食事や受診などの世話を良くしていたが、ある時から甥の妻が自分の着物などを盗むと言い出した。甥には訴えるのに、その妻には直接訴えることはなく、食事は甥の家で認知症が進行して施設に入所するまで何事もないように食べていた。恰も「妄想する人格」と「妄想のない人格」の2面があるようであった。
この3人とも高度の難聴者であり、高齢者の聴力障害は日常生活に制約が生じるだけでなく、「妄想」や「幻覚」を誘発したり、認知症のリスクになるとも報告されている。認知症のリスクとされてきた歯の状態や視力低下に加え、難聴に対する耳鼻科的な関心がもたれている。
ただし、認知症と難聴の関連は疫学的に指摘されているが、そうではない人も多く、統計的なものの縛りを逃れ例外を生きることも、人生のささやかな冒険の切り札になるのではないかと思う。
家族の力
その人は50代で若年性認知症と診断されて、夫に伴われ私のところに来た。既に認知症はかなり進行しており、本人には受診の理由など分からなかった。診察室に入ることに戸惑い、着席するのも夫の指図が必要で、面接では夫が一方的に説明する横で不機嫌な表情や態度が多かった。その頃は趣味の会に参加しており、診察場面との違いが覗われ、夫の干渉も一因かと思ったことがある。
しかし、その後も、面接で夫は妻の自宅での様子を熱心に説明して、気付いた疑問を尋ねて理解に努めていた。数年後、認知症は更に進行して、言葉や行動の困難(失語や失行など)が目立つようになり、昼間は介護施設に通い、夜間は勤務から帰宅する夫が介護するという生活を続けてきた。この間、夫は気持ちの動揺を見せることなく、介護する生活を「ありのまま」として引き受けているように思われた。そして、当初は反発や拒否をしていた本人もいつの間にか、安心して夫を頼りにするようになっており、夫のぶれない献身の態度には学ぶものがあった。
認知症の予後は、病型によっても異なり、個人差もあるが10年以内の報告が多いので、10年の在宅介護は例外的かもしれない。10年ひと昔と謂われるが、家族にとって10年という介護の歳月は認知症者となった人を徐々に受容するための必要な浄化の期間になっているようでもある。
終わりのない介護はないが、認知症者自身が亡なくなったり、長期入院が必要な場合だけでなく、家族が自宅での介護を終了する心境についても触れておく。
母親を「かあちゃん」と呼んで受診に同伴していた家族は、施設に入所することについて母親に「もう、良かね」と告げ、認知症が進んだ母親は分からないながらも「うん、良かよ」と答えた。
母親を大事にしながらも認知症を学んでいた他の家族は、予定していたかのように10年目に入所先の介護施設を決めて「今度、施設に入ります」と、在宅介護の終了を清々と宣言した。
ある家族は、認知症のはじめは母親の言動に振り回されていたが、同居して落ち着くと、母親の疑いの余地がない幻聴話(政治家と話をする、その政治家の負傷を心配する、他の政治家の批評をするなど)を聴くだけで、家族も本人も話題として納得して安心していた。その後、新型コロナに感染したり、骨折をして、体力の衰えと共に、家族が分からない程に認知症が進むと、家族も施設入所に迷いはないようであった。
もう一つは少ない例だが、軽度認知障害のまま10年以上が経ち、これからも状況が変わらない限り同居を続けるだろう家族もある。
介護者が交替する例も少なくないが、記憶に残る例として、病前からの不機嫌や頑固さのため気の安まることのなかった手ごわい認知症者をさわらぬ神に祟りなしでつかず離れずの距離間を会得した妻が亡くなって、当たり障りなく子供が引き継いだ例もある。
とっておきの逸話は、二人とも認知症者である実家の父母の受診に同伴していたしっかりものの娘の話だが、両親が交通量の多い道路を渡切る行動などで二人が保護されて入院にする度に、愚痴を言うこともなくてきぱきと世話をする姿が印象的であった。
父親が施設に入所した頃から母親の受診には他の家族が同伴するようになった。ずいぶん経って、外来に来た娘はやせて言葉も弱々しかったが、本人からALS(筋萎縮性側索硬化症)であると気丈に告げられた。ALSは脳神経内科や神経病理学の主要なテーマでもあり、難病として知られている。精神科医で小説家でもあった、なだいなだの小説「しおれし花飾りのごとく」では、元気そうだったスナックの“ママ”がALSであったという50年以上前に読んだ本を思い起こさせてくれた。(つづく)