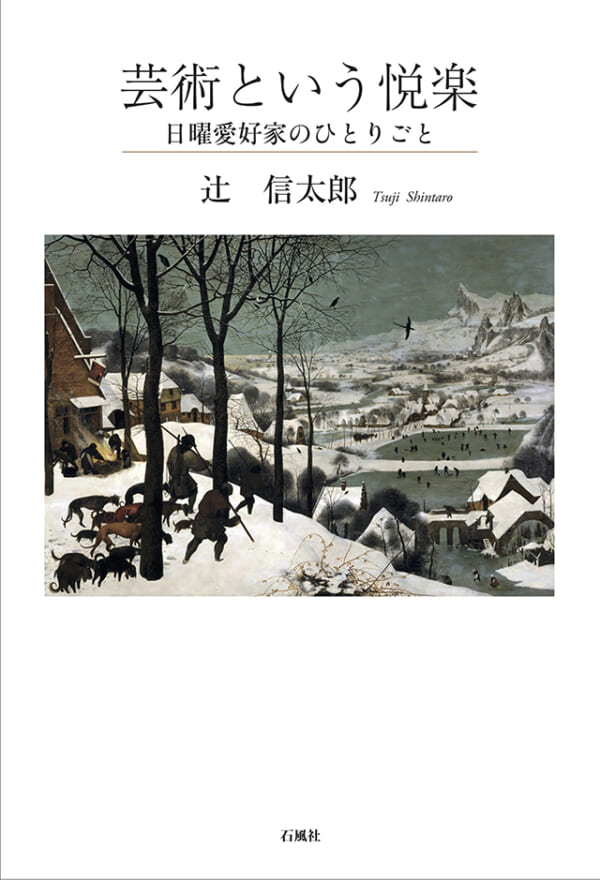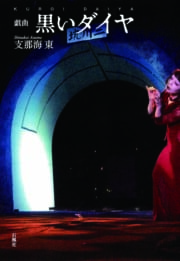金峰山の窯場の犬「ふく」は今年14才。去年、耳が遠くなり今はほぼきこえなくなったが食欲は旺盛で喜びのジャンプもいまだ健在だ。かつてはウサギ3匹、モグラは数知れず獲った強者だった。「ふく」の前には約10年生きた「キツネ」という犬がいた。両犬とも雑種で捨てられていた、一方は八代の公園、他方は窯場の近く、共に子犬の時だ。「キツネ」は柴犬の雑種、「ふく」はそれより一回り大きい白地に茶色の斑がある。
「キツネ」は金峰山の工房の近くにダンボウル箱で置き去られた5匹の中の1匹、連絡を受けやって来た動物センターの手を逃げ切ったのは彼女だけだった。野良犬となった彼女は数匹の犬を飼っていた隣家にたびたびやって来たがそこの主はこの雌犬をきらった。「キツネ」は嫌われていることが分かっていても周辺をうろつき、残ったエサを頂戴してこちらへも顔を出す。その当時、米国人の青年B君が毎日工房に通っていた。彼は無類の犬好きで当然「キツネ」に餌づけを始めた。手から餌を与えようとするが用心深く、決して一定の距離以上に近付かない。その様子からB君は「キツネ」と呼ぶようになった。「キツネ」は窯(半地下式の穴窯)の丸い天井の上を居場所と定め、平気で眠るようになった。少し高い位置からは周囲の見通しもよく、どの方向にも逃げられる利点があった。その後「キツネ」に子供ができ、悪いことに彼女を嫌っている隣家の床下に産んだ。ぺちゃんこの腹に気付いた私たちは赤ん坊を探し出し穴窯の横の窪んだところに移した。これで一安心と思った翌日には赤ん坊が穴から消えていた。窯道具を積み上げた奥の手の届かないところに移したようで鳴き声が聞こえるが、こちらも知らん顔を決めた。やっと安心したのか「きつね」は落ち着きをみせた。私たちとの距離も少しずつ近くなり、いままで触れることも適わなかった鼻面に触れると小さな身体が固まっているのが伝わってくる、逃げたいけれど逃るわけにいかぬ母犬がいた。次はどうやって首輪を付けるか、これは何度か失敗した、警戒され首をすうっとずらされる、苦労したはずだが今はどうやって首輪が付いたか記憶にない。
はじめの頃「キツネ」は窯の上を起点に日々野山を自由に走りまわっていたが、周辺の人たちは当然私たちの飼い犬と思い始めたので繋ぎとめることにした。隣家のクレームもあり潮時だった。「キツネ」にとっては迷惑な話で自由を奪われ、暫くは落ち着かなかったがすぐに慣れ、いつの間にか堂々たる窯の番犬となった。
後年、ふとしたことから隣家が「キツネ」を嫌っていた理由が解った。「名前」である。隣家のオバアチャンの名前が「ツネ」だった。いわゆる「オツネ」さん。当時私たちが毎日呼びかけた「キツネ」という声は隣家には我が家の婆様を呼び捨てにしているようにしか聞こえなかったに違いない。全く考えもしなかった、周囲への配慮も知らないまだ若く、未熟だったということだろう。
だみ声で女丈夫、女手ひとつで娘3人を育てたコワイ「オツネバアチャン」ごめんなさい。
「キツネ」が死んでまだ間もない頃、オマエにぴったしの子犬拾ったと、八代の友人がおっしゃる。出かけてみればメスとオスの子犬が2匹、メスはおとなしくオスはやんちゃ、もちろんやんちゃを引き取るが三つ子の魂は不変で天性のオバカ、教育とかしつけというものは相手の適性と不可分であることを犬におしえられた。ただただ元気だけが取り柄でこちらの散歩相手には丁度良かった。「キツネ」から「ふく」へと受け継がれた我が工房の犬は5メートルほどの自由と朝夕2度の山野の散歩、夜は窯の隣で独り眠る。この日々の暮らしが1年に一度だけ壊れる。「窯焚き」である。この3日間は人も犬も火を守りながら非日常を過ごすことになる。最初は人が傍に居ることに喜んでいる犬も昼夜なしの三日間ともなると次第に時計が狂い始め、最後は犬小屋から出てこなくなる。火を止めると人も犬も死んだ様に眠る、本当によく眠る。