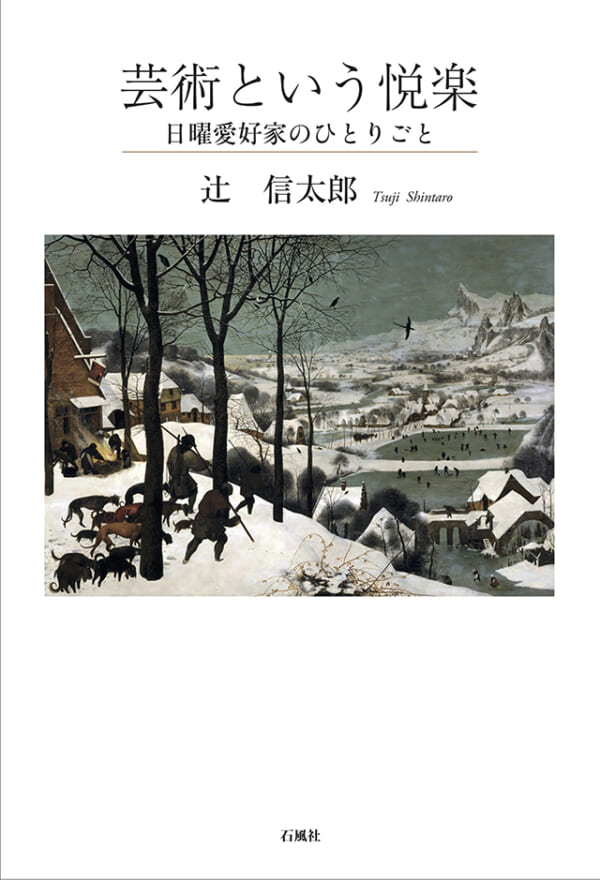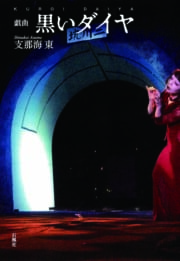「ヤキモノ作りは“土,釉薬、焼き”に尽きる、と思うんですよ」と穏やかだがキッパリとした口調で言っていたMさんが亡くなった。昨年の秋に癌と診断され、今年になって急変したという。64才。40年ほど前、お互い弟子時代、小石原(福岡県)にいた私は苗代川(鹿児島県)を訪ね、鮫島佐太郎さんの窯で出会った。以来、空白の時期はありながら変わらぬ交友が続いた。若い頃から口数が少なく、言葉を選び、丁寧に喋る人で、強い意志を感じさせる人だった。彼の作る器は粉引(こひき)と呼ばれる古典的技法ながら全く古びたところが無く、彼の言うところの“土、釉薬、焼き”に独特の工夫があり、それが品のある素朴さと力強さを生み、多くの人から根強い支持を得ていた。
Mさんが亡くなって1ヶ月後、梅雨の中の晴れ間を選び、私は初めて阿久根の工房を訪ねた。目印になるものが無いと言って、日傘を差した奥さんが歩いて1時間余りを牛の浜駅まで迎えに来てくれた。(彼女は運転しない。駅までの足はあるというので安心していたら、自分の足を指差して、「ホラッ、足はある」と言ったのには驚いた。)川内原発を遠くに見ながら山の方へしばらく入って行く、途中から車一台が通れるくらいの山道となりもっと進むとその先に彼らが工房兼住居として使っている元分校が現れた。標高はあまり高くないが少し窪地になった場所に錆びた遊具、端に2クラスの教室と宿直室、その前にはセンダンの大樹。教室2つ分が仕事場で、蹴りロクロ、焼成前後の器、土や釉薬の材料、テストピースなどで埋まっていた。この足の踏み場ない光景をゆっくりと見て行くと、土や釉薬のテストを絶えず繰り返していたことが浮かび上がってきて、現場だなあとつくづくおもう。古武士のようなMさんの
「なかなか納得できる色が出んですがねー」という口癖を思い出す。
その「色」こそ“土、釉薬、焼き”によって生まれるもので、そこに距離を置く私を諭しているようでもあった。校庭にはまだ4分の1程しか使われていない原土がシートで覆われている。愛用の灯油窯は窯詰めを終え,焼くばかりに準備されたままの状態だった。奥さんが見せてくれた焼成ノートには毎回の内部の配置、焼成条件の変化を実に詳細に書かれており、“土、釉薬、焼き”ということを求め続けていたことが分かる。その手応えを掴めば“作る”などということは自ずと湧いてくるような事だったろう。
以前、ある著名人が茶陶作りに入り、大々的展覧会、作品集出版と話題なったことがある。好評だったようで、知人の学芸員は「とても良かった、レベル高いよ」、友人の記者は「あの程度の年数でそこまで出来るのか?」と言う。その都度私の考えは話したが、どうも引っかかるものがある。あるとき古典に詳しいMさんに訊いた「これぐらいの年数で、このレベルのモノが作れると思うか?」暫く黙したあと、彼は「無理だと思います、一人では。余程、有能な協力者が居れば別ですが。」私と彼のヤキモノ観はかなり違っているが、この事では同意見だった。つまり“作る”ことは出来ても“土、釉薬、焼き”には多くの時間が要るという事だ。それでも私の引っかかるものが消えない。
「何故?」
それはは作品の良し悪しではなかった。つまり私は家柄、血筋佳き人の作品に対する検証を簡単に放棄する世間の空気が我慢できないのだ。佳き家柄の人の前では私たちは理由の無い期待と幻想を抱いてしまう。政治の世界では、やっとこれが無意味であると分かったが、他では厳然と通用しているのだろう。そして、この手の話にどこか苦い味が残るのは私たちのコンプレックスと表裏をなしているからではないのか。
阿久根の分校跡の校庭に立ち、空を見上げる。渓流がすぐ横を流れ、以前より大きく育ったという周りの雑木林がまあるく青空を縁取って、それを支えるように立つ大きなセンダンの木。Mさんはここで“土、釉薬、焼き”という命題から外れることなく、少し早くはなったがヤキモノ作りの生を全うした。