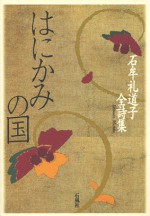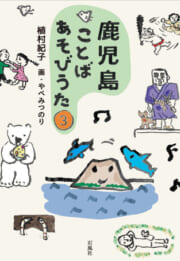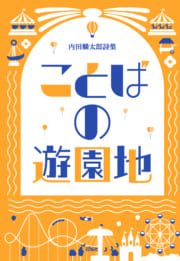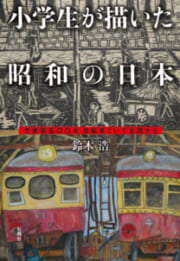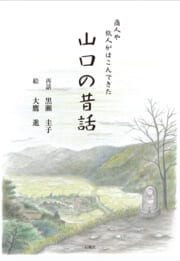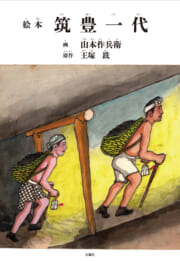◇はじめに
これから私が書こうとしているのは〝親子型同伴ノンフィクション〟とでもいうべきものだ。主人公のジイジは私の父である。ジイジはきわめて平凡な一般人である。世間が拍手喝采してくれそうな趣味も業績も何もない。それではなぜ書くのか。言うことすることすべてが味わい深いからである。
ジイジになる前の父にはあまり関心がなかった。関心がなかった、と書くと語弊があるだろう。書く対象にはならないという意味だ。その父がトシをとる。心身がおとろえる。ヨタヨタする父=ジイジに、がぜん興味がわいてきた。
なにしろみんなトシをとるのである。みんな死ぬのである。目の前のジイジを見つめれば、人間の運命を書くことにつながるのではないか。そう思うと、ジイジが、衣裳をまとって舞台に登場した役者のように見えてきた。実際には舞台映えしない外見である。普段慣れ親しんだ古くて地味な服を着ている。トホホという感じである。
私にできることはできるだけ正直に書くことだ。「できるだけ」というのはあまりホントのことを書いては肉親のことだけにマズイという思いがある。フィクションをまじえたほうが真実にせまる場合もあるのだ。
真実とは何だろう。人の数だけ真実はある。いや、場合に応じて真実は異なるというべきだろう。私は正直に書くだけだ。事実は真実を超える。読者はそれぞれの経験や感性に応じて、それぞれの真実をつかみとってくれるだろう。
医療や介護について書くことが多くなりそうだ。この私の文章を読み、「高齢化社会となり、お年寄りの医療や介護への関心は今後、どんどん深まってくる。そんな折、独り暮らしのお年寄りの具体的事例に満ちた、実に、役に立つ文章だ」と言ってくれる人がいるかもしれない。そんな人はいないと思うが、万が一ということがある。
私としては、不思議や意外性に満ちたジイジの言動を面白がって書くだけなのである。ジイジが医療や介護のお世話になる機会が増えるほど、医療や介護についても書きこむことが多くなるだろう。石牟礼道子を書くには水俣病が避けて通れないのと同じような事情である。主人公はあくまでジイジなのであるが、ジイジを置き去りにして筆がすすむことがあるかもしれない。
一般的に人間の九〇歳というのは大きな区切りである。八〇歳代まではそうでもなかったのに、九〇歳になったとたん、周囲の反応が変わる。「本格的な長寿の人だ。タダモノではない」という感じになってくる。一方で、加齢のため、どうしても認知機能が低下する。常識人が踏み込まない領域に踏み込むことが多くなる。なにかやらかしたとしても、「仕方ないなー」というあきらめにも似た空気が当人を包む。タイトルの「無敵の男」とはそういう意味だ。
◇そらの郷にて
九三歳のジイジは一九三二年、徳島県の北西部、吉野川の上流、北岸の町に生まれた。北に山を背負い、南に吉野川が流れる。日当たりのよいジイジの住む地域には古くから人の営みがあった。中世には集落ができていたという。
「そらのひと」とジイジは若い頃、言われることがあった。徳島市など県東部の都市部の人たちは、西部の標高の高い地域を「そらの郷(さと)」と呼ぶのである。「そら」という語感は爽やかだ。そこには差別的ニュアンスはなく、素朴で開放的というイメージがこめられている気がする。
一九六一年生まれの私は「そらの郷」などと耳にしたことはない。「そら」とは、東から見て西が秘境的に閉ざされて見える、交通が不便の時代の産物なのであろう。地味で何の特色もないと思っていたわが父祖の地が「そらの郷」というジブリ映画のようなネーミングの恩恵を受けていたとは愉快だ。
「そらの郷」のわが家では、地元の清酒「芳水」を愛飲している。「芳水」の酒蔵の桶を桶職人の私の祖父(ジイジの父)がつくったという因縁があるかららしい。私の幼い頃のトタン屋根の家には、竪穴式住居の雰囲気にも似た地下藏があり、切りそろえた竹を収納していた。湿っぽい闇に包まれ眠る竹。桶の材料なのであろう。
叔母(ジイジのいちばん下の妹)によると、祖父は話がうまく、祖父の周りにはいつも人の輪ができていた。けんかっぱやい無骨な人という記憶しかなかったので、叔母からその話を聞いたときは意外だった(その叔母も二〇二四年に他界した)。時々講演をする私自身の姿を祖父に重ねてみたくなる。祖母は家の一室で蚕を飼っていた。蚕がもたらすカネで祖父の乏しい収入を補ったようだ。地域一帯に桑の実があった。蚕を飼う家が多かったのだろう。
曾祖父は大工である。何かの仕事の見返りに土地をもらったらしい。その土地にいま地域の集会所が立っている。その曾祖父には女ばかり五人の子がいた。長女が婿をとった。その婿が桶職人の祖父だ。男二人、女三人の五人きょうだいの長男がジイジである。
私も妹のスエコも、就職を機に家を出た。二〇一九年に母が死んだ。母の主治医から「お父さんは(妻が死病にかかったという状況を)よく分かっておられないようです」と言われた。母の死をきっかけに父の認知面でのほころびが目立ち始めた。
いまジイジは「そらの郷」の古い家で一人で暮らすのである。母の遺影をソファに置き、「畑に行ったら、草が話しかけてくるんじゃ」「下野さんも谷山さんの家も、どの家も子供が都会に出たまま戻ってこない。仕方のないことじゃ」など、生きているように話しかける。それも終日であるから、ボケの一時的なあらわれとしては片づけられない。「かあちゃんは死んでいない」というジイジの執念が感じられる。演じているわけではない。口から自然と出てくる宗教の祈りのようなものだろうか。
「家が郵便局の事務所になった」と突拍子もないことを言うこともある。「職員はどこへ行ったかな?」と福岡市在住の私に電話してくる。「職員なんていないよ」と言うと、「実際にいるんだから仕方なかろう。ワシは現実にもとづいて話をしているんじゃ」と反撃してくる。「家が郵便局」というのがジイジの現実なら、私としては沈黙するしかない。
◇テレビを宰領?
異変をはっきりと告げたのはテレビである。「テレビを切ろうとしても、テレビに出ている人が、切るな、と言うんじゃ」と言うのである。地域一帯のテレビの放送を自分が宰領しているようにも思っていて、「もういい加減世話役をやめたいのに、やめさせてくれんのじゃ」とも言う。高齢者への戒めの言葉に「テレビに向かい合っているとボケますよ」というのがあるが、それを地でゆくようにボケつつあるのが感じられた。
「やめたい」がジイジの口癖になった。郵便局を停年退職後、かんぽの湯などでの嘱託職員も勤め上げた。地域や老人会の役員もすませた。コメづくりもいまはしていない。いま「やめる」ものはない。ジイジは菅義偉・総務大臣(当時)宛てに「退職願」を書いた。地域一帯のテレビの世話役をやめる、というのである。テレビを管轄しているのが総務省だとよく知っていたものだ。
二〇二四年、「もうひとつ退職願を書いた」というので見せてもらうと、後期高齢者医療広域連合会会長あての「退職願」であった。「やめたい」ジイジとしては「やめる」対象を探し、保険証の「後期高齢者医療広域連合会」にたどりついたのだ。ジイジは被保険者にすぎないのだが、連合会の職員であるかのように思うらしい。「退職願」を書いたとしても、ジイジとしては保険証を放棄するつもりはなく、あくまでも「職員」をやめたい、ということなのだ。
「後期高齢者医療広域連合会会長様/職員の退職依頼について/平素は色々とお世話になりありがとうございました。さて〇〇〇〇(ジイジの名前)の退職依頼については、本人は昭和7年8月20日生れで、当年92歳であります。老齢のため体調も害しており、生活にも支障をきたしております。退職の期日は5月5日を予定しておりますのでよろしく御配慮を願っております。本当に申し訳ありませんが、よろしく御配慮をお願いいたします。敬具/〇〇〇〇(本人名)捺印」
世間的には通用しないジイジの退職願であるが、「やめたい」という気持ちはなんとなく分かる。だれしも人生の局面のどこかで「やめたい」と思ったことがあるのではないだろうか。菅義偉や健康保険管理組合の偉い人の代わりに私がジイジの退職願を受理しておくわけである。
福岡市在住の私は二〇二三年、役場の中にある地域包括支援センターに連絡し、ジイジと面談してもらった。第三者の見立てがほしかったのだ。女性の担当者がクルマで出向いてくれた。「テレビを消させてくれないんじゃ。テレビに出ている人が、消すな、と言うんじゃ」など、ジイジはいかに自分がテレビをやめたくてもやめられないか、縷々語ったそうである。私は、介護保険制度を利用することにした。四〇歳以上の人が加入者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用する仕組みである。
町では「地域広域連合」を保険者として介護保険を運営している。二〇二三年に要介護一となり、介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まった。家族や親類以外にジイジを気にかけてくれる人ができたというだけで大きな安心である。
そして二〇二五年がくる。