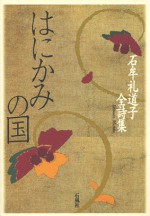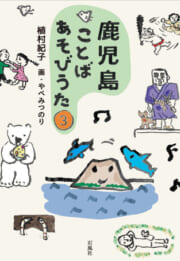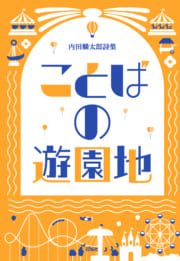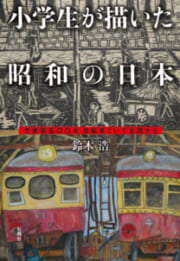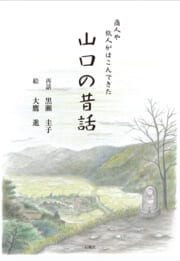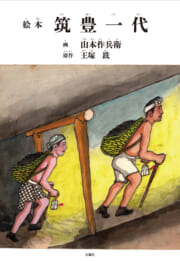◇かかりつけ医
ジイジの散髪のため、山鉾理容店に電話した。
「わしは、がんになった。できません」という。
「体調をくずした」などといわず。「がんになった」とモロに言う。
八〇歳代のご主人は、阿波踊りの連も率いる酔狂人である。ジイジはもう何年も山鉾に通っていたのだ。「病をのりこえたら、またオヤジの髪をきってやってください」。
このようにして名物店が消えてゆくジイジの町である。
同じ通りの高尾理容店に行った。ここには私は子供のころによく行き、行くたびにご主人から五〇円もらっていた。中は昭和そのもの。旧いエアコンが熱風を吹きつけてくる。
三代目という四〇歳代の主人の腕はたしかで、「念が入っとる」とジイジは満足した様子。料金は三五〇〇円。山鉾より三〇〇円安い。
店をでるとゴーストタウン。隆盛を誇った真鍋酒店も大和屋薬局もシャッターがおりている。猫の子一匹歩いていない。
ジイジが長年通う丸上医院はゴーストタウン街の東の外れにある。現在の院長は丸上洋医師。五〇代半ばと思われる。院長の両親も同じ場所で開業しており、私も幼い頃からずっと診てもらった。一〇〇年以上の歴史がある病院だ。
住民は頼りにしているのであるが、丸上院長は患者と話をするのが苦手のようである。世間話ができない。おとなしい。いつもうなだれている。「丸上先生は聴診器をあてないのですよ。このへんのおじいさん、おばあさん、先生に診てもらった人はみんな、言っていますよ。胸の音を聴かないで、健康状態が分かるのか、と」とタクシーの運転手から聞いたことがある。コミュニケーション障害? に起因する消極的診療が敬遠され、過疎化などでただでさえ少ない患者が、他地域の医療機関に流れている様子なのだ。
丸上医院のスタッフは院長のほか、受付の女性、女性看護師四人、なのであるが、謎の男がひとりいる。院長よりも年長の坊主頭のこの男性(便宜上、山法師と呼ぶ)が、事務員なのか、看護師なのか、薬剤師なのか、分からない。
職種は分からないが、取りまとめ役であるらしい。軍隊でいえば軍曹である。ジイジは便秘と高血圧解消のため丸上に通う。診察時間の確認などで、ジイジの付き添い者たる私に山法師が電話してくることがある。かけてくるときも「丸上医院です」と言うのみで自分の名を名乗らない。そこがまずヘンである。
地域包括支援センターと相談していた頃、丸上医院から「ヘルパーさんをつけてはどうだろうか」と電話をもらったことがある。毎月ジイジの様子をみてくれている医院ならではの配慮である。いま思えばそのとき電話をくれたのは山法師であった。野太い男の声に、医院の内情をまだよく知らない私は丸上先生なのかと思ったが、「先生の意見では早急にヘルパーさんを……」などと言うので丸上医師本人ではないことが分かった。名乗らないので何者かけっきょく分からない。だからというわけではないが、ヘルパーさんの件はこの時点ではウヤムヤになってしまった。
「午後四時ごろ行く」と連絡しているのに、午後四時ごろ、「まだですか。忘れていませんか?」と電話をかけてきたこともある。私は医院の入口でその電話を受けた。スマホで話す私を見た山法師は苦笑して受話器を置いた。ほかに患者はいないのである。催促する理由が分からない。
ある日、山法師はジイジに「おしっこ、とってくれますか」と紙コップを差し出す。私が介助して尿をとる。提出して、丸上先生の診察にのぞむ。先生は尿について言及しない。支払いのとき、「検尿の結果は?」と聞くと、看護師ら女性たちは山法師を見る。山法師は検査を忘れていたのだ。医師と連係していない。彼はあわてて検査する。山法師は私を呼び、「異常ないようです」と言う。「丸上先生の見解は?」と聞いてもいいのだが、事を荒立てたくない私は黙ってカネを払う。
山法師は受付のあたりにいつもいる。看護師らのテキパキした動きに比して、山法師のオッサンらしい鈍重な動きは、医療の流れのなかのノイズといえないこともない。わが家に来てくれる訪問看護師はジイジのクスリの確認のため丸上医院に時折行くのである。「あの坊主アタマの人が丸上先生だと思っていました」と言う。院長の存在感が希薄なため、山法師が目立つのだ。
晴れても雨でも風がふいてもジイジは丸上医院に行くのである。医院の評判などはそもそも気にしない。医者は丸上だと決めている。むかし、「ミユキ野球教室」という日本テレビ系列の番組(一九五七~九〇年)があり、野球好きのジイジも私もよく観ていた。テーマ曲「紳士だったら知っている♪ 服地はミユキと知っている🎵」というのが印象深かった。それにならって、「わがジイジは決めている♪ お医者は丸上と決めている🎵」と歌いたい誘惑にかられる。
「丸上先生のご両親にもよく診てもらったなぁ」と私が振ってみると、「そうか? 丸上医院には初めて行くぞ」とジイジには通じない。「丸上医院に初めて行くの?」と問うと、「えっ、高松までゆくのか」と話がかみあわない。高松はお隣香川県の県庁所在地であり、ジイジの家からだとクルマで二時間くらいかかる。私にもジイジにも馴染みのない土地である。「丸上」が「高松」とどうして結びつくのか。「むかし、丸上に行ったとき、ワシの叔母さんのダンナがおって、この人が左官でなぁ。原付バイクでどこへでも行くんじゃ。そうじゃ、猪ノ鼻峠を越えて、高松まで行ったことがあったなぁ」というようなことでもアタマをよぎったか。ジイジの発言は突飛ではあるが、まんざら根拠のないことではないのだ。
◇免許返納
ジイジが運転免許を返納したのは二〇二五年二月一八日である。九二歳で返納したわけだ。元気な高齢者はだれしもそうだと思うが、ジイジも免許を手放すのを渋った。
田舎でクルマがないと不便である。不便というより、独り暮らしの年寄りにしてみれば、致命的である。ジイジの住んでいる地域は、自宅から三〇分歩いても店がない。日々の食が困る。退職して職場からも離れてしまって、クルマもないとなると、時間を持て余す。生き甲斐をもてない、という話にもつながる。
ジイジが九〇歳代になっても、私は、返納を促すどころか、「運転の職人」とジイジを持ち上げてきた。「職人」はまんざらウソではない。もう半世紀以上運転しているのだ。ハンドルさばきなど堂に入っている。左右確認なども入念におこなう。どうせ運転するのなら、自信をもって運転してほしい。だから私は、「職人」とジイジを持ち上げた。
それともうひとつ、ジイジの軽自動車はミッション車であり、オートマチックに慣れた私はミッション車を運転する自信がなかった。たまに帰省しても、申し訳ないと思いつつ、ジイジの運転するクルマの助手席に乗っていたのだ。
これではいかんと思って、ジイジのクルマが広い場所にさしかかった折など、「練習させて」と代わって運転してみたりしていた。ギアチェンジ時に多少ぎくしゃくするが、それだけ気をつければ問題ない。もう少し慣れればミッション車を克服できるぞ、と思った。
免許返納を先延ばしにしているさなか、思いがけないことが起こった。クルマを運転中のジイジが警察に保護されたのだ。保護されたのは自宅から東(徳島市方面)へクルマで一時間余り、まったくなじみのない町である。知らない土地、見慣れぬ街並み、眼前の光景は次々に変わってゆく……。ジイジの不安と恐怖はいかばかりか。窮した挙句、クルマから降り、通りがかりの人に助けを求めたらしい。パトカーとともに代行運転で自宅に戻ってきた。
このときジイジは警官に「家内と二人暮らし」と申告したらしい。ジイジの地元の池田警察署の警官がソファの上の私の母の遺影を確認し、「実際は一人暮らし。認知症がすすんでいる」と判定した。翌朝、池田署の女性署員が私の携帯に電話をしてくれたのである。スマホの画面に徳島県の地元警察署の番号が表示されたとき、私はジイジの死を覚悟した。変死したと思ったのである。「クルマごと保護された」と聞いた私は安堵しつつ、「早急に運転をやめさせる」と約束した。
それでも、のど元過ぎれば熱さを忘れる。ジイジに状況を振り返ってもらっても、「道を間違えたんじゃ。大げさに考えるな」と平然としており、「そうかもしれない」と思う自分がいた。このまま返納せずにしばらく様子をみるのもアリか。クルマがなくなるとジイジは困るものなあ、とジイジのために先延ばしするように考えをもっていった。逃げたのだ。しかし、事態は容易ならない段階に入っていた。
警察に保護されてから約二カ月後の夜、また警察から電話があった。スマホに表示された番号を見て、「今度こそ重大事件・事故が起こった」と観念した。徳島市近郊を管轄する名西署である。最初の警告を無視したのだから、この結末は仕方がない、と思いつつ電話に出ると、今度は前回よりさらに遠く、徳島市の手前の石井町での保護である。繰り返しの息子的感慨になって読者には申し訳ないが、一時間半も知らない道をよく行ったものだ。アタマはともかく運転技術はまずまずなのである。今回も警察官がジイジの家まで来てくれて、壁にはってある連絡先に私の名をみつけ、連絡してくれた。二回目の保護ということもバレていた。私は若い警官のソフトな対応に感謝した。叱責とか難詰とかではなく現状をありのままお知らせします、いう感じである。「免許は返上させます。めいわくをかけて申し訳ない。三度目はありません」と約束した。
落ち着いたのち、電話でジイジと話してみると、さすがに「やってしまった」感は深く、声は沈んでいるが、「岡山まで行ってきた。徳島ではない」と一部事実をボカして論点をズラそうとする。わけがわからないまま運転していたのとは違う。明確な意思があったのだという主張である。
数日後、徳島県警本部から「運転を継続するなら、医師の診断書が必要」という通告があった。当然の成り行きであろう。認知症がすすんで運転はもう無理なのは明白なのだが、警察は免許の取り扱いには慎重である。権力をふりかざして強引に返納させることはしない。あくまでも自主的な返納を求めてくる。
ジイジには気の毒だが、私にとってはチャンス到来である。「警察が免許を返納しろと言ってきた」と返納の大義名分ができたのである。事実は既に述べたように「運転を継続するなら、医師の診断者が必要」という免許継続への希望をのこしたものであったのであるが、ジイジは教習所の認知検査も軽々パスしてきた。「運転は可能」という診断書を書く医師がいないとも限らない(現実には診断書を書くのは山上先生である。先生もジイジがクルマで医院にくることに懸念を示している)。「警察が免許を返納しろと言ってきた」というとウソになるが、私がそう言わなければ事態は動かない。ジイジは、警察に保護されて代行で帰宅した屈辱の記憶が生々しいこともあって、「そうか、警察が言うてきたか」と返納を承諾した。
私は、ジイジの軽自動車の助手席にジイジを乗せ、警察署に連れて行った。ミッション車に慣れた私は自分の意思で変速する運転を新鮮に感じていた。もう運転をジイジに頼ることはない。私が代理で返納してもよかったのだが、ジイジが実際に警察署に行った方が、「免許返納」がアタマに刻まれると思ったのだ。せっかく返納しても、本人に「免許を返納した」という自覚がないならば、なにかの拍子にハンドルを握らないとも限らない。
クルマは廃車にはしないことにした。福岡市在住の私ではあるが、今後、徳島に来る機会が増える。クルマは必要だ。ジイジもクルマに愛着がある。妹のスエコによると、このクルマの購入時、「これが最後のクルマになるなぁ」と母が父(ジイジ)に言ったそうだ。クルマは存続したが、ジイジのクルマへの未練も存続することになった。