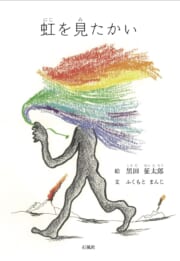「日常の間合い」で衝迫
写真家ユージン・スミスの制作過程を垣間見たことがある。今では封印されたが、胎児性の水俣病患者である娘を風呂場で抱きかかええる母子の写真である。七〇年代初め、スミス氏は廃屋のような一軒家を水俣に借りていた。そこに張り巡らされたロープには、このピエタのようなプリントだけが数十枚も吊り下げられていた。一枚一枚焼き付けが違うのだが、私にはどれも同じように見えた。しかし写真家にとっては、その微妙な違いの中から選び出された一枚こそが「作品」であったのだ。
この山口勳写真集「ボタ山のあるぼくの町」(海鳥社)は、ある意味その対極にある写真によって纏められている。
山口勳は炭坑夫を父として生まれ、自らも坑夫の経験を持つ。その後の経歴を見ると、「65年従軍カメラマンとしてヴェトナムへ渡り戦火の中の民衆を取材」となっているので、歴戦のフォトジャーナリストのように思えるが、どうもそうではない。
それは写真を見ると分かるのだが、この人の写真は対象に「肉迫」していない。どこか対象との間合いがあるのだ、それもごく自然な空気のようなものが漂っている。路地で遊ぶ子供も洗濯するオバサンも、フンドシ一丁のおじさんもみな屈託がない。日本近代や工業化社会の矛盾としての筑豊という、ジャーナリスティックな視点の欠如というより、そういう視点からおおらかにこぼれ落ちた六〇年代の庶民の日常が、無造作に差し出されている。
いわば身内の人間が、顔見知りの炭坑生活者の日常を空気のようにとった、ということはあるだろう。しかしこの人の写真には、ただの写真好きや人柄のよさを越えた衝迫がある。それは、内部の人間でありながら、カメラをもった途端外部として排除されるという力学と拮抗することになる。
ガス爆発事故直後を撮った写真は、やはり緊張を見る者に強いる。その中の一枚、事故で亡くなった遺体を十数人の仲間が物言わず見つめている。その幾つかの厳しい視線は、カメラそのものにも向けられているのである。