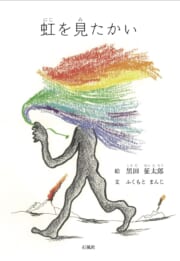毒と愛情交じる詩人論
毒と愛情がないまぜになった不思議な味わいの詩人論である。自己批評と品性を備えた文章の後味は悪くない。
本書は、石原吉郎をはじめ著者と「激しく」親交のあった五人の詩人たちの「思い出」を綴ったものである。全て故人だが、ただの追悼文や詩人論と思って読むと、血が泡立つほどの毒にあたる。
五人のうち著名な詩人は表題の石原ひとり。しかし生真面目ゆえに屈折し「痛々しい詩を書くことになる」杉克彦や人を魅了する詩を書きながら「どんなことも喜びの方角へもっていくことのできない辛い性癖」の詩人北森彩子について記された文章も胸に響く。
一九七七年に亡くなった石原吉郎はすでに伝説の人である。七〇年前後に学生であった私達には、シベリア抑留体験を記した石原の散文集『望郷と海』の衝撃は深かった。それは過酷な体験を「告発することなく」、ひたすら己を凝視することで抽出された、苛烈で美しい思想と受け止められた。
若かった読者が持つ石原像は、日本に生還したものの、身内や世間から拒絶され、孤独のなかで詩作(思索)し、孤独に死んでいった修行僧のそれであった。
しかし著者は、そんな「世間一般」の理解や本人のエッセイの中には、「真の石原吉郎はいない」と言い、「散文の仕事はあくまでも詩の付録」と言い切る。
初めて会った頃、石原は「詩だけを見なさい。詩に直接関係のないことに惑わされては駄目です」と著者に言ったという。その孤高に見えた詩人が次第に詩壇の賞や世俗的序列にこだわりはじめ、嫉妬や浮世の淋しさに翻弄され、孤絶のなかで「毀れて」ゆく。
痛ましくはあるが、その作品や人物を貶めるものではない。むしろ石原の世俗的な「一断面」をとば口に、これまで語られてきた幻想を引き剥がし、詩作品本来のあるべき場所へ定置し直そうとしている。そうすることで、私たちも石原の詩作品の再発見という現場に立ち会うことになる。
作品は、作品そのものに語らせるのが原則である。本書を読むと、純粋なる作品と俗なる表現者の関係という、ありふれたしかし解きようのない問題にも行きあたり、作品の再読を促される。