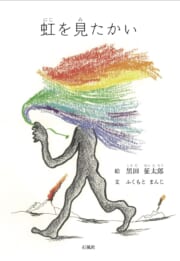私が松浦豊敏さんに初めてお会いしたのは、43年前のことである。日にちも忘れない。1970年5月24日、場所は東京の某所。翌25日には、厚生省(当時)の一室で一任派と呼ばれた水俣病の患者さん達に、チッソからの低額で理不尽な調停案が提示されようとしていた。それを実力阻止するための作戦会議の場で四十代半ばの氏に会ったのである。私は二十代初めの若造で、松浦さんが谷川健一氏(民俗学者)、雁氏(詩人)とも親しい労働運動のオルグとは知る由もなかった。短髪長身の松浦さんは、逮捕必至の行動について淡々と指示を与えた。
松浦さんは、翌年東京を引き上げ熊本市の喫茶店のマスターとなった。「カリガリ」という水俣病患者支援の梁山泊となった店で、氏を「水俣病闘争」の作戦参謀として迎えるための受け皿でもあった。はじめは料亭を作ろうなどという話もあったが、結局身の丈にあった十坪ほどの店になった。夜は支援者やジャーナリストの寄り集まる酒場となり、私もほぼ毎日そのカウンターに屯していた。
1973年3月に水俣病第一次訴訟の判決が出て、チッソとの自主交渉を行うため患者さんの戦いの場は東京のチッソ本社に移った。それまでの二年間の支援の現場で、松浦さんは寡黙で無駄のない指揮官だった。それが一区切りした七三年の秋、「暗河」という季刊雑誌が創刊された。その責任編集者が石牟礼道子・渡辺京二・松浦豊敏の三氏だった。私もこの雑誌の編集を手伝うことになったが、迂闊にもこの三氏が、水俣病問題以前から文学の領域で深く関わる関係にあったことを知らなかった。松浦さんは詩人だったのである。
詩人の魂をもった労働運動家で、『争議屋心得』や『ロックアウト異聞』という著書もある氏を語るのに欠かせないのが、その軍隊体験である。松浦さんは熊本の旧制宇土中学を卒業した後、中国大陸に渡っている。陸軍大佐河本大作の率いる国策会社で共産軍の動静を探る特務についた後、十九歳で現地徴集され「冬部隊」の一兵卒になった。華北からビルマまでの五千㌔という日本軍最長の行軍を敢行した部隊である。仲間が飢餓と病で次々と落命する中、松浦さんも栄養失調で落伍するが、それでもベトナムまでの四千㌔を歩いたのである。この部隊は徴発という名の略奪を繰り返しながら「身も心も乾いて枯れて」歩くミイラとなりながら南下した。この消耗戦を一兵卒の独白として、雑誌「暗河(くらごう)」の創刊号に書いたのが「越南ルート」である。この作品は、安易な共感や理解を拒否する戦争の実相を綴ったものだが、兵士の心身にとって戦争体験とは何かをみごとに描ききっている。イデオロギーと倫理を排した己への視線は、凡百の戦後文学にはなかったものである。
私は出版社を営むようになって、「戦争体験を核にした自伝を書きませんか」とお願いしたことがある。「カリガリ」のカウンターの隅で書き物をしていた松浦さんは、老眼鏡をとりちょっと間をおいて「今さら言うても分からん」とさびしそうに微笑んだ。私はその後「暗河」に掲載された松浦さんの四篇の小説を再読し、編み直せば見事な自伝的小説集になることを発見し、恥じた。それを一昨年『越南ルート』として出版したのだが、やはり松浦さんのことが何も分かっていなかったのだと自戒する。
今は松浦さんという人に、この世で逢えたことを感謝するだけである。