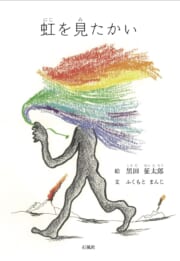「酔狂人・仁三郎」
お相撲さんが中洲をうろうろする頃になると、フグの季節である。
フグで思い浮かぶのは、博多の酔狂人・篠崎仁三郎(にさぶろう)のことである。仁三郎は、博多大浜の魚市場髄一の大株、湊屋の大将で、若い頃からの悪僧(わるそう)。父親が亡くなるや博打にふけり始め、心労で母親も後を追い、あげくに身代をつぶして嫁さんにも逃げられる。「親不孝の見本は私でございます」と言いつつ、進退窮まれば瀕死の友人の生き肝を担保(かた)に酒を飲むなど、とんでもない型破りのにわか的人生を送った人物である。
仁三郎は、九州日報時代の夢野久作に「博多っ子の本領」について問われて、「死ぬまでフクを喰ふこと」をその条件の一つに挙げている。フグはもちろん猛毒があり、今でもこの季節になると、肝かなにかに中毒(あた)った話が必ず新聞に載る。私が知っているだけで、この数年の間にわが町内で二人が死にかけた。
この仁三郎というお人は、カナトフグにはじまりトラフグは言うに及ばずナメラという極めつけまで試し、四度死にそこなった。あたったときの気分は、軽いものは、目が回りふらふらと足がしびれ、何ともいい気持ちだという。ひどいと唇の周りからしびれ始め、次に腰が抜け手足の感覚がなくなり、目がボーッとかすみ口も利けなくなるという。
仁三郎のフグ喰いは、道楽にしても年季が入っている。乳離れしたばかりの頃、父親がフグの白子を食べさせるので、母親があわてて止めると、「甘いこと云うな。フクをば喰いきらんような奴は、博多の町では育ちきらんぞ。あたって死ぬなら今のうちじゃないか」と、これまたとんでもない親父だ。
四度目にあたった時は、白目をむいてぶっ倒れているので、いよいよダメだと、棺桶まで持ち込まれた。ところが本人は、耳は聞こえるし意識もはっきりしている。その時の恐ろしさは、「エレベーターの中で借金取りに出会ったようなもん」だったという。さぞ怖かったろう。
さて、前にも書いたが、夢野久作は「福岡県人中に見受来る面白からざる気風に対し、一服の清涼剤を与ふる目的」で『近世快人伝』を書いたと記している。「面白からざる気風」というのは、拝金主義や舶来趣味に軽薄神経過敏な世相をいっているのだが、その世相に対抗するのに、福岡士族の末裔である玄洋社系の人物たちと並べて、この酔狂なる博多町人を挙げている。現代の市民社会的規範から見ると、「清涼剤」どころかどちらも顰蹙(ひんしゅく)ものである。時代批判として、「ちょっといい話」なんぞを持ってくるヤワな美談精神とは、肚(はら)が違う。
ところで久作は、この博多町人に何を仮託したのだろうか。もちろんにわか的なナンセンスにたいする評価がその底流にあるが、さらに自分自身をも笑いものにできる精神の自在さへの、深い共感があるように思える。
これは結果として政治から抜け出せなかった、玄洋社的なものへの批評であるとともに、市民社会的良識で貧血気味の私たちの精神に対する、批評としての毒でもある。
1995・8〜12
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)