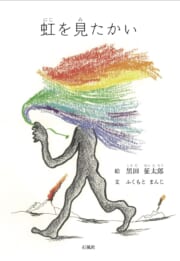「トリックスター」
一時はやったフリーターというのはどうなったんだろう。バブルがはじけると、「ちゃんとしなくっちゃ」という言葉とともに、新保守の潮流がはじまったようだが、そういう流れとともに「ちゃんと」就職するか、ただのアルバイトに戻ったのだろうか。
私の知り合いで、いつ会っても、何をして食っているのかよく分からない男がいた。絵を描かない絵かきで、十代のころは、早熟の才で何か賞も取ったようだが、私が福岡で知りあってからの彼は、絵を描いているという様子はなかった。共通の知人であるピアニストの山下洋輔さんが、「若いときに才能を認められると後がつらいんだよな」と言ったことがある。
絵は描かなかったが、会うたんびにいい女を連れていた。女性はいつも若かった。20代の時も30代の時も40代になっても、いつも二十歳(はたち)そこそこの女性を連れていた。皆なかなかに魅力的な女性たちで、賢そうだった。
男は長身長髪で、ヒッピーというよりは、大正期の壮士風だった。金はないけれど卑屈にならず、人の懐にすっと入ってくるようにどこか憎めないところがあった。居候と踏み倒しの天才で、しばらく顔を見ないなと思っていると、ふらりと現われて、東京のだれそれの家にしばらくやっかいになっていたと言った。次々と居候をハシゴをしながらそれぞれに「とっておきの話」を運ぶ、消息の移動民のようなところもあった。
たぶん好奇心の強い娘たちにとっては、市民社会のどこにも所属しない自由で危険な魅力を発散する男だったのだ。そして娘たちが、数年をおかずに彼の元を去っていったのも、同じ理由からだったのだろう。
私が知り合う前の彼は、福岡の前衛美術集団の最年少でぶら下がって、そのグループと行動をともにしていたという。彼が仲間とともに高等学校の屋根の上で、すっ裸のハプニングをしている写真を見せてくれたこともあった。その時期が彼にとっても「華」だったのかもしれぬ。
彼がくっついていた前衛美術集団の画家たちは、破天荒で個性的な人物たちだったが、時間の流れの中で、それぞれにところを得ていった。だが、彼ひとり「ちゃんとすること」をからかうように、何もしなかった。
時がたち、「反芸術」を標榜した年上の画家たちが個展を開くようになると、彼は不思議な嗅覚でもって会場に現れた。ニコニコとニタニタの中間ぐらいの笑みを浮かべて、まるでトリックスター(道化)のように先輩たちの作品を眺めて、愉快そうに酒を飲んでいた。
こういう人物というのは、端(はた)で見ていると面白いが、始終そばにいられると、自分のなかにある俗物根性を批評されているようで、うっとうしくなることが多い。それでも、福岡の街に「ちゃんとした」人間ばかりが多くなると、時々懐かしくなる。
火葬場で男の立派な頭蓋骨を見た夜、したたかに酔っぱらった私と葦書房の久本三多は、取っ組み合ったまま飲み屋の急な階段を転げ落ち、そのまま六本松の交差点の路上まで転がっていった。
男は、絵を描かない絵かきだったけれど、自身がなかなかの作品だったのだと、今にして思う。
1995・8〜12
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)