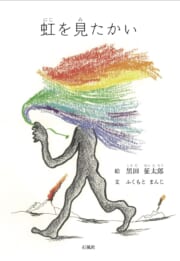「石の家」
15年前に不思議な人物に会った。明治41年生まれの生粋の福岡人。私が会った時には悠悠自適の暮らしぶりで、目の光の強さと意志的な鼻梁を除けば、小柄でおだやかなご老人に見えた。
しかし初めて訪ねた時に遭遇した家族どうしの議論にぶっ飛んでしまった。内容は自分たちの長年住み慣れた家を壊すかどうかということなのだが、その理由が普通じゃなかった。
その家は福岡市南郊の、なだらかな斜面の住宅地にある、おおきな岩に守られた、さながら城塞なのだ。
隠し砦(とりで)のような入り口から螺旋状に階段をくぐり抜けると、千坪ほどの庭がびっしりと石に覆われている。それは石庭などという情緒的なもんじゃない。うろこのある巨大な爬虫類の背中のようでもあるし、大洪水が家を飲み込もうとしたまま凍りつきひび割れ、そのまま石と化したようにも感じられる。
呆然とする私の前で、老人はにこにこ笑いながら、「これは、作品じゃなかもんな」とおっしゃる。
老人は、昭和の初めから天神で寿司屋を営んできた。といって、石の庭が職人芸のたぐいかと言うとその手の玩物(がんぶつ)趣味ではない。小さいもので数百キロ、大きいものになると数トンの石は、山から掘り出されたままの原石なのに、それぞれが、削らずともぴったりとくっつきあうようにして斜面をはっている。
このおびただしい数の石を、老人は、丸太にチェーンブロックひとつで、四十年かかって敷きつめたのだ。
「私が置いたっちゃなか、石が私に置かせたっちゃもんな」
石たちは、増殖するように斜面を覆い、波うち、あるいは塔を形づくっている。老人の家族がすむ日本家屋は、石の海原に浮かぶ孤島のような風情で、石に侵入された玄関はすでに取り壊されていた。
いやが上にもテンションのあがってしまった私は、注がれる酒に、底なしのバケツだった。酔いつつ脳髄が凍りついた私の前で、二つの意見が激突したのである。
一方は、「石が家に侵入しようとしているのは、なにか深い意味があるのだ。だから家を取り壊そう」。片や、「しかし人間がここに住んできたことも無意味じゃない。だから壊しちゃダメだ」。要約するとそういうことになる。
さて、この夜の結論はどうなったか。ご老人は四年前に亡くなり、石の庭は福岡市に寄贈された。
近い将来公開される。その時、自分の目で確かめてほしい。
1995・8〜12
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)