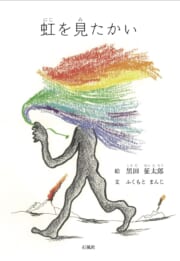「この世の一寸先は闇」
アパートを出て、地下鉄工事中の道路を横切ろうと信号待ちをしていた。
すると、ヘルメットを被り歯のない口でニコニコ笑いかけてくる男がいる。工事現場の交通整理員の制服を着ている。バーPのマスターだ。意表を突かれて、「どうしたとですか?」と尋ねると「いゃ、こういうことです」と自嘲気味に笑った。歩きながら、心のどこかが粛然(しゅくぜん)となった。
その数カ月前、マスターは焼き肉屋でアルバイトをしていた。私が町を自転車で走っていて偶然出会うと、「店を閉じて今はバイトをしている」と言う。その焼き肉屋に幾度か通ううちに、マスターはその店を辞めていた。年は50をいくらか過ぎている。潰れた店の借金を抱えた身では、そうそう再就職も楽ではないだろうと、少し気になっていた。
潰れた店も、再起をかけて移転新装した店だった。だが、一年と持たなかった。古い方の店に初めて連れていってくれたのは、亡くなった同業先輩の久本氏だった。二人で飲んだくれたとき、屋台すら閉まる明け方に、まだ開いてる店があるから行こうという。その店がPだった。そんな時間にも吹き溜まりのように飲んでいる客がいた。
マスターは、若い頃メキシコに行っていたといい、ショータイムと称しスペイン語の歌を歯のない口で生真面目に歌った。仕事一筋で、こまごまと動きまわり、酒は一滴も飲まない。店にはフィリピーナやメキシカンもいて、それなりに猥雑で活気もあり、二次会、三次会によく使った。
バブルの崩壊とは関係ないはずだが次第に客足が遠のきはじめ、フィリピーナ達を雇うこともできなくなっていった。窮したマスターは、眠る間もなく昼の定食をはじめた。薄暗いボックス席で食う焼き魚定食は、もの悲しくわびしかった。ある日印刷を頼まれたチラシを持って店に行くと、マンションの駐車場に通じる裏口からもうもうと煙が出ている。慌ててドアを開けると、ガス台の上のフライパンの油が燃えており、初めて見るキッチンは狭く雑然としていた。マスターは、店のソファでぐっすり眠り込んでいた。
マスターのそもそもの本業は占い師である。全国紙の占いの欄を担当した程の実力もあり、そのての本の出版の相談も受けた。しかしあまりに商売が上手くいかないので、姓名判断で自分自身改名してしまった。
私も今の事務所に移る前に、観てもらった。
「とてもいい運気だ。仕事も増える。10年たったらもっといいところに移りなさい」
マスターの言葉を信じていいものだろうか。
(1998・9月)
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)