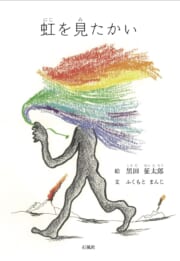IT産業の現代的寓話
小倉魚町に、読書人によく知られた金榮堂という書店があった。店のウインドウには、いつも推薦する書籍の一節が、無骨な手書きで張り出されており、棚には主人の見識で集められた本が有機的に並んでいた。金榮堂に行くと、求めようと思った本以外に何冊もの関心を惹く本を手に取らされた。この小さな書店を思い出したのは、「アマゾン・ドット・コムの光と影」を読んだからだ。
アマゾンは、世界最大のオンライン書店として知られているが、創業者のベゾスが目指したのは、チェーン店や巨大書店ではなく、「小さな書店」だったという。一見矛盾する発想だが、実はそれこそがアマゾンの独創なのだと著者は言う。
つまり、日本のリアル書店は、これまで新刊の洪水に翻弄され、顧客の求めるものを見極める余裕がなかった。ところがアマゾンは、顧客データをもとに読者の好みにあった需要を予測し、次の仕入れや商品開発にまでつなげている、ということである。
私達が大型書店で本を買っても、書店員から貰うのは訳の分からぬチラシぐらい。しかしアマゾンの場合、一冊の本を購入すれば、「小さな書店」の顧客の好みを熟知した店主のように、さまざまな情報を提供して客の購買欲を刺激すると言う訳である。
これは、アマゾンの「顧客第一主義」、いわば光の部分である。ところが、光があれば影もある。著者は、福岡出身の元・物流業界紙編集長で、実はこの本、秘密主義で知られるアマゾンジャパンの物流センターへの潜入ルポである。その労働現場は、注文の本を一分間に三冊ピックアップすることがノルマの、徹底的にマニュアル化された冬場も暖房なしの空間である。過酷な条件に辞める人間も多いが、システム至上主義で、人間は次々と補充され、さらに時給は下がる。
人間味のある「小さな書店」を目指す巨大なITビジネスは、徹底的に非人間的なシステムによって支えられているという、現代の寓話である。