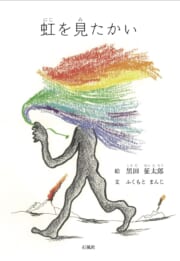「大衆演劇」
久しぶりに福岡市内で筑紫美主子一座の佐賀にわかを観た。
筑紫さんは、旭川生まれの佐賀育ちだが、現在糸島に居を構え、福岡とは非常に縁の深い方である。筑紫さんの芝居ならば、何はさておき駆けつけるという熱烈なファンが、福岡だけで千人は下らないだろう。
今回の公演は、舞台生活55周年記念。この20数年筑紫さんの芝居を観てきたが、あらためて筑紫さんのすごさをみた。私は、くり出される言葉に、全身を揺すぶられ、腹の底から笑った。
話のすじは、妻に病死され乳飲み子を抱えた男(客演・常田富士男)が、思いあまって男の子を捨ててしまう。それを拾った貧しい夫婦者も育てる育てないで離婚したあげく、妻(筑紫美主子)が引き取る。それから二十五年がたち息子も立派に成人し、事情はあるが気だてのよい嫁をもらう。そこへアメリカで富豪になって帰国したという実の父親が、息子探しにやってくる。そこでのてんやわんや。
ストーリーはいくぶん時代がかっているが、今回は筋書きそのものより、その中で繰り広げられる姑と嫁のやり取りにみんな笑い転げた。それは、筑紫さん扮する姑の嫁いびりである。この姑がとんでもない意地悪ばあさんで、ことごとく嫁をいびる。もちろん姑は、捨て子から育て上げた息子を嫁にとられたというさびしさから嫁いびりをするわけだが、実際のやり取りをみていると、このばあさん、嫁いびりそのものが楽しくてしようがないという感じなのだ。その佐賀弁の絶妙さ!
通常の物語だと、最後には意地悪ばあさんも、自分の非を悔いて、嫁さんと仲直りする。ところがこのばあさん最後まで善良な嫁さんをたたき出そうとする。不思議だがそれがみるものを奇妙に自由にする。やり取りのおかしさが、どこか善悪を超えているのだ。
これまで筑紫さんの芝居にいわれてきたことは、筑紫さんの、白系ロシア将校との混血という出自にはじまる苦難の人生と、観客(庶民)の人生が重なり合って、泣き笑いの大衆演劇ということになる。筑紫さん自身も、失恋して死のうと思って飛び込んだお堀に水がなく、泥に足を取られてもがいているうちに、今度は死んじゃならんと大騒動している自分の姿が、滑稽でおかしくみえたのが、自分の芝居の原点だという。悲しみの極限が反転しておかしみに変わる。
そのことはわかる。しかし今回の芝居のおかしさと解放感のすごさは何だろう。大げさにいうと、筑紫さんの視線は人間を超えちゃったのではないかと思った。つまり姑の嫁いびりを純粋に徹底することで、人情や勧善懲悪の世界を突き抜ける。そのことで、私たちをがんじがらめにしている「期待される家族関係」からしばし解放する。私の深読みかもしれないが、嫁いびりの場面における観客のアナーキーな笑いのすごさと、それをみて微笑んでいる観音様のような筑紫さんを、思ってしまった。
1995・8〜12
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)