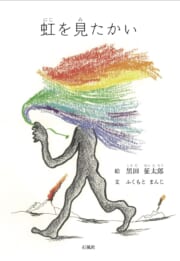「バブル」
新聞で、信用金庫や銀行の相つぐ破綻が報道されている。これまでも、土地ころがしによる錬金術のからくりは露呈していたが、ようやく地金がでてきたわけだ。正直に言うと、銀行の不良債権の総額が40兆円以上あるときいて、なぜかほっとした。金額が予想より小さいという意味ではない。バブル絶頂時に、世の中に氾濫していたお金に対応する実体が、経済音痴の私には、どうしても実感できなかったからだ。
当時福岡にもトーキョー・マネーが大量に流入した。まさにボーダーレスな金は、国境を越えて外国の建築家たちやデザイナーをも招き入れた。ラブホテルがシティーホテルになり、有り余った金にいくらかの罪悪感を感じた企業は、メセナという名で文化支援を吹聴した。あいまいホテルの前宣伝にガルシア・マルケス原作の作品を上映する不動産屋まで現れた。
土地は高騰し続けた。路地や暗がりが消滅し、海が埋め立てられ、街の表情がのっぺらとハイカラに、まるで映画のセットのようになっていった。
しかしどう考えても、それまで坪50万だった土地が1000万円になる原理がわからなかった。そこには通常の需給関係を超える力が働いているとしか思えなかった。それを動かしていたのが虚構の40兆円=不良債権だとわかって、ようやく腑に落ちた。そもそも実体は無かったのだ。
欲に踊らされてどんちゃん騒ぎをしていたものが、一夜あけたら担保の黄金が肥えダメに変わっていたというやつで、こういうからくりは、破綻してこそ自然の理にかなう。
さてバブル経済は崩壊したが、私たちが高度消費社会の中で生きていることには、いささかの変化もない。その消費活動は、衣食住を維持するための必須の消費(エンゲル係数という言葉がなつかしい!)より、快楽を基準とする選択自由な消費がむしろ主流になった。
かつてはご馳走だったカレーライスがサラリーマンの昼飯になったように、今では毎日がお祭りである。用意周到で質実なアリの経済から、破滅を先送りする豪奢なキリギリスの経済にテイクオフしたわけだ。
バブル最盛期にはやったコピーに、「おいしい生活」(糸井重里)というのがある。文化活動に熱心な東京のデパートのものだが、楽して質のいい暮らしがしたいという、バブル時の気分を的確に表した見事なコピーだ。今私たちは、「モノはもう十分だから、心の豊かさがほしい」と言っている。深読みすれば、「よりおいしい生活を!」ということだ。
気分はまだバブルなのだ。
もちろん人間の欲望を、無限に解放していこうとする現在のシステムに対し、清貧の倫理や精神主義で批判する風潮は常に存在する。しかし経済活動が、私たちの欲望が作り出す幻影をモチーフとしている以上、このバブルという怪物を退治するのは、一筋縄ではゆきそうにない。
1995・8〜12
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)