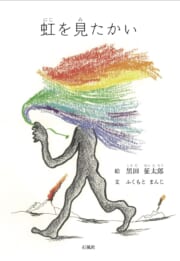「よそ者」
ある時、台湾の友人が「福岡の人はタマゴみたいです」と言う。
「ふむっ」(まだこれからということかな)
「福岡は、外国人に対してはじめはガードが堅いですが、いったん殻を破ると、あとはとことんやさしいです」
彼は大阪の日本語学校で一年間勉強した後、博多にきて三年。大阪の人は、はじめからくだけた調子でひとあたりもよかったが、結局ふみこんだつき合いはできなかったという。
「そとは柔らかくて甘いですが、中には堅い種があるモモみたいです」
さすが比喩の国の人だ。
彼の言うようにこの町にはあくの強い排他性は感じられない。共同体が強く残っているところでは、外部の人間がいるといないでは、まるっきり見せる表情が違うものだが、伝統の祭山笠(やまかさ)の舁(か)き手にはよそ者がゴロゴロいる。はじめのとっつきの悪さも、いわば町っ子らしいシャイな気質のあらわれだとみればわかる。
私もよそ者だが、博多に住んで21年、仕事をするうえで地の人間にことさらに仁義を切る必要もなかった。それまで暮らした鹿児島や熊本という地方都市に比べると、ここには格段にひとを自由にする空気がある。
都市としての豊かさの指標は、一般にはひと・モノ・カネの質に、サービス・情報・交通網の完備ということになるのだろうが、私には、よそ者や外国人のような異質の者をいかに自由にふるまわせるかという、その自由さのキャパシティにあると思える。道交法とのイタチごっこを繰り返しながら屋台が町にあふれているのも、異質なものに対する町の寛容があるからだ。そういう意味でこの町はよそ者には暮らしやすい。
で、この自由な空気は、どこに由来しているのだろうか。古来アジアに開かれた交易都市としての伝統だろうか。それとも東京マネーによって「再開発」されつつあるのっぺらぼうな町の光景を、自由と勘違いしているだけだろうか。
冒頭の「タマゴとモモ」のはなしを、生まれも育ちも福岡の知人にしてみた。彼はアジアの山岳地帯で、独自の民間協力をつづけている骨のある人物である。
「そうねー、関西人は表面は軽そうやけど、意外と芯があるもんな。博多んもんは、芯がありそうで、案外中へはいるとぐじゃぐじゃやね」
「うーん」