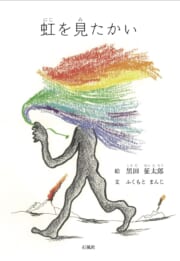エロス漂う宮本民俗学の原点
宮本常一氏の代表作である『忘れられた日本人』は民俗学の古典といってもよい作品であるが、農民や漁民のくらしを、戦後の早い時期に土地の古老から聞き取ったものである。私にとって時折読み返す数少ない一冊であり、外国に赴任する友人には必ず薦める一冊である。
この本に収録されている「土佐源氏」を読んだのは、もう二十年以上前になる。その時私は。盲目のもと馬喰が語る色懺悔にぞくぞくする感動を覚えた。土佐檮原の橋の下にすむ老乞食は「いちじく形の頭をして、歯はもう一本もなく頬はこけている」。盲目になったのも極道の報いであるといいつつ、父なし子であったこと、子守り娘たちとよからぬ遊びをしつつ育ったこと、そして馬喰としての無頼の日々を、かいこが糸を吐き出すように語る。「人は随分だましたが、牛とおなごだけはだまさなんだ」という色懺悔のクライマックスは、身分違いのお方様との密通である。牛のまぐわいを息を詰めて見つめ「牛の方が愛情が深いのかしら」というお方様に馬喰は、「この方はあまり幸せではないのだなあ」と思いを致す。匂いたつエロスは、ふたつの渇いた魂の飢えが、越えられない身分差の裂け目に流れ込むところに、成り立っている。
『忘れられた日本人』には、夜這いや歌垣そして田植え時のエロ話のように、おおらかなエロスも通奏低音の一つとして流れているのだが、数代を遡れば私たちの大半がそうであった「百姓」の原像のようなものが記されている。それはいかに美質であっても復活かなわぬものだが、それを記憶としても失えば、私たち日本人の魂の核を亡失するに等しいと思える何かである。
この短い文章でそれを伝えるのは難しいが、例えばこういう話である。
対馬の民族調査に行った宮本氏は、昼間精力的に聞き書きをした。村に入るにも徒歩で米持参の時代である。その聞き書きを整理し、夜を徹して古文書を筆写する。膨大なエネルギーだが、インターネット時代の私たちが何を失ったか、瞭然とする。
写しきれないので文書を借りたいと申し入れるが、返事は数時間待っても来ない。区長に連れられて「寄り合い」の場に行くと、会場の板場に二十人ばかり、周りの樹に三人四人と寄り掛かり話し合っている。話し合いはもう二日に亘り、「夕べも明け方近くまで話し合って」いたという。文書の話も朝方でて文書を巡るさまざまな古い話題に広がりつつ、いまはまた別の話に移っている。途中食事に帰る者もあれば眠る者もいる。話し合いは自在に行き来しながらも結論が出るまでじっくり続けられた。
さらに四ヶ浦の共有文書を見たいと頼むと、半日ほどの連絡のあと、それぞれの総代が羽織袴姿に正装して小舟でやってくる。協議のあと借りた古文書を一昼夜掛けて写して返すと、総代たちは月の出た夜の海に、お礼も受け取らずに漕ぎ出してゆくのである。(2004/06 雑誌「モンタン」に掲載)