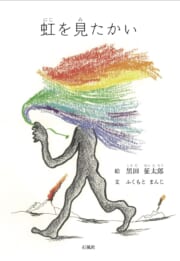渡辺京二さんとお城沿いの道をカリガリに向かって歩いた。こんな風に2人で歩いたのは何十年ぶりだろうか。「人はそれぞれ考えが違うけれど、愛(いとお)しいものなんだよ」という渡辺さんの言葉が胸に響き、私は春の宵の中で不思議な温かさのなかにいた。
カリガリというのは熊本市中央区城東町にある喫茶店で、夜は飲み屋になる。1971年10月に開店し、すでに43年の歳月が流れたことになる。その店が今月いっぱいで閉じるということになり、3月16日に全国から200人以上が駆けつけ、「さらば、カリガリの日々」という集まりがあった。渡辺さんは、そこでの挨拶で、「人と人とが出会う場をつくるということは、これは大事業です」とおっしゃった。渡辺さんの先の言葉は、その会場を出てカリガリに向かうときのことである。
私は福岡で出版業を営んでいるが、他人(ひと)より長い学生時代を熊本で過ごした。福岡に40年住んでいても、いまだに友人関係のコアは熊本にあり、それが培われたのがカリガリだった。店が開店した時期は、60年代末に高揚した全共闘運動の終末期で、この店もいくらかデカダンな空気を纏っていた。ただそんな学生気分の青臭さを包むように、戦争や戦後の思想的苦闘を経てきた大人たちの存在が、店の重心を支えていた。
独特の空気が漂う飲み屋なのだが、その異色さは曰く言い難い。店主は昨年亡くなった松浦豊敏さん、今は連れ合いの磯さんが切り盛りしている。松浦さんは、華北からベトナムまで4千キロを一兵士として行軍、死線をくぐった人で、戦後はラディカルな労働運動を指揮、複数の著作を持つ作家でもあった。ただ文化人という言葉にはそぐわない雪駄と手ぬぐいの似合う長身短髪、含羞の人だった。
この店には、さまざまな人間が出入りしたが、その核になるのが「水俣支援」だった。そもそもカリガリは、松浦さんを水俣病闘争の「指南役」として迎えるための受け皿としてできた店だ。裁判闘争からチッソとの直接交渉まで、ここは作戦本部でもあり、梁山泊でもあった。水俣病研究会や機関誌編集やミーティングの場でもあった。
開店当初は、石牟礼道子さんがカレーを試作し、肉もでかくて美味かったけれど、コストがあわずにお蔵入りした。石牟礼さんは、ここで原稿を書いていたこともある。
運動にひと区切りつくと、雑誌「暗河(くらごう)」が発刊された。石牟礼・渡辺・松浦3氏の責任編集による思想・文芸誌だった。私はこの雑誌の編集を手伝うことで出版の世界に踏み入ったのだが、迂闊なことに石牟礼さん以外の2人が、「文学」の世界の人などとは思いもしなかった。
私たち文学に縁のない若い者(もん)は、ここを足場に浅川マキや山下洋輔のライブ、「黒テント」の興行を打った。大学の禁止告示を無視しての興行で、気分はアンダーグランドだったのである。「カリガリ」という店の名も、ドイツ表現主義の無声映画「カリガリ博士」から、私が提案したものだった。
この店は、夕暮れになると報道関係者や研究者のたまり場となり、詩人も小説家も絵描きもやってくる。月並に言えば、文化とジャーナリズムの坩堝みたいな店である。しかし不思議なことに「地方文化人」のにおいはしないのである。多分ここには、世界に開かれた「批評性」が、電流のように流れていたのだと思う。風土に深く根ざしながら、地方に閉じない知性。ただの飲んだくれの集まりにみえて、怠惰に陥ると席がなくなる、世に稀なる空間だったと、今にして思う。
これからは、カリガリとともに齢をとった私たちが、世に試されてゆくことになる。