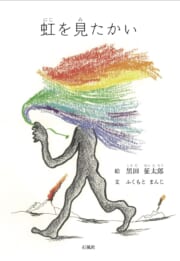「屋 台」
夕暮れになるとどこからともなく屋台があらわれ、雑踏の中に灯がともる。無表情なビルの壁に、肩を押し合うように並んだのれんの中からラーメンのにおいが流れ、焼酎の香りがただよう。猥雑と喧噪の中で、街がふうっと息をつき、くつろいだ表情を取り戻す。
最近、行きつけの屋台のおやじの表情が暗い。客のいない席にぽつねんと座っていたりする。ここのところ売り上げがずいぶん落ちているらしい。猛暑のせいだけではなさそうだ。
大将が東京でのサラリーマン生活に見切りをつけて、屋台をはじめて10年がすぎた。娘さんも短大にいれ、そこそこの暮らしも維持し、あのとき思い切って博多に来てやはりよかったと思う。長浜や中洲の観光屋台と違い、近所の常連の顔を眺めての商売は、不器用な自分にもむいている。
あとしばらく頑張って、屋台の権利をそれなりの値段で人にゆずり、次の人生を考えようと思っていたところに、オカミから道路使用許可について厳しいお達しがきた。
福岡県警の道路使用許可は、「屋台業者本人に限り、許可の譲渡については、現在屋台を手伝っている親族以外は認めない」というものである。娘さんにはその気がないのでこの屋台は自分一代で終わり、これまでの苦労が泡のように消える。
営業時間の規制も厳しくなった。夕方6時から翌朝4時ときまっているが、これまでは4時ぎりぎりまで営業していたものを、4時には片付け終えねばならなくなった。この実質一時間の営業短縮で売り上げが半分近くに落ちた。
もちろん県警だって屋台が憎くて規制しているわけじゃない(と思う)。その強い姿勢には市民の根深い苦情が背景にある。いわく、通行のじゃまで、悪臭がして非衛生的だ。加えて観光客から法外な料金をとる屋台の横行。欲がのれんをぶら下げたような屋台は論外だが、通行の障害になるとか、非衛生であるとか、美観を損なうとかいう「良識」には異論がある。
ソウルオリンピックの時には、韓国では屋台を表通りから閉め出そうとしたが、幸いにしてユニバシアードのわが福岡市ではそういう話は聞かなかった。むしろ街の顔のひとつとして積極的に評価しようという空気になりつつある。かつてGHQ(連合国軍総司令部)と厚生省が屋台を廃絶しようとし、それに抗して組合の人々が死闘を展開した時代を思えば、隔世の感がある。
私たちが子どものころに比べて、街も人も明るくこぎれいになった。はな垂れ小僧もいない。DDTで頭からシラミを駆除し、虫下しで寄生虫を体から追い出して、つまるところアレルギー体質になったように、バラックやホームレスを排除したあげく、再開発と称して都市は衰弱してゆく。
屋台が存続するかどうかは、オカミによる「規制」でも市民の文化的「保存意識」でもなく、私たちにわずかに残された雑菌的「体質」にかかっている。
*2012年2月17日、福岡市は、「原則一代限り」としている屋台営業について、公募による参入を認める方針を明らかにした。しかし、それまでグレーゾーンの中で認められていた屋台の営業権の譲渡は禁止。「原則一代限り」に変りはない。
1995・8〜12
(石風社刊 『出版屋の考え休むににたり』
「博多 バブル前後 1990年代」より再録)