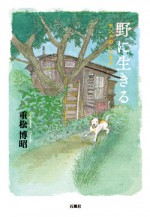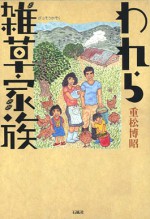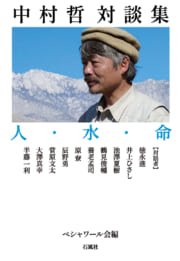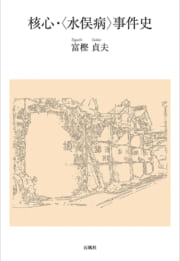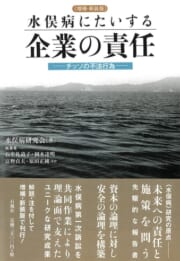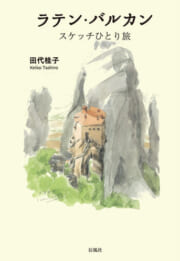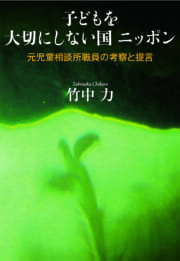この7月下旬から8月半ばの連日の炎暑に、風邪をひきまくる馬鹿がいるのだから我ながら面倒見切れない。生命体の肝腎な所が弛(たる)んでいるというか淀んでいるというか。きつい時ほど無理やりにでもとにかく動き回り、汗をぐっしょりとかいて心身のだるさを洗い流す、そんな体力もいよいよなくなってきた。この所よく熱が出る。37度2~5分は私にとっては何十年ぶりかの高熱だ。
いいこともある。足腰が頼りないので、いつものようにせかせかとではなく一足一足土と草を踏みしめ雑草園を登る。しばしば立ち止まる。日の出前の雲一つない白一面に青がにじむ。ふっと心和む微風。笹や蕗(ふき)やミョウガの葉に浮かび滑る露の玉…久しぶりにゆったりと木々を眺めやる。改めて驚くほどに天高くあるいは四方八方にあるいは横に分厚く、各自勝手奔放に生い茂っている。金木犀、泰山木、ねむの木、柿、李(すもも)、モクレン、桜…山の主のようににくすんだ掘っ立て小屋を包む栗、銀杏、南天、アジサイ、梅、グミ、梨(なぜか原種に返った石梨、かぶりつくと歯が折れそう、さわやかな甘味)、柿、茶(この5月、ほぼ一年分摘み、揉んだ)…その上の全部で十aほどの段々畑も、ユリノキ(大きな花が大量の蜜を出すとか)、ハゼ(その気になれば蠟が取れる)、桑(実はもちろん、葉も蚕になった気分で食べると素直な味)、八朔、ビワ(葉は貴重な常備薬)、ブルーベリー(ひと夏かけてノンが収穫とジャム作り)、ナツメ等の目を見張る勢いに日陰が多くなった。さらに上は元栗山、樹齢70年以上の巨木数本は今もたくさんの実を落としてくれる。あとクルミ、柚子、山桃、杏子(あんず)、イチジク、コナラ(椎茸の榾木に)、椿(やれば実から油が)、樫、柴…
実は私はほとんど世話らしい世話をしたことがない。これらはノン独りの作品だ。できるだけ余計なことをせず(出来なかったともいえるが)、この地に合った木を(合わなかったものは自然消滅した)できるだけ金を使わず(そもそもなかった。野生あるいは自生、実から育てたり、枝や苗を貰ったり)、あくまで自分たちが食べるもの、食べたいものを、あれこれと。私たちには別にそういう気はなかったのだが、この「雑木園」がこれからの日本の里山のあり方の一つを示しているかもしれない。木々が深く根を下ろし、落ち葉が分厚く地面を覆い、炎暑・干ばつにも大雨にも強い。保水力も豊かだ。様々の植物が無理なく雑多に共存しているので病気・虫にも強い。いくつかがやられても他が補ってくれる。養鶏(平飼い・放し飼い)にも最適だ。この猛暑でも鶏小屋は人間小屋より涼しい。「卵の会」会員を募り、ついでに季節の果物・野菜等も配達する。草刈りや収穫等に家族連れで参加してもらうのもいい。「遊びの学校」も「癒しの里」もいい。
雨なしの炎天下、トマトはさっさと枯れ、ナス、ピーマン、エンサイの茎や葉にはカメムシが隙間もないほどにびっしり。マサメの元気のいいこと、まるで葛(くず)のように周りの雑草に絡みつきさらに伸張しようとしてる。キュウリは初めての大豊作、完熟たい肥やもみ殻等をたっぷり敷いたのが効いたのだろう。つる紫、オクラ、花オクラも健闘、里芋はなんとか踏ん張っている。いずれも畑を起さず、刈った草や堆肥を敷いていくだけ。おかげであちこちに青じそが勝手に芽を出し香りのいい葉を茂らせている。三つ葉も。ヨメナやハコベ、よもぎ等も摘んで食卓に。カボチャは見る見る畑を覆い尽そうとしている。この「不耕起雑草栽培」も、ますます深刻に日常的になる「異常気象」に対応する方法の一つでは。大雨にも表土が流れず、旱魃時にもふかふか。草が嫌いでなければ誰でもできる。ちょっと油断すると草の林になるのが難点だが。
8月後半、まさに恵みの雨。強烈な日差しの後の夕暮れ時、もしくは夜の初めに、ほぼ連日。昔のせっかちで豪快な夕立とは違い、遠慮深い。ササーと空が暗くなってもなかなか降らない。夜になって思い出したように爽やかな天のシャワーが風のように降り注いでくる。待ってましたとばかりに雑草たちは一気に荒々しく茂った。私の方はまだ鬱陶しい熱の日々だ。コロナと一般のインフルエンザのウイルス検査はマイナス、細菌感染もなし。最初は内科の次に漢方の風邪薬を飲んだ。いやー久しぶりによく眠った。夜10時間、午前午後1時間ずつ。朝5時半から気分のいい1、2時間に1日分の餌やり(緑餌のための草取りも)をすませた。あとは休みの合間に卵取り、それに配達。
早くも9月に。ナス、ピーマン、エンサイは復活した。あの腰から下が萎えてしまいそうなだるさは大分取れた。微熱は少し下がったが続く。風邪薬は止め、いつもの漢方煎じ薬だけにした。できるだけ身体を休め、最低限の仕事だけは確実にこなさねば。季節がら、その最低限が大変なのだ。秋冬野菜の種まき、何より栗拾い。鹿、猪、アナグマ等々の侵入だけはなんとしても防がねば。でもマア、当分、気分のいい時だけ、やれるだけやるしかない。もともといい加減でぼんやりするのが好きな男なのです。それがこの1か月以上の夏休みでますますフニャフニャと投げやりになってしまった。要はただ生きて死ぬ、それ以上に大切なことなどないのです。話は大きくそれるが、科学技術の「進歩」によって、不死が実現する、いつまでも生きていけると信じている人々がけっこういるらしい。私などつい産業廃棄物処分場に打ち捨てられ永遠に腐らない膨大なプラスチック類の残骸を思い浮かべてしまう。どうも現代物質文明の最先端にいる少なからぬ方々は、自身が生き物であることを忘れている。あるいは生き物が嫌なのかな。生き物をやめたい、生き物を超えたい、だから「生き物でない人間」AI・ロボット製造に血眼になるのかも。一方、超ものぐさ・面倒くさがり屋の私としては、死そのものはむしろ救いなのです。大地に、天に返るのだから。死があるから生がある。愛(かなしみ)がある。
ハッサン(雌中犬、15歳7か月、白・黄土色、ビーグル・ラブラドル等の雑種)の最期を私がはっきりと意識したのは7月6日の夜半に目覚めた時だった。一部屋おいた切り炬燵のある板張りからハッサンの少し荒い息遣いが聞こえてきた。ひどく生真面目にせかせかと。身の内に残る命の熱を排泄しているような。もう4日、食べていない。近頃家のあちこちによく落としあるいは漏らしていた排泄の跡もこの所まったくない。水は飲んでいる…
数か月前、一見猛犬だが心優しい力持ち・モモが来て以来、その世話(年寄りに力仕事)に追われ、ハッサンのことはほとんどノンに任せっきりだった。
足腰がすっかり弱るまでは、車で出かける時いつもハッサンが助手席だった。 毎朝、雑木林へと登り、自由散歩をした。たまに林の奥に姿を消すことがあったが、すぐに帰ってきた。夏は掘っ立て小屋の土間に穴を掘って涼しげに横たわり、冬は薪ストーブを囲んだ。秋には、猪、鹿、アライグマ、アナグマを追い、その猛烈な追跡中にマムシにかまれ、春は菜の花の光あふれる川原を走った。いつもそう遠くないどこかにいた。ペットではなかった。相棒だった。生活者だった。ただ生きていた。
8日、相変わらず息遣いは荒いが、表情は平静。ユラユラと一歩一歩草の道を踏みしめ、掘っ立て小屋の前の草原に登ってきた。久しぶりにマッサージ、毛が抜ける、抜ける、抜けたら少しは軽くなって楽になるかな。
夜中に2回、今までにない大きな声で鳴いた。じっと座ったままだった。翌朝4時、ハッサン鳴く、起こしてやると、奥の部屋に行き横になった。5時半、自力で外に出た。門の前で寝ていた。少し安心した。じわじわと闇が薄れていった。8時前、玄関前に横たわって動かない。静かな表情で、目を開けて、生きているよう。すぐにノンを呼んだ。死んだという実感がまるでわかなかった。でも、生きてはいない。
今から考えてみると、悲しみ方がまるっきり足りなかったのだ
2か月近くがたった今
じんわりと生きる力が抜けていくような・・・
心がひび割れていくような・・・
その裂け目から、ぬくもりのこもった涙が、滲み出てくる・・・
完 2025年9月3日