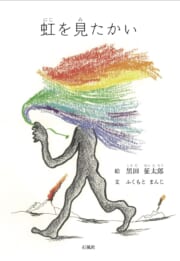一目で気に入った。表情・しゃべり方・動作が初々しく目が生きている。オーストリア人女性(母はマレーシア人、父はイギリス人)、18歳のタラ。前日まで寒空続きだったが、彼女がウーファー(助っ人)として到着した日は快晴、妻が作った昼食のチャンポンを音をたてて(正統派のズズーではなくチュルチュルだったが)汁一滴残さず食べたのもいい。
事が多い。彼女の最初の雑木林への散歩についていったハッサンが通りのすぐそばに無断でかけられた鹿・猪のくくり罠にかかった。彼女は泣き叫んで戻った。私は外出中だった。妻がかけつけた時、ハッサンはわめきもがいた。もがけばもがくほど罠はきつくしまった。我が家の古くからの盟友、材木・家作り業の白金さんに電話、本当に有難いことにすぐに二人駆けつけてもらい、無事ハッサンは救出された。
それにしても私に縁のある女性は事が多い。事が多い女性に惹かれるのか。私自身がしないですめばそれが一番の事無かれだからだろう。妻がいなければ、こんな私にしてみれば波乱万丈の人生は送れなかっただろう。
翌朝七時からタラと犬2匹と私との散歩が始まった。1日目、この冬1,2の寒さ、零下三、四度、山じゅう厚い霜だった。まだ森の中は薄暗い。一面の落ち葉は氷っていない。フカフカサクサクッと茶褐色でコーンフレークのよう。所々淡い光に浮き上がる霜は粉砂糖。彼女に伝えようとしたが、私の英語力、彼女の日本語力、共に力不足だ。黙々と歩いた。クロは私を先導し、時に立ち止まり、嗅ぎ回り、前足で落ち葉と腐葉土をかきまぜ堀りまくる。ハッサンは谷間に下ったり、私達を一気に追い越し、又戻ってきたりと生気あふれる。散歩を終え、私は鶏の餌やり、タラは小屋の肥料出しをしている時、日の出、山じゅうが輝いた。「きれい!」、彼女が小屋から顔を出して叫んだ。
2日目は暗い雨だった。私が外に出たとき、すでに彼女は準備万端。森はまるで湖の底のようで、雨の煙に木立が沈んでいた。「ライクアレイク、湖、わかる?」と言うと、彼女は深くうなずき、じっと谷底をみつめた。
3日目も雨だったがしっかり散歩した。4日目も雨、彼女は森に行きたがったが、この朝だけは下の通りに下り、熊ヶ畑へと登り、下った。霧のような雨に一面田が浮かび、はるか頭上に青々と山々が連らなっていた。
「あなたの住むところは素晴らしいですね。」
とタラはきらきらした目でまっすぐ私を見ていった。「ありがとう」と返すしかなかった。すぐそばにある産業廃棄物処分場のことを英語で説明できそうにないし、わがふるさとが素晴らしいことに違いはない。そこに住んでいる私達がそれをわかっていないだけだ。
5日目の夜、タラと日フィルのコンサートに田川へ出かけた。妻は義母と留守番に回った。1曲目のベートーベンの序曲が終って、左隣に、年配の男性が座った。嫌な予感、ブルッフの流れるようなバイオリンにゆったりと身を沈めようとした時、案の定、重苦しい咳、、そして激しい貧乏ゆすり、なにもかもぶちこわしだ・・・。ふと右隣のタラを見ると、ひたすら曲に没頭して、いかにも幸せな表情だ。
考えてみれば、ある程度金と時間に余裕のある健康な人だけが、咳一つせず、センベイ1枚食べず、お茶の1杯も飲まず、身動き一つせず聞く音楽ってなんだろう。雑音こそ生命の音楽なのかも。
なんてへ理をこねても、やっぱり咳は嫌だったが、3曲目の「展覧会の絵」は良かった。なにしろ大音響で他の音は聞えない。それに次から次へと楽器が主役をかわり見てても楽しい。特に一瞬の芸術・打楽器はスリリングだった。
彼女が帰る7日目の朝、うっすら雪が積もり、東の空は淡い橙色だった。生まれて初めての雪景色にタラは「18年で1番美しい朝」とちょっとさびしそうな笑顔で言った。
いつものことだが生きのいいウーファーさんが去った後はガクリと気が抜ける。エネルギッシュな彼等についつい年を忘れ付き合い過ぎてどっと疲れが出る。妻もそうだ。寂しさもあって、口論になることがよくある。
義母がいてくれて本当に助かる。彼女はどちらの味方もしない。余計なことは言わない。ただ存在している。いつも一日一日を感謝して生きている。それが有難い。
タラが教えてくれたこともそうだった。肥料出し、薪割り、クルミ割り、後片付け・・・とにかく働くことが、生きていることが楽しいのだ。もちろん食べることも、おしゃべりも、眠りも、散歩も・・・すべてが生きる流れなのだ。私のように食べること、飲むこと、眠ることが目的ではない。皆が義母かタラのようだったら、この地球もどんなに生き生きと平和になることだろう。
わずか一週間だったが、三世代が生きる豊かな家族を経験することができた。やはり家族は、社会は、異と異とが共存しなければね・・・血のつながりはあってもなくてもいいのかもね・・・・・